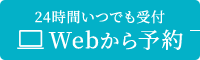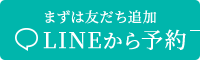「喉(のど)」とは
 「喉(のど)」とは、口の奥から首にかけての部分を指す言葉です。食べ物や飲み物、そして空気が通る大切な通り道です。
「喉(のど)」とは、口の奥から首にかけての部分を指す言葉です。食べ物や飲み物、そして空気が通る大切な通り道です。
- 食べ物や飲み物が通る道(食道へつながる部分)
- 息を吸ったり吐いたりするときの空気の通り道(気管へつながる部分)
- 声を出すための声帯がある部分
などが「喉」に含まれます。
喉の違和感
 喉に何かが引っかかっているような感じや、詰まった感じ、イガイガするような感覚のことです。
喉に何かが引っかかっているような感じや、詰まった感じ、イガイガするような感覚のことです。
喉の違和感の原因と疾患
さまざまな病気が原因となります。
咽頭炎の初期症状
風邪やウイルス感染の始まりでは、まだ強い痛みはなく「イガイガする」「何となくつかえる」といった違和感だけが出ることがあります。
胃酸の逆流
胃食道逆流症などでは、胃から食道や喉に酸が上がってくると、炎症やむくみが起き、喉の違和感やヒリヒリ感の原因になります。
首の腫れやしこり
甲状腺や喉の周囲が腫れると、圧迫されて「何かがある」感じが出ることがあります。原因としては甲状腺が腫大するバセドウ病などがあります。まれに腫瘍が隠れていることもあるため、長引いたり、大きさが増してくる場合は精査が必要です。
ストレスや緊張
咽喉頭異常感症では、強いストレスや疲労で喉の筋肉がこわばり、何かがあるように感じることがあります。
飲み込みの機能の不調
加齢や脳梗塞などの影響で飲み込みの働きがうまくいかなくなると、食べ物やつばが残っているような感じになります。
喉の違和感の検査
喉の違和感は、多くの場合は風邪や軽い炎症による一時的なものですが、長引いたり、強くなる場合には検査が必要になることがあります。当院では、症状に応じて次のような検査を行います。
問診と視診
まずは症状の経過や生活習慣、胃酸の逆流やストレスの有無などをお聞きします。口の中や喉を直接観察して、炎症や腫れ、しこりがないかを確認します。
血液検査
炎症や感染の有無、甲状腺の病気などを調べるために行うことがあります。
画像検査
首の腫れや甲状腺の異常が疑われる場合には、頸部エコー(超音波検査)を行います。放射線を使わず、安全に首の状態を確認できます。
内視鏡検査
診察では観察しきれない喉の奥に病気があることが疑われる場合には、内視鏡検査が有効です。当院で必要と判断した場合には、耳鼻咽頭科へご紹介いたします。
喉の違和感の治療
原因によって治療の方法が異なります。当院では、症状の原因を見きわめたうえで、次のような治療を行います。
咽頭炎が原因の場合
咽頭炎の初期症状で違和感が出ているときは、かぜ薬やうがい薬、必要に応じて抗菌薬を使って治療します。
胃酸の逆流が原因の場合
胃酸が喉まで上がって違和感を起こしている場合には、胃酸を抑える飲み薬を処方します。生活習慣(就寝前の食事を控える、脂っこいものやアルコールを減らす など)の改善も大切です。
甲状腺の腫れやしこりが原因の場合
甲状腺の病気が見つかった場合は、血液検査やエコーで状態を確認します。必要に応じて専門の医療機関へご紹介し、適切な治療につなげます。
ストレスや緊張が原因の場合
強いストレスや疲労が背景にある場合には、まず安心していただくことが大切です。生活リズムを整えることや、必要に応じて安定剤・漢方薬を使うこともあります。
飲み込みの機能が弱っている場合
加齢や神経の病気が関係しているときは、食べ方の工夫やリハビリが有効です。必要な場合は専門医にご紹介します。
喉の痛み
 喉の痛みは、誰もが一度は経験するありふれた症状です。喉の粘膜は外部からの刺激や感染を受けやすく、とてもデリケートです。そのため、炎症や腫れが起きるとすぐに「痛み」として自覚されます。代表的な原因は、喉の感染による咽頭炎・扁桃炎です。
喉の痛みは、誰もが一度は経験するありふれた症状です。喉の粘膜は外部からの刺激や感染を受けやすく、とてもデリケートです。そのため、炎症や腫れが起きるとすぐに「痛み」として自覚されます。代表的な原因は、喉の感染による咽頭炎・扁桃炎です。
扁桃炎と咽頭炎について
 「咽頭(いんとう)」とは、口の奥から喉の奥にかけて広がる部分のことです。風邪のときにイガイガする場所といえばイメージしやすいかもしれません。その咽頭の中でも、口を大きく開けて鏡で喉を見ると、左右に見える丸い組織が扁桃(へんとう)です。免疫の働きをもつ組織で、細菌やウイルスと最初に戦う役割があります。咽頭全体に炎症が広がったものを咽頭炎、扁桃に炎症が強く出たものを扁桃炎、と呼びます。どちらも「喉の炎症」ですが、炎症の場所によって名前が分かれているのです。
「咽頭(いんとう)」とは、口の奥から喉の奥にかけて広がる部分のことです。風邪のときにイガイガする場所といえばイメージしやすいかもしれません。その咽頭の中でも、口を大きく開けて鏡で喉を見ると、左右に見える丸い組織が扁桃(へんとう)です。免疫の働きをもつ組織で、細菌やウイルスと最初に戦う役割があります。咽頭全体に炎症が広がったものを咽頭炎、扁桃に炎症が強く出たものを扁桃炎、と呼びます。どちらも「喉の炎症」ですが、炎症の場所によって名前が分かれているのです。
咽頭炎・扁桃炎を引き起こす病原菌
咽頭炎・扁桃炎はさまざまな病原菌により引き起こされ、その種類により治療方法が異なることがあります。
感冒(かぜ)
もっとも一般的な喉の炎症の原因です。さまざまなウイルスによって起こり、喉の痛み以外に鼻水・鼻づまり、咳、くしゃみ、軽い発熱などを伴います。通常は数日〜1週間程度で自然に回復します。
インフルエンザ
高熱(38℃以上)や強い喉の痛み、全身のだるさ、関節痛や筋肉痛を伴うことがあります。
新型コロナウイルス感染症
喉の強い痛み、発熱、咳、鼻水など、かぜと似た症状を示します。味覚や嗅覚の異常、強いだるさ、呼吸困難を伴う場合もあり、基礎疾患や高齢の方では重症化することがあります。
溶連菌感染症
小児に多い細菌感染ですが、大人でもかかります。急な発熱と強い喉の痛みが特徴で、喉の奥に白い膿のような付着物(白苔:はくたい)が見えることがあります。15分程度の迅速検査で診断が可能です。診断がついた場合には、抗菌薬による適切な治療が必要です。治療をきちんと行わないと、リウマチ熱や腎炎といった合併症につながることがあります。
伝染性単核球症(EBウイルス感染症)
思春期以降の若い世代に多いウイルス感染症です。喉の強い痛みと発熱に加えて、首のリンパ節が腫れる、全身の強いだるさが出るのが特徴です。喉に白苔がつくこともあり、溶連菌感染症と見分けにくい場合があります。診断には血液検査が必要になることがあり、治療は抗菌薬ではなく安静や症状を和らげる治療(対症療法)が中心です。抗菌薬は効果がないため、溶連菌との正しい見極めが重要です。
扁桃周囲膿瘍
咽頭炎・扁桃炎が悪化して、扁桃の周りに膿(うみ)がたまってしまう病気です。飲み込みにくい,口をあけにくい、つばを飲み込めずによだれがたれてくる、などの症状を認めた場合には扁桃周囲膿瘍を起こしている可能性があります。クリニックでの治療が困難な病気ですので、疑われた場合には専門病院を紹介します。
咽頭炎・扁桃炎以外の原因
咽頭炎・扁桃炎以外にも原因となるものがあります。これらは、生活習慣や周囲の環境が関係していることが多いため、治療や対応の仕方も異なります。
胃酸の逆流
胃酸が喉まで上がってきて粘膜を刺激すると、ヒリヒリとした痛みを感じることがあります。
乾燥や刺激
乾燥した空気や、たばこの煙、粉じんなどの刺激でも、喉が痛むことがあります。
喉の痛みの検査
喉の痛みの多くの場合は風邪や軽い炎症による一時的なものですが、長引いたり、強くなる場合には検査が必要になることがあります。当院では、症状に応じて次のような検査を行います。
問診と視診
まずは症状の出方や経過、周囲での流行状況などを詳しく伺います。そのうえで口の中や喉を直接観察し、炎症や腫れ、膿(白苔:はくたい)の有無を確認します。
インフルエンザや新型コロナの検査
流行期や全身症状を伴う場合には、インフルエンザ検査や新型コロナウイルスの迅速検査を行うことがあります。
溶連菌の検査
喉に白苔があり、溶連菌の感染が疑われる場合には、溶連菌の迅速検査を行うことがあります。
血液検査
感染の程度や合併症の有無を確認するために血液検査を行うことがあります。
喉の痛みの治療
喉の痛みの治療は、原因によって内容が異なります。当院では診察や検査で原因を見きわめたうえで、適切な治療を行います。
感冒(かぜ)の場合
多くはウイルスが原因で、自然に回復していきます。治療は安静・水分補給・喉の炎症を抑える薬やうがい薬で症状を和らげることが中心です。
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の場合
症状の経過や発症からの時間によって、抗ウイルス薬を使用することがあります。発熱や痛みに対しては、解熱鎮痛薬を併用します。決められた期間、自宅療養が必要になります。
溶連菌感染症の場合
迅速検査で診断がついた場合には、抗菌薬による10日間の治療が必要です。適切に治療しないとリウマチ熱や腎炎などの合併症につながることがあるため、処方された抗菌薬は指示通り最後まで内服することが大切です。
伝染性単核球症の場合
抗菌薬は効かないため、安静と症状をやわらげる治療(対症療法)が中心です。
胃酸の逆流が原因の場合
胃酸を抑える薬を使用し、あわせて生活習慣(就寝前の食事を控える、脂っこいものやアルコールを減らす など)の改善を行います。
乾燥や刺激が原因の場合
加湿やこまめな水分補給、禁煙、マスクの着用などで喉を守ります。必要に応じて炎症を抑える薬を使うこともあります。
重症の場合(扁桃周囲膿瘍など)
膿がたまっている場合は、抗菌薬の点滴や切開排膿などの処置が必要になります。入院加療が必要になることもあるため、専門の病院と連携して対応します。
溶連菌感染症と伝染性単核球症
 溶連菌感染症と伝染性単核球症は、どちらも若い方に多く見られる「喉の強い痛み」と「喉の奥に白い付着物(白苔:はくたい)が見られる病気」です。外見だけでは区別がとても難しいことがあります。溶連菌感染症の方が頻度は高いのですが、伝染性単核球症に対して誤って溶連菌用の抗菌薬を使うと、効かないばかりか高い確率で皮膚に発疹(湿疹)が出ることが知られています。そのため当院では、どちらか判断がつきにくい場合には、両方にできるだけ安全に対応できる抗菌薬を選んで治療しています。これにより、溶連菌感染症への効果を保ちながら、伝染性単核球症での発疹リスクを減らすことができます。
溶連菌感染症と伝染性単核球症は、どちらも若い方に多く見られる「喉の強い痛み」と「喉の奥に白い付着物(白苔:はくたい)が見られる病気」です。外見だけでは区別がとても難しいことがあります。溶連菌感染症の方が頻度は高いのですが、伝染性単核球症に対して誤って溶連菌用の抗菌薬を使うと、効かないばかりか高い確率で皮膚に発疹(湿疹)が出ることが知られています。そのため当院では、どちらか判断がつきにくい場合には、両方にできるだけ安全に対応できる抗菌薬を選んで治療しています。これにより、溶連菌感染症への効果を保ちながら、伝染性単核球症での発疹リスクを減らすことができます。
よくある質問
喉に何かが引っかかっているような違和感があります。大丈夫でしょうか?
喉の違和感は、かぜの初期症状のほか、胃酸の逆流(胃食道逆流症)やストレスによる咽喉頭異常感症など、比較的よく見られる原因で起こることが多いです。多くは一時的なものですが、甲状腺の病気などが隠れていることもあります。症状が長く続くときには一度ご相談ください。
喉の痛みはすべて「風邪」が原因ですか?
風邪によることが多いですが、インフルエンザや溶連菌感染症、新型コロナウイルス感染症などでも強い痛みが出ます。発熱や全身のだるさを伴うときは、単なる風邪と決めつけず医療機関を受診してください。
喉が痛くて白いもの(白苔)がついています。何の病気でしょうか?
白苔は溶連菌感染症や伝染性単核球症などで見られます。見た目だけでは区別が難しいため、迅速検査や血液検査で診断します。誤って抗菌薬を内服すると発疹が出ることもあり、注意が必要です。
喉の痛みで病院に行った方がよいのはどんなときですか?
強い痛みで食事や水分がとれない、高熱が続く、白苔がある、リンパ節が腫れている、1週間以上改善しない場合などは受診してください。
喉の違和感や痛みはストレスや疲れでも起こりますか?
はい。咽喉頭異常感症といって、ストレスや疲労で喉の筋肉が緊張し、違和感が出ることがあります。重大な病気ではないことが多いですが、続くときは一度ご相談ください。
喉が痛いときに市販薬で対応しても大丈夫ですか?
市販のうがい薬やトローチで症状が和らぐこともあります。ただし、強い痛みや高熱があるときは自己判断せず、医療機関での診察を受けることをおすすめします。
喉の違和感が長く続く場合、がんの可能性もありますか?
喉の違和感が長く続く場合には、まれに腫瘍などが隠れていることもあります。当院では腫瘍の専門的な検査や治療は行っていませんが、必要に応じて専門医をご紹介します。
受診したらどんな検査をしますか?
 まずは問診と視診で喉の炎症や腫れを確認します。必要に応じて血液検査や甲状腺のエコーを行います。当院で判断が難しい場合は耳鼻咽喉科へご紹介します。
まずは問診と視診で喉の炎症や腫れを確認します。必要に応じて血液検査や甲状腺のエコーを行います。当院で判断が難しい場合は耳鼻咽喉科へご紹介します。
喉の痛みや違和感にうがいは効果がありますか?
うがいは喉の乾燥や細菌の繁殖を抑える効果があり、予防や軽い症状の改善に役立ちます。ただし強い炎症や感染がある場合は、薬による治療が必要です。
普段からできる予防法はありますか?
加湿やこまめな水分補給、禁煙、十分な休養が基本です。胃酸逆流のある方は就寝前の食事を控えるなど生活習慣の改善も有効です。乾燥や刺激を避けることが再発予防につながります。