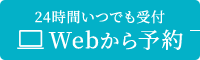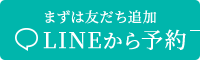健康診断での異常の指摘
 健康診断は、症状が出る前に病気やその前段階を見つけ、早期に対応するための大切な機会です。健診の結果で「異常あり」と指摘されても、必ずしもすぐに重い病気というわけではありません。体調や検査のタイミングによる一時的な変化が原因の場合もあります。しかし、その一方で、初期の段階では自覚症状のない病気が潜んでいることも少なくありません。健診で異常を指摘された場合は、「様子をみればいいだろう」と放置せず、再検査や医療機関での確認を受けることが重要です。健診の結果には、異常の程度や対応の目安を示す判定区分が記載されています。この判定区分は、生活習慣の見直しでよい場合から、早急な精密検査や治療が必要な場合までさまざまです。結果票をよく確認し、必要に応じて適切な行動をとることが、健康を守る第一歩になります。当院では、健診結果の見方や必要な対応について丁寧に説明し、必要に応じて検査や治療を行っています。結果票をお持ちいただければ、その場で一緒に確認し、次に何をすべきかを明確にご案内します。
健康診断は、症状が出る前に病気やその前段階を見つけ、早期に対応するための大切な機会です。健診の結果で「異常あり」と指摘されても、必ずしもすぐに重い病気というわけではありません。体調や検査のタイミングによる一時的な変化が原因の場合もあります。しかし、その一方で、初期の段階では自覚症状のない病気が潜んでいることも少なくありません。健診で異常を指摘された場合は、「様子をみればいいだろう」と放置せず、再検査や医療機関での確認を受けることが重要です。健診の結果には、異常の程度や対応の目安を示す判定区分が記載されています。この判定区分は、生活習慣の見直しでよい場合から、早急な精密検査や治療が必要な場合までさまざまです。結果票をよく確認し、必要に応じて適切な行動をとることが、健康を守る第一歩になります。当院では、健診結果の見方や必要な対応について丁寧に説明し、必要に応じて検査や治療を行っています。結果票をお持ちいただければ、その場で一緒に確認し、次に何をすべきかを明確にご案内します。
健康診断で使われる主な判定方式
健康診断の判定方法は、実施する機関や自治体によって異なります。最も普及している日本人間ドック・予防医療学会などで広く用いられている「A~E方式」の基準を以下に示します。
| 区分 | 判定 | 説明 |
|---|---|---|
| A | 異常なし | 検査結果は基準範囲内で、特に問題はありません。今後も定期的に健診を受けましょう。 |
| B | 経過観察 | 検査値がわずかに基準値から外れていますが、現時点で治療は不要です。医師の指示に従い、一定期間ごとに状態を確認してください。 |
| C | 要再検査・生活改善 | 検査値に基準値からの外れや変化がみられます。再検査や、必要に応じて日常生活の過ごし方を見直すことをおすすめします。 |
| D | 要精密検査・治療 | 病気の可能性があり、より詳しい検査や治療が必要です。早めに医療機関を受診してください。 |
| E | 治療中 | すでに医療機関で治療や経過観察を受けている状態です。治療を継続し、医師の指示に従って定期的に検査を行いましょう。 |
※日本人間ドック・予防医療学会 判定区分の作成過程と意義より引用
健康診断で異常が指摘されることが多い項目について
健康診断で異常を指摘された場合でも、数値の程度やほかの検査結果、症状の有無によって必要な対応は異なります。ここでは、血圧・血糖値・尿酸値・コレステロール・肝機能・尿検査・クレアチニン・腹囲といった、健診で異常が見つかりやすい項目ごとに、基準や対応の目安を説明します。当院では患者様に合わせた管理・治療をご案内しておりますので、下記項目の指摘事項に該当している方はお気軽にご相談ください。
血圧が高い
 C判定(収縮期140〜159mmHg または拡張期90〜99mmHg)は、日本高血圧学会の診断基準でも高血圧に該当します。放置すると脳卒中や心臓病、腎臓病などのリスクが高まるため、できるだけ早めに再検査や医療機関での診察を受け、生活習慣の改善(食事の見直し、適度な運動、禁煙、節酒、体重管理など)と血圧管理を始めることが重要です。一方、D判定(収縮期160mmHg以上または拡張期100mmHg以上)は、治療開始レベルの高血圧です。二次性高血圧の可能性や臓器障害の有無を評価したうえで、原則として薬物による降圧治療を開始します。協会けんぽ(全国健康保険協会)は未治療の方に対して160/100mmHg以上を受診勧奨の目安としていますが、これは保険者独自の基準であり、医学的な診断基準や健診区分とは異なります。健診では140/90mmHg以上で高血圧と診断されます。さらに、疫学研究では115/75mmHg付近から脳・心血管リスクが連続的に上昇することが示されており、「160/100mmHg未満なら安心」という考え方は適切ではありません。C判定の時点から早めの管理が大切です。
C判定(収縮期140〜159mmHg または拡張期90〜99mmHg)は、日本高血圧学会の診断基準でも高血圧に該当します。放置すると脳卒中や心臓病、腎臓病などのリスクが高まるため、できるだけ早めに再検査や医療機関での診察を受け、生活習慣の改善(食事の見直し、適度な運動、禁煙、節酒、体重管理など)と血圧管理を始めることが重要です。一方、D判定(収縮期160mmHg以上または拡張期100mmHg以上)は、治療開始レベルの高血圧です。二次性高血圧の可能性や臓器障害の有無を評価したうえで、原則として薬物による降圧治療を開始します。協会けんぽ(全国健康保険協会)は未治療の方に対して160/100mmHg以上を受診勧奨の目安としていますが、これは保険者独自の基準であり、医学的な診断基準や健診区分とは異なります。健診では140/90mmHg以上で高血圧と診断されます。さらに、疫学研究では115/75mmHg付近から脳・心血管リスクが連続的に上昇することが示されており、「160/100mmHg未満なら安心」という考え方は適切ではありません。C判定の時点から早めの管理が大切です。
血糖値が高い
 C判定(空腹時血糖110〜125mg/dL または HbA1c6.0〜6.4%)は、糖尿病予備群にあたります。生活習慣の見直しを行い、できるだけ早めに再検査や医療機関での評価を受けましょう。一方、D判定(空腹時血糖126mg/dL以上 または HbA1c6.5%以上)は、糖尿病と診断される可能性が高く、できるだけ早めの受診と治療開始が必要です。血糖値が高い状態を放置すると、心臓病や脳卒中、腎症、視力障害などの合併症リスクが高まります。C判定の段階から対応を始めることが重要です。
C判定(空腹時血糖110〜125mg/dL または HbA1c6.0〜6.4%)は、糖尿病予備群にあたります。生活習慣の見直しを行い、できるだけ早めに再検査や医療機関での評価を受けましょう。一方、D判定(空腹時血糖126mg/dL以上 または HbA1c6.5%以上)は、糖尿病と診断される可能性が高く、できるだけ早めの受診と治療開始が必要です。血糖値が高い状態を放置すると、心臓病や脳卒中、腎症、視力障害などの合併症リスクが高まります。C判定の段階から対応を始めることが重要です。
尿酸値が高い
C判定(尿酸値7.1〜8.9mg/dL)は、高尿酸血症にあたります。症状がなくても放置すると痛風だけでなく腎障害や尿路結石、心血管病のリスクが高まるため、食事(プリン体・アルコールの制限)、水分摂取、適正体重の維持など生活習慣の改善(例:食事の見直し、適度な運動、禁煙、節酒、体重管理など)を行い、できるだけ早めに再検査を受けましょう。一方、D判定(尿酸値9.0mg/dL以上)は、症状がなくても薬物治療を含めた管理を検討する段階です。特に痛風発作や腎機能低下がある場合は早急な対応が必要です。C判定の段階でも、生活習慣の改善(例:食事の見直し、適度な運動、禁煙、節酒、体重管理)と経過観察を早めに行うことで将来の合併症を予防できます。
コレステロールが高い
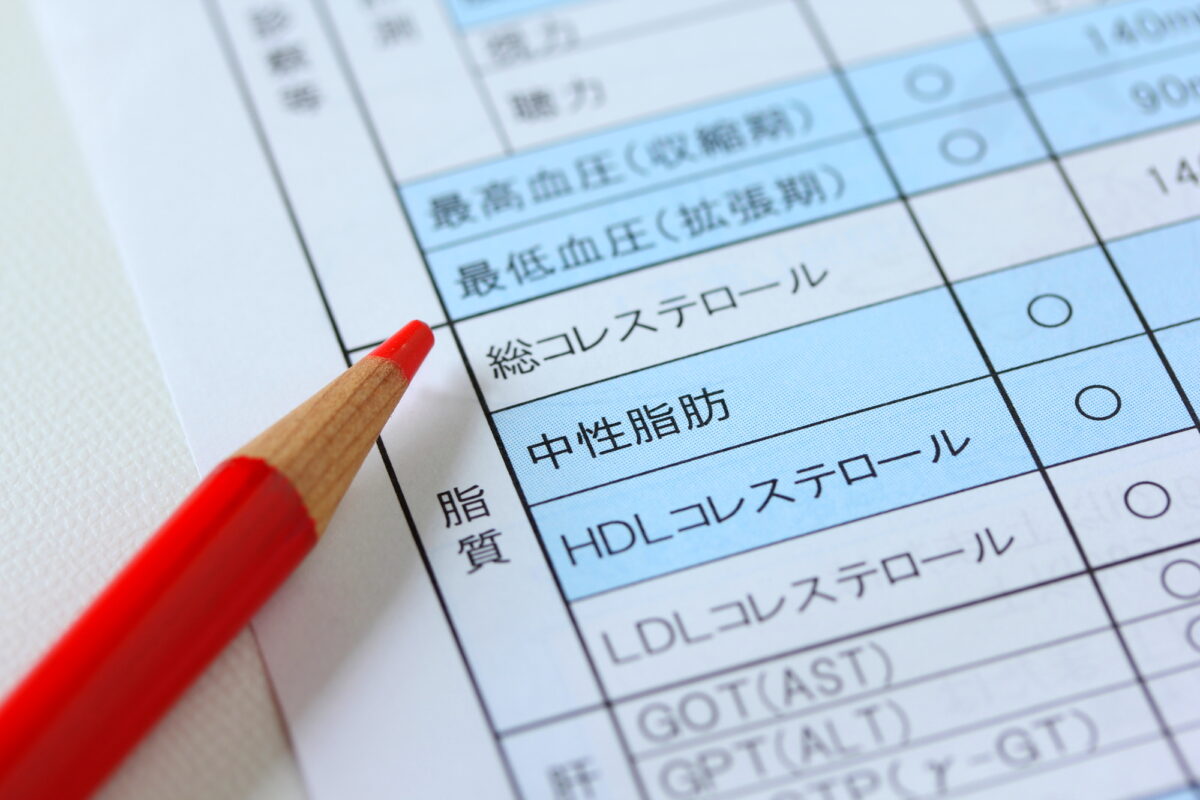 C判定(LDLコレステロール140〜179mg/dL またはHDLコレステロール40mg/dL未満など)は、脂質異常症にあたります。放置すると動脈硬化が進行し、将来的に心筋梗塞や脳梗塞などの心血管疾患のリスクが高まります。生活習慣の見直し(バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、体重管理など)を行い、できるだけ早めに再検査や医療機関での評価を受けることが大切です。一方、D判定(LDLコレステロール180mg/dL以上など)は、動脈硬化の進行リスクが非常に高い状態です。心筋梗塞や脳梗塞の既往、糖尿病、慢性腎臓病などの合併がある場合は、より厳格な管理が必要になります。具体的な管理目標や治療内容は、医療機関で検査結果や全身の状態を踏まえて決定します。C判定の段階から生活習慣の改善(食事の見直し、適度な運動、禁煙、節酒、体重管理など)を始めることで、将来の重大な合併症を予防できます。
C判定(LDLコレステロール140〜179mg/dL またはHDLコレステロール40mg/dL未満など)は、脂質異常症にあたります。放置すると動脈硬化が進行し、将来的に心筋梗塞や脳梗塞などの心血管疾患のリスクが高まります。生活習慣の見直し(バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、体重管理など)を行い、できるだけ早めに再検査や医療機関での評価を受けることが大切です。一方、D判定(LDLコレステロール180mg/dL以上など)は、動脈硬化の進行リスクが非常に高い状態です。心筋梗塞や脳梗塞の既往、糖尿病、慢性腎臓病などの合併がある場合は、より厳格な管理が必要になります。具体的な管理目標や治療内容は、医療機関で検査結果や全身の状態を踏まえて決定します。C判定の段階から生活習慣の改善(食事の見直し、適度な運動、禁煙、節酒、体重管理など)を始めることで、将来の重大な合併症を予防できます。
肝機能障害がある
 C判定(ASTやALTが基準値上限の1.5〜2倍程度、γ-GTPの軽度上昇など)は、軽度の肝機能異常にあたります。これらの数値は、肝臓に現在どの程度の負担がかかっているかを示す指標です。原因としては脂肪肝(飲酒や肥満、糖尿病などによる)、軽度のアルコール性肝障害、薬の影響などが多くみられます。自覚症状がなくても悪化することがあるため、生活習慣の見直し(節酒、体重管理、食生活改善など)を行い、できるだけ早めに再検査を受けましょう。一方、D判定(ASTやALTが基準値の2倍以上、γ-GTPの著明な上昇など)では、数値が高く肝臓に強い負担がかかっている可能性が高いため、速やかな精密検査が必要です。アルブミンや総ビリルビン、プロトロンビン時間、血小板数なども確認し、必要に応じて治療や経過観察を行います。
C判定(ASTやALTが基準値上限の1.5〜2倍程度、γ-GTPの軽度上昇など)は、軽度の肝機能異常にあたります。これらの数値は、肝臓に現在どの程度の負担がかかっているかを示す指標です。原因としては脂肪肝(飲酒や肥満、糖尿病などによる)、軽度のアルコール性肝障害、薬の影響などが多くみられます。自覚症状がなくても悪化することがあるため、生活習慣の見直し(節酒、体重管理、食生活改善など)を行い、できるだけ早めに再検査を受けましょう。一方、D判定(ASTやALTが基準値の2倍以上、γ-GTPの著明な上昇など)では、数値が高く肝臓に強い負担がかかっている可能性が高いため、速やかな精密検査が必要です。アルブミンや総ビリルビン、プロトロンビン時間、血小板数なども確認し、必要に応じて治療や経過観察を行います。
尿検査の異常
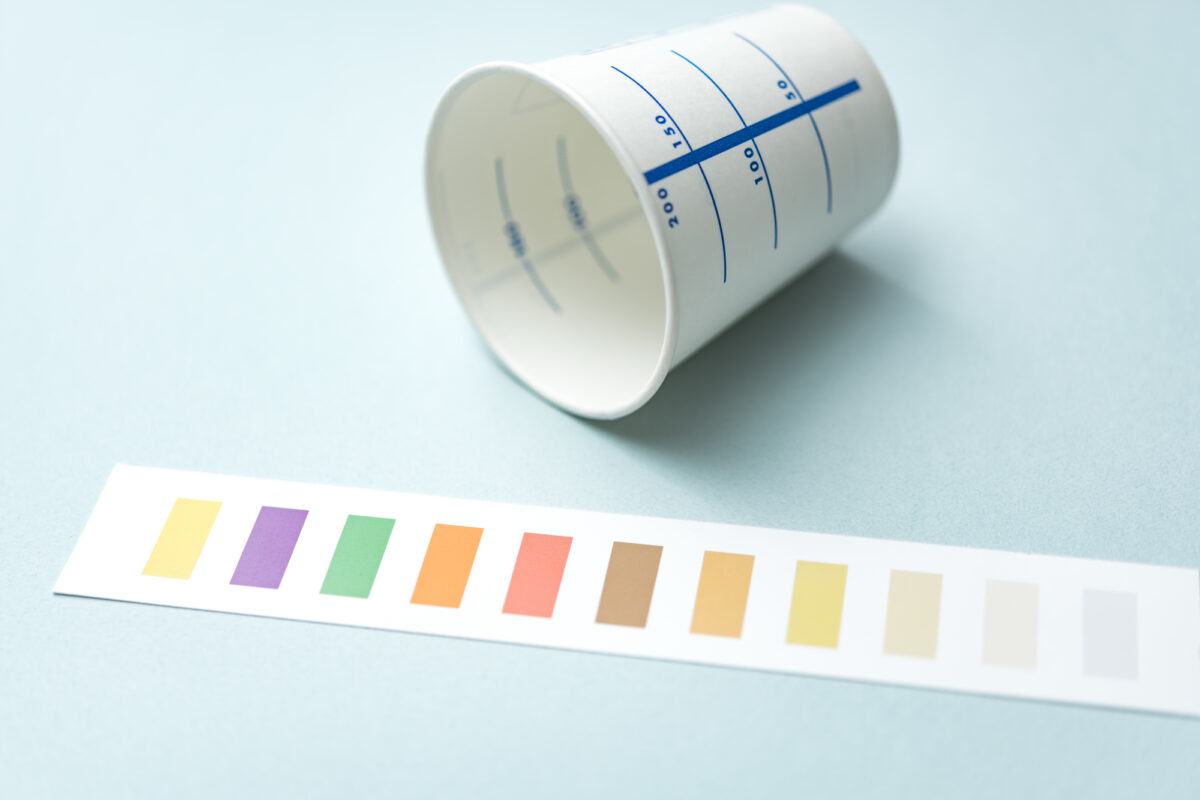 C判定(尿蛋白や尿潜血が軽度陽性、尿糖が軽度陽性など)は、生理的な変動や一時的な体調変化で出ることもありますが、初期の腎臓病や尿路系の病気が隠れている可能性もあります。症状がなくても放置せず、まずは再検査で結果を確認することが大切です。再評価によって一過性の変化か持続する異常かを見極め、その後の対応方針を決めます。一方、D判定(尿蛋白が持続して強陽性、尿潜血が顕著、尿沈渣で異常細胞が確認されるなど)は、腎臓や尿路の病気が存在する可能性が高く、放置すると進行や合併症を起こす危険があります。慢性腎臓病、尿路結石、膀胱がんや腎盂がんなど、早期発見・治療が重要な病気が含まれるため、速やかな精密検査を受けましょう。
C判定(尿蛋白や尿潜血が軽度陽性、尿糖が軽度陽性など)は、生理的な変動や一時的な体調変化で出ることもありますが、初期の腎臓病や尿路系の病気が隠れている可能性もあります。症状がなくても放置せず、まずは再検査で結果を確認することが大切です。再評価によって一過性の変化か持続する異常かを見極め、その後の対応方針を決めます。一方、D判定(尿蛋白が持続して強陽性、尿潜血が顕著、尿沈渣で異常細胞が確認されるなど)は、腎臓や尿路の病気が存在する可能性が高く、放置すると進行や合併症を起こす危険があります。慢性腎臓病、尿路結石、膀胱がんや腎盂がんなど、早期発見・治療が重要な病気が含まれるため、速やかな精密検査を受けましょう。
クレアチニンが高い
 C判定(クレアチニンが基準値を軽度超過、またはeGFRが60未満で軽度低下している場合)は、腎臓の働きがやや低下している状態です。加齢や一時的な脱水、激しい運動の直後などでも数値が高くなることがあります。また、筋肉量が非常に多い人(過剰な筋トレを継続している方やボディビルダーなど)や、蛋白質を多く摂っている場合(プロテイン摂取など)では、腎臓が正常でもクレアチニン値が基準値より高く出やすくなります。ただし、腎臓は一度働きが落ちると元に戻りにくい臓器です。症状がなくても再検査や尿検査で経過を確認し、異常が続く場合は原因を調べて、これ以上悪くならないようにする治療を始めることが大切です。一方、D判定(クレアチニンが明らかに高値、またはeGFRが著しく低下している場合)は、腎臓の働きがかなり弱っている可能性が高く、放置すると将来的に透析が必要になる可能性があります。糖尿病や高血圧、尿路の詰まりなどが原因となることも多く、速やかに詳しい検査と治療を行う必要があります。当院では腎臓内科の専門医として、健診で見つかった早い段階からの治療はもちろん、腎臓の働きの低下が進行した場合の適切な管理まで一貫して行っています。クレアチニンの異常を指摘された方は、症状がなくても早めにご相談ください。
C判定(クレアチニンが基準値を軽度超過、またはeGFRが60未満で軽度低下している場合)は、腎臓の働きがやや低下している状態です。加齢や一時的な脱水、激しい運動の直後などでも数値が高くなることがあります。また、筋肉量が非常に多い人(過剰な筋トレを継続している方やボディビルダーなど)や、蛋白質を多く摂っている場合(プロテイン摂取など)では、腎臓が正常でもクレアチニン値が基準値より高く出やすくなります。ただし、腎臓は一度働きが落ちると元に戻りにくい臓器です。症状がなくても再検査や尿検査で経過を確認し、異常が続く場合は原因を調べて、これ以上悪くならないようにする治療を始めることが大切です。一方、D判定(クレアチニンが明らかに高値、またはeGFRが著しく低下している場合)は、腎臓の働きがかなり弱っている可能性が高く、放置すると将来的に透析が必要になる可能性があります。糖尿病や高血圧、尿路の詰まりなどが原因となることも多く、速やかに詳しい検査と治療を行う必要があります。当院では腎臓内科の専門医として、健診で見つかった早い段階からの治療はもちろん、腎臓の働きの低下が進行した場合の適切な管理まで一貫して行っています。クレアチニンの異常を指摘された方は、症状がなくても早めにご相談ください。
腹囲が基準を超えている(男性85cm以上、女性90cm以上)
 腹囲が基準を超えている状態は、内臓脂肪が多く蓄積していることを示します。自覚症状はありませんが、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病を発症しやすくなります。腹囲の増加はそれだけで病気が確定するわけではありませんが、他の検査項目(血圧・血糖・脂質など)に異常がある場合は「メタボリックシンドローム」と呼ばれ、心筋梗塞や脳卒中などの動脈硬化性疾患のリスクがさらに高くなります。生活習慣の改善(食事の見直し、適度な運動、禁煙、節酒、体重管理など)を始め、定期的に再測定して変化を確認しましょう。腹囲の減少は生活習慣病の予防や改善に直結します。健診で指摘された場合は、放置せず、できるだけ早めに生活改善などの行動を起こすことが大切です。
腹囲が基準を超えている状態は、内臓脂肪が多く蓄積していることを示します。自覚症状はありませんが、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病を発症しやすくなります。腹囲の増加はそれだけで病気が確定するわけではありませんが、他の検査項目(血圧・血糖・脂質など)に異常がある場合は「メタボリックシンドローム」と呼ばれ、心筋梗塞や脳卒中などの動脈硬化性疾患のリスクがさらに高くなります。生活習慣の改善(食事の見直し、適度な運動、禁煙、節酒、体重管理など)を始め、定期的に再測定して変化を確認しましょう。腹囲の減少は生活習慣病の予防や改善に直結します。健診で指摘された場合は、放置せず、できるだけ早めに生活改善などの行動を起こすことが大切です。