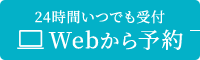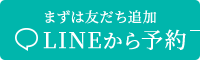南流山で消化器内科をお探しの方へ
消化器内科とは、食道、胃、腸、肝臓、胆のう、膵臓など、食べものの通り道や消化吸収に関わる臓器の病気を内科的に診断・治療する専門の診療科です。腹痛、下痢、便秘、吐き気、胸やけ、食欲不振、血便など、ありふれた症状の背後に重大な病気が潜んでいることもあるため、丁寧な評価と的確な初期対応が重要です。当院では、一般的な胃腸症状に対する内科的診療に加え、糖尿病や腎臓病といった慢性疾患に伴う消化器症状にも専門的に対応していることが大きな特徴です。たとえば、糖尿病による胃の動きの低下(糖尿病性胃不全麻痺)や、腎機能低下に伴う高カリウム血症治療薬による頑固な便秘、肥満・糖代謝異常に関連する脂肪肝など、これらは総合的な内科管理が求められる分野であり、当院の強みが最も活かされる領域です。症状の背景にある全身状態を見極め、必要に応じて血液検査や腹部エコーを実施し、さらに精密検査や専門治療が必要と判断される場合には、速やかに専門医療機関をご紹介いたします。些細な症状でも気になることがあれば、ぜひご相談ください。
消化器の関連した症状
ここでは、患者さんからよくご相談いただく代表的な症状と、それぞれに対する当院の診療の考え方をご紹介します。
胃の不快感(胃もたれ、胃痛、胸やけ、げっぷ、しゃっくり)
 胃の不快感は、日常的に多くの方が経験するありふれた症状のひとつですが、原因は人によってさまざまで、背景にある病態も多岐にわたります。比較的軽いものから、注意が必要な病気が隠れているケースまであり、症状の現れ方や持続期間、生活習慣、基礎疾患の有無などによって対応が異なります。本項では、当院でよくご相談いただく胃の不快感の代表的な原因や関連症状について、わかりやすくご紹介します。ご自身の症状に近い項目がありましたら、参考にしていただき、気になることがあればお気軽にご相談ください。
胃の不快感は、日常的に多くの方が経験するありふれた症状のひとつですが、原因は人によってさまざまで、背景にある病態も多岐にわたります。比較的軽いものから、注意が必要な病気が隠れているケースまであり、症状の現れ方や持続期間、生活習慣、基礎疾患の有無などによって対応が異なります。本項では、当院でよくご相談いただく胃の不快感の代表的な原因や関連症状について、わかりやすくご紹介します。ご自身の症状に近い項目がありましたら、参考にしていただき、気になることがあればお気軽にご相談ください。
生活習慣による胃の不快感
 脂っこい食事、早食い、過食、睡眠不足、ストレスなどは、胃酸の分泌や胃の動きを乱しやすく、食後の胃もたれやムカムカ、げっぷの原因となります。症状が一時的で、生活改善により自然に軽快するようであれば、こうした機能的な不調が関係している可能性があります。
脂っこい食事、早食い、過食、睡眠不足、ストレスなどは、胃酸の分泌や胃の動きを乱しやすく、食後の胃もたれやムカムカ、げっぷの原因となります。症状が一時的で、生活改善により自然に軽快するようであれば、こうした機能的な不調が関係している可能性があります。
ウイルス感染による胃の不快感
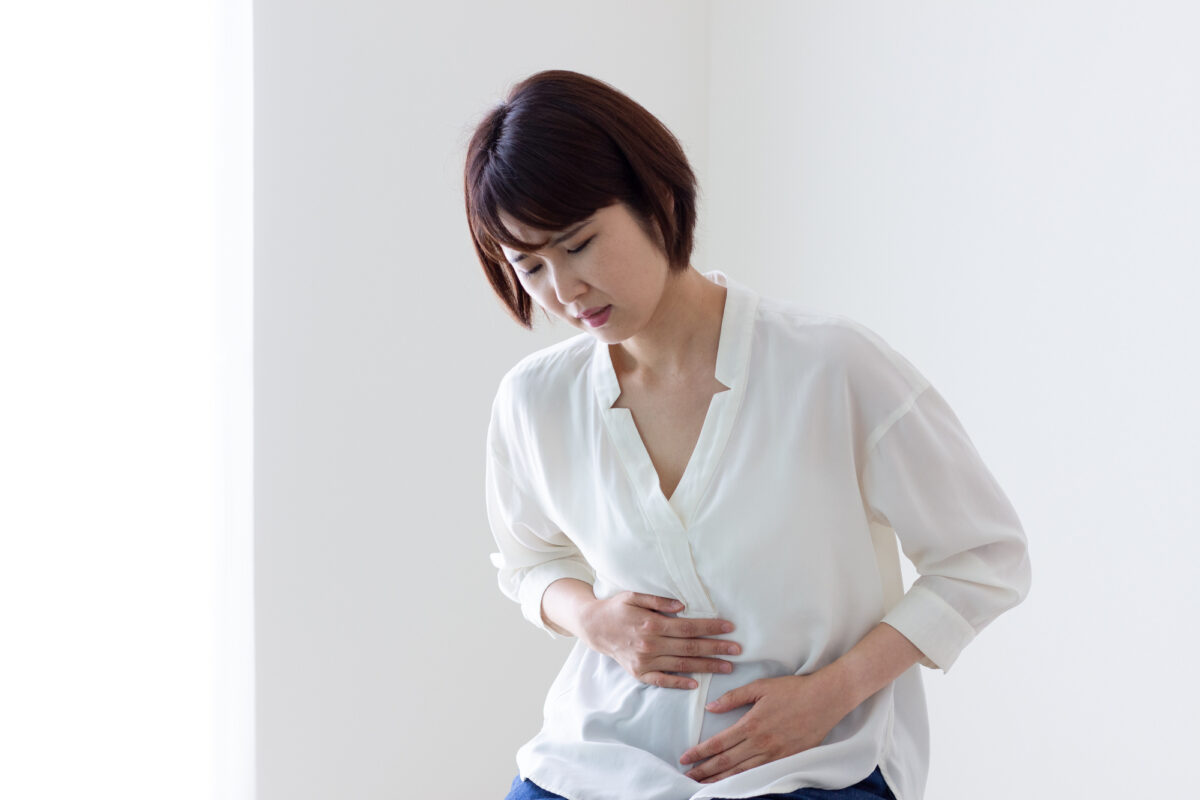 冬場を中心に流行するウイルス感染では、腸の炎症が原因となって胃の不快感が現れることがあります。ウイルスが小腸に感染すると、その刺激が脳に伝わり、みぞおちのムカムカや痛み、吐き気といった症状が出ることがあります。いわゆる「お腹の風邪」と呼ばれるもので、胃そのものに明らかな異常がなくても、みぞおちの不快感や吐き気を感じることがあります。
冬場を中心に流行するウイルス感染では、腸の炎症が原因となって胃の不快感が現れることがあります。ウイルスが小腸に感染すると、その刺激が脳に伝わり、みぞおちのムカムカや痛み、吐き気といった症状が出ることがあります。いわゆる「お腹の風邪」と呼ばれるもので、胃そのものに明らかな異常がなくても、みぞおちの不快感や吐き気を感じることがあります。
胃酸の逆流による胸やけ、げっぷ
 胃酸が食道へ逆流することで、胸やけや呑酸(酸っぱい液が上がる感じ)、げっぷが出やすくなることがあります。胃の入り口にある筋肉(下部食道括約筋)がゆるんでいたり、食後すぐに横になるなどの生活習慣が関係していることもあります。胸のあたりが焼けるように熱く感じる症状が続く場合には、胃酸の逆流が関係している可能性があります。一度ご相談ください。
胃酸が食道へ逆流することで、胸やけや呑酸(酸っぱい液が上がる感じ)、げっぷが出やすくなることがあります。胃の入り口にある筋肉(下部食道括約筋)がゆるんでいたり、食後すぐに横になるなどの生活習慣が関係していることもあります。胸のあたりが焼けるように熱く感じる症状が続く場合には、胃酸の逆流が関係している可能性があります。一度ご相談ください。
胃粘膜の炎症や傷つきによる痛み
胃の粘膜が炎症を起こしたり、深く傷ついたりすると、空腹時や食後にシクシクとした痛みや重苦しさを感じることがあります。市販薬で一時的に良くなることもありますが、繰り返す場合には一度ご相談ください。ピロリ菌や薬剤の影響など、背景にある要因を評価することが大切です。
糖尿病に伴う胃の運動障害
 糖尿病のある方では、自律神経の働きが低下することにより、胃の動きが鈍くなることがあります。これは、糖尿病の代表的な合併症である神経障害の一つとして現れる症状で、知らないうちに進行していることも少なくありません。少し食べただけで満腹になる、食後の膨満感が続く、吐き気が出る――といった症状が長く続く場合には、糖尿病による胃の運動障害が関係している可能性があります。
糖尿病のある方では、自律神経の働きが低下することにより、胃の動きが鈍くなることがあります。これは、糖尿病の代表的な合併症である神経障害の一つとして現れる症状で、知らないうちに進行していることも少なくありません。少し食べただけで満腹になる、食後の膨満感が続く、吐き気が出る――といった症状が長く続く場合には、糖尿病による胃の運動障害が関係している可能性があります。
げっぷやしゃっくりが気になる方へ
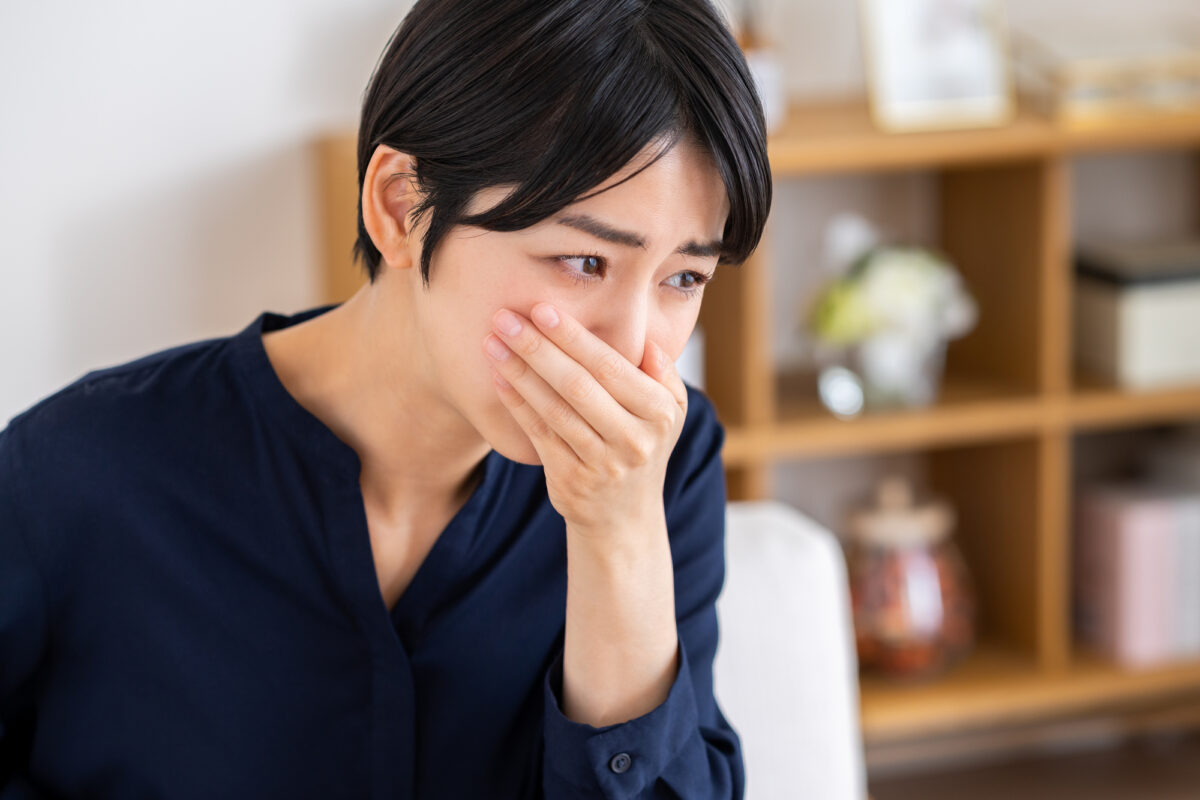 げっぷは、飲食とともに飲み込んだ空気が胃から戻る現象で、胃酸の逆流やストレス、空気を無意識に飲み込む癖(呑気症)などが関係していることもあります。また、しゃっくりは横隔膜の痙攣によって起こりますが、長く続く場合は胃や胸部の刺激、自律神経の乱れなどが背景にあることもあります。日常的に気になる場合はご相談ください。
げっぷは、飲食とともに飲み込んだ空気が胃から戻る現象で、胃酸の逆流やストレス、空気を無意識に飲み込む癖(呑気症)などが関係していることもあります。また、しゃっくりは横隔膜の痙攣によって起こりますが、長く続く場合は胃や胸部の刺激、自律神経の乱れなどが背景にあることもあります。日常的に気になる場合はご相談ください。
当院での対応
当院では、胃の不快感に対して、症状の経過や生活背景、基礎疾患の有無を丁寧に確認し、必要に応じて血液検査や腹部エコーを行います。内視鏡検査などが必要な場合には、信頼できる専門病院をご紹介いたします。検査で異常が見つからない場合でも、機能の不調や全身状態の変化に応じた対応を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
吐き気、嘔吐
 「ムカムカする」「吐きそう」「実際に吐いてしまった」といった吐き気、嘔吐は、消化器の不調を感じる際によく見られる症状のひとつです。原因は非常に多岐にわたり、胃腸のトラブルだけでなく、感染症や糖尿病、ストレス、薬の影響など、全身の状態とも深く関係しています。重篤な病気のサインとして現れることもあるため、症状の背景を丁寧に見極めることが大切です。本項では、当院でよくご相談いただく代表的な原因や、注意が必要な症状についてご紹介します。
「ムカムカする」「吐きそう」「実際に吐いてしまった」といった吐き気、嘔吐は、消化器の不調を感じる際によく見られる症状のひとつです。原因は非常に多岐にわたり、胃腸のトラブルだけでなく、感染症や糖尿病、ストレス、薬の影響など、全身の状態とも深く関係しています。重篤な病気のサインとして現れることもあるため、症状の背景を丁寧に見極めることが大切です。本項では、当院でよくご相談いただく代表的な原因や、注意が必要な症状についてご紹介します。
ウイルス性腸炎や食べすぎによる吐き気、嘔吐
吐き気、嘔吐の原因として最も多いのが、ウイルスや細菌による腸炎(いわゆる「お腹の風邪」)や、暴飲暴食・脂っこい食事の後に胃腸の働きが乱れるケースです。腸に炎症が起こると、神経を通じて脳が刺激され、みぞおちのムカムカや吐き気として感じられます。こうした吐き気は数日で自然に落ち着くことが多いですが、食事が進まない、軽く水を飲んでも気持ち悪い、吐き気が何日も続く――そんなときは、我慢せずご相談ください。
胃の病気が原因の吐き気、嘔吐
胃炎、胃潰瘍では胃の粘膜が不安定になり、食後や空腹時に吐き気が出ることがあります。特に、食後に胸やけ、ムカムカ、げっぷを伴う場合は、胃酸の逆流が関係している可能性があります。これらは繰り返し起こりやすいため、症状が続くときは一度医療機関での評価をおすすめします。
糖尿病に関連した吐き気
糖尿病をお持ちの方で、少しの食事でお腹がいっぱいになったり、食後に吐き気が長く続くような場合には、糖尿病性胃不全麻痺という状態が関係していることがあります。これは糖尿病の合併症である自律神経障害の一つで、胃の動きが鈍くなってしまうことで起こります。胃カメラで異常が見つからなくても、こうした神経の影響によって症状が出ることがあります。
ストレス、薬、その他の原因による吐き気
吐き気は、精神的な緊張やストレス、乗り物酔い、片頭痛、妊娠初期などでも起こります。また、鎮痛薬は、胃の粘膜を荒らし、炎症や潰瘍を引き起こすことがあるため、服用後に吐き気や胃の不快感が出ることがあります。これらの症状が繰り返される場合は、薬の見直しや胃の状態の確認が必要です。
注意が必要な吐き気、嘔吐
吐き気や嘔吐の多くは一時的な胃腸の不調によるものですが、なかには重大な病気のサインとして現れていることもあります。とくに、黒色便(タール便)や吐血、みぞおちの強い痛みを伴う場合には、胃潰瘍や胃がんなど、上部消化管からの出血を伴う病気が疑われます。これらは早急な診断と治療が必要なこともあり、放置すると貧血や出血性ショックを起こすことがあります。また、吐き気が数日以上続いて食事や水分がとれない、脱水症状が疑われる、意識がぼんやりするといった場合も、体力の消耗が進み、点滴治療や入院が必要になることがあります。このような症状がある場合は、まずは当院までご相談ください。必要に応じて、連携している専門医療機関へ速やかにご紹介いたします。
当院での対応
当院では、吐き気、嘔吐の原因を丁寧に見極めるため、症状のタイミング、持続時間、食事との関係、服薬歴、基礎疾患などを詳細にうかがいます。必要に応じて、血液検査や腹部エコーを行い、背景にある病態を総合的に評価します。症状が一時的なものであっても、繰り返したり、他の症状を伴ったりする場合は、お早めにご相談ください。
腹痛
 お腹の痛みは、日常的によく見られる症状のひとつですが、原因は人によってさまざまです。多くは軽い胃腸の不調によるものですが、なかには早期の対応が必要な病気が隠れていることもあります。ここでは、当院でよくご相談いただく腹痛の代表的な原因や、特に注意が必要なケースについてご紹介します。
お腹の痛みは、日常的によく見られる症状のひとつですが、原因は人によってさまざまです。多くは軽い胃腸の不調によるものですが、なかには早期の対応が必要な病気が隠れていることもあります。ここでは、当院でよくご相談いただく腹痛の代表的な原因や、特に注意が必要なケースについてご紹介します。
よくある腹痛
腹痛の原因として最も多いのは、ウイルス性腸炎です。下痢や吐き気、微熱を伴う「お腹の風邪」は、特に冬場によくみられます。数日で自然に回復することが多いですが、水分がとれないときは脱水に注意が必要です。また、脂っこい食事や暴飲暴食、ストレスによって胃腸の働きが乱れ、一時的な腹痛が起きることもあります。こうした場合は、生活習慣の見直しや整腸剤などで改善することが多く、経過を見ながら対応します。
注意が必要な腹痛
腹痛の中には、重大な病気によって引き起こされるものもあります。たとえば、胃潰瘍や膵炎、胆石、虫垂炎(盲腸)、腸閉塞などでは、強い痛みや発熱、吐き気、血便、便が出ないといった症状を伴うことがあります。また、腹痛が急に強くなった、長時間続いている、いつもと違う場所が痛むといった場合も注意が必要です。さらに、糖尿病のある方では、「糖尿病性ケトアシドーシス」という内科的な緊急疾患でも腹痛が現れることがあります。これはインスリン不足により血糖が著しく上昇し、血液が酸性に傾くことで、脱水、吐き気、腹痛、意識障害などを伴う状態です。外科的な急性腹症と区別がつきにくいこともあり、血糖値や尿中ケトンの確認が診断の鍵となります。当院では、腹痛の原因を丁寧に見極めるため、症状の内容や経過に応じて必要な検査を行い、必要に応じて専門医療機関と連携して対応いたします。気になる症状がある場合は、お早めにご相談ください。
お腹の張り
 「お腹が張る」「ガスがたまって苦しい」「お腹がゴロゴロして不快」などの症状は、日常的によく見られますが、原因はさまざまです。食事や生活習慣によって一時的に起こることもあれば、腸の病気や消化管の機能の乱れが背景にあることもあります。特に多いのは、腸の動きが乱れたり、ストレスがかかったりすることで腸にガスや内容物がたまり、膨満感を感じるケースです。たとえば、便秘が続くと腸の中に便やガスが長くとどまり、お腹の張りや不快感が強くなることがあります。過敏性腸症候群のように、腸が過敏になっている場合には、実際にはあまり膨らんでいなくても張っているように感じることもあります。一方で、お腹の張りに加えて激しい腹痛や吐き気、便やガスがまったく出ないといった症状がある場合には、「腸閉塞」などの重篤な病気が隠れている可能性もあり、早急な対応が必要です。お腹の張りは「軽い不調」として放置されやすい症状ですが、生活の質に大きく影響することもあります。当院では、症状の経過や便通、食事内容、ストレス状況などを丁寧にうかがい、必要に応じて検査や治療をご提案いたします。気になる症状が続く場合は、お早めにご相談ください。
「お腹が張る」「ガスがたまって苦しい」「お腹がゴロゴロして不快」などの症状は、日常的によく見られますが、原因はさまざまです。食事や生活習慣によって一時的に起こることもあれば、腸の病気や消化管の機能の乱れが背景にあることもあります。特に多いのは、腸の動きが乱れたり、ストレスがかかったりすることで腸にガスや内容物がたまり、膨満感を感じるケースです。たとえば、便秘が続くと腸の中に便やガスが長くとどまり、お腹の張りや不快感が強くなることがあります。過敏性腸症候群のように、腸が過敏になっている場合には、実際にはあまり膨らんでいなくても張っているように感じることもあります。一方で、お腹の張りに加えて激しい腹痛や吐き気、便やガスがまったく出ないといった症状がある場合には、「腸閉塞」などの重篤な病気が隠れている可能性もあり、早急な対応が必要です。お腹の張りは「軽い不調」として放置されやすい症状ですが、生活の質に大きく影響することもあります。当院では、症状の経過や便通、食事内容、ストレス状況などを丁寧にうかがい、必要に応じて検査や治療をご提案いたします。気になる症状が続く場合は、お早めにご相談ください。
便秘
 一般的には「週に3回未満の排便」や「いきんでも出にくい」「便が硬い」「すっきり出ない」といった症状がある場合、便秘と考えられます。排便の頻度だけでなく、「出にくさ」や「残便感」といった感覚的な症状も大切なサインです。
一般的には「週に3回未満の排便」や「いきんでも出にくい」「便が硬い」「すっきり出ない」といった症状がある場合、便秘と考えられます。排便の頻度だけでなく、「出にくさ」や「残便感」といった感覚的な症状も大切なサインです。
よくある原因
便秘の多くは、水分や食物繊維の不足、運動不足、朝のトイレ習慣が乱れていることなど、生活習慣の乱れが関係しています。また、女性ホルモン(特に黄体ホルモン)は腸の動きを抑える作用があるため、女性では月経周期や妊娠中に便秘が悪化しやすいことも知られています。加齢に伴う腸の運動低下も影響します。
薬による便秘
さまざまな薬が便秘の原因になります。たとえば、鉄剤、カルシウム製剤、抗コリン薬、鎮痛薬、抗うつ薬などが代表的です。また、慢性腎臓病の方に用いられる高カリウム血症治療薬も便秘を引き起こしやすいため、注意が必要です。薬を継続しながらも便秘をコントロールできるよう、慎重に評価、調整します。
病気が原因の便秘
糖尿病や甲状腺機能低下症、パーキンソン病などの病気では、腸の動きが全体的に低下し、便秘が慢性的に続くことがあります。また、急に便秘になった、血便が出る、体重が減るといった症状がある場合は、大腸がんなどの重い病気が隠れている可能性もあり、早めの評価が必要です。
治療の考え方と当院の方針
当院ではまず、食事や水分、排便習慣の見直しを基本とし、必要に応じて薬を使った治療を行います。薬については、近年のガイドラインでは腸の動きを活発にさせる刺激性下剤は原則として常用を避けるべきとされています。また、腎機能が低下している場合は薬の選択に制限が出てきます。当院では、一人ひとりの症状や体質に合わせて、安全で無理のない治療を一緒に考えていきますので、お気軽にご相談ください。
下痢
 「お腹がゆるい」「すぐにトイレに行きたくなる」「水のような便が続いている」など、下痢は日常でもよくみられる症状です。多くは一過性のもので自然に治まりますが、原因によっては注意が必要なケースもあります。ここでは、よくある下痢の原因や、受診が必要なサインについてご紹介します。
「お腹がゆるい」「すぐにトイレに行きたくなる」「水のような便が続いている」など、下痢は日常でもよくみられる症状です。多くは一過性のもので自然に治まりますが、原因によっては注意が必要なケースもあります。ここでは、よくある下痢の原因や、受診が必要なサインについてご紹介します。
急性の下痢
突然始まった下痢の多くは、ウイルスや細菌による感染症(いわゆる「お腹の風邪」)や、食あたり、冷たいもの、脂っこい食事の影響などが原因です。発熱や吐き気、腹痛を伴うこともありますが、数日で自然に回復することが多く、まずはこまめな水分補給と安静が基本です。市販薬で抑えず、悪化するようなら早めにご相談ください。
慢性的な下痢
下痢が4週間以上続く場合は、「慢性下痢症」として扱います。腸の炎症やホルモン異常、薬の影響、腸の動きの異常(過敏性腸症候群)など、さまざまな要因が考えられます。とくに血便、体重減少、夜間の下痢、発熱などがある場合は、炎症性腸疾患や腫瘍性病変などの重い病気が隠れていることもあるため注意が必要です。
薬や全身性疾患に伴う下痢
下痢の原因には、薬の副作用や消化管以外の病気(全身性疾患)が関係していることもあります。たとえば、抗菌薬、糖尿病薬(GLP-1受容体作動薬など)、マグネシウム製剤、抗がん剤などが原因となることがあります。また、甲状腺機能亢進症や糖尿病による自律神経障害などでも、腸の動きが過剰になり、慢性的な下痢が起こることがあります。こうした場合には、便以外の症状(体重減少、動悸、しびれなど)にも目を向けながら、背景の病気を含めた評価が必要です。
当院での対応
当院では、下痢の原因を見極めるために、症状の経過、便の性状、発熱や体重変化の有無、服薬状況、持病の有無などを丁寧にお聞きします。必要に応じて、血液検査や腹部エコーを行い、重い病気の可能性がある場合は、専門医療機関へ迅速にご紹介いたします。一方で、機能性の下痢であれば、生活習慣の見直しや整腸剤の使用によって多くの方が改善を期待できます。
食欲不振、体重減少
 「最近食欲がわかない」「自然と体重が減ってきた」などの症状は、日常でもよく見られます。多くの場合は一時的な体調不良や生活習慣の乱れが原因ですが、ときに重大な病気のサインであることもあり、経過を見ながら適切な判断が必要です。ここでは、当院でよくご相談いただく原因や、特に注意すべきケースについてご紹介します。
「最近食欲がわかない」「自然と体重が減ってきた」などの症状は、日常でもよく見られます。多くの場合は一時的な体調不良や生活習慣の乱れが原因ですが、ときに重大な病気のサインであることもあり、経過を見ながら適切な判断が必要です。ここでは、当院でよくご相談いただく原因や、特に注意すべきケースについてご紹介します。
よくある原因と体調による変動
食欲不振や軽い体重減少は、疲労、ストレス、睡眠不足、気温の変化、消化不良などの一過性の体調変化によってよく起こります。特に胃腸の動きが落ちているときや、便秘が続いているときなどには、食べたくない、食べられない感覚が続くこともあります。また、感染症の回復期や風邪の初期症状、薬の副作用でも、一時的に食欲が落ちることがあります。このようなケースでは、数日~1週間程度で自然に回復することがほとんどです。
注意が必要なサインと背景疾患
一方で、明らかな原因がないのに食欲が落ち続けている、体重が1か月で2〜3kg以上減っている、疲れやすい、微熱が続く、お腹が張る、下痢が続くといった場合は、内科的な病気が背景にある可能性があります。たとえば、以下のような疾患が関係していることがあります。
- 消化器の病気(胃潰瘍、胃がん、大腸がん、慢性膵炎など)
- 内分泌疾患(甲状腺機能亢進症、糖尿病など)
- 腎機能の低下や肝機能障害
- うつ病や不安障害などの精神的ストレス
- 高齢者に多いフレイル(体力の衰え)やサルコペニア
当院では、これらの症状が気になる方に対して、丁寧な問診と診察に加え、必要に応じて血液検査や腹部エコー、便検査などを行い、背景にある疾患がないかを確認します。必要に応じて専門医療機関と連携し、適切な対応につなげてまいります。
黒色便・血便
 便の色に変化があると、多くの方が強い不安を感じます。なかでも「真っ黒な便(黒色便)」や「赤い血が混じる便(血便)」は、消化管のどこかで出血が起きているサインであり、原因によっては早めの評価が必要です。黒色便(タール便)は、胃や十二指腸などの“口に近い消化管の出血”によって現れることがあります。出血した血液が胃酸により酸化されて、黒くねっとりとした便になります。主な原因には、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんなどです。一方、血便は便に赤い血が混じる症状で、大腸や肛門など“肛門に近い消化管”からの出血であることが多く、鮮やかな赤い血が便の表面についたり、トイレットペーパーに血がつくといった形で現れます。痔などが原因であることも多いですが、大腸ポリープ、大腸がん、虚血性腸炎、潰瘍性大腸炎などの病気でも血便が起こることがあります。血便が繰り返す、体重が減る、貧血や腹痛を伴うといった場合には、下部消化管内視鏡検査が必要です。当院では、問診や視診に加え、血液検査、便潜血検査、腹部エコーなどを用いて、出血の程度や可能性のある原因を評価します。内視鏡検査が必要と判断される場合には、信頼できる消化器専門医療機関へご紹介いたします。便に血が混じる症状がある場合は、たとえ軽度であっても自己判断せず、一度ご相談ください。
便の色に変化があると、多くの方が強い不安を感じます。なかでも「真っ黒な便(黒色便)」や「赤い血が混じる便(血便)」は、消化管のどこかで出血が起きているサインであり、原因によっては早めの評価が必要です。黒色便(タール便)は、胃や十二指腸などの“口に近い消化管の出血”によって現れることがあります。出血した血液が胃酸により酸化されて、黒くねっとりとした便になります。主な原因には、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんなどです。一方、血便は便に赤い血が混じる症状で、大腸や肛門など“肛門に近い消化管”からの出血であることが多く、鮮やかな赤い血が便の表面についたり、トイレットペーパーに血がつくといった形で現れます。痔などが原因であることも多いですが、大腸ポリープ、大腸がん、虚血性腸炎、潰瘍性大腸炎などの病気でも血便が起こることがあります。血便が繰り返す、体重が減る、貧血や腹痛を伴うといった場合には、下部消化管内視鏡検査が必要です。当院では、問診や視診に加え、血液検査、便潜血検査、腹部エコーなどを用いて、出血の程度や可能性のある原因を評価します。内視鏡検査が必要と判断される場合には、信頼できる消化器専門医療機関へご紹介いたします。便に血が混じる症状がある場合は、たとえ軽度であっても自己判断せず、一度ご相談ください。
代表的な消化器疾患
当院では、消化器に関わる日常的な不調から、生活習慣に関連した病気、慢性疾患まで、幅広く診療を行っています。ここでは、当院でよくご相談いただく代表的な消化器疾患について、それぞれの特徴や診療の考え方をご紹介します。
ウイルス性腸炎
 ウイルス性腸炎とは、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスが小腸の粘膜に感染して起こる急性の腸の炎症です。主な症状は、水のような下痢、吐き気や嘔吐、軽い発熱、みぞおち~下腹部の痛みなどです。感染から1~2日で症状が現れ、多くは2~3日で自然に回復します。特に冬場に流行しやすく、家庭や学校、施設内で集団発生することもあります。
ウイルス性腸炎とは、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスが小腸の粘膜に感染して起こる急性の腸の炎症です。主な症状は、水のような下痢、吐き気や嘔吐、軽い発熱、みぞおち~下腹部の痛みなどです。感染から1~2日で症状が現れ、多くは2~3日で自然に回復します。特に冬場に流行しやすく、家庭や学校、施設内で集団発生することもあります。
感染のきっかけと予防
感染経路は、ウイルスのついた手で飲食物を扱うこと(経口感染)が中心です。とくに生のカキや調理が不十分な貝類を食べたあとに発症するケースが知られています。また、感染者の嘔吐物や便に含まれるウイルスが周囲に広がり、家庭内や施設内でうつることもあります。予防には、石けんを使った丁寧な手洗いがもっとも重要です。アルコール消毒だけでは不十分なため、調理前やトイレ後には必ず流水と石けんで手を洗いましょう。
治療と注意点
ウイルス性腸炎には特効薬がないため、治療の基本は水分補給と安静です。経口補水液やスポーツドリンクを少量ずつ、こまめに摂取してください。食欲が戻るまでは無理に食べず、消化の良いものから少しずつ再開します。必要に応じて、吐き気止めや整腸剤、解熱鎮痛薬などで症状をやわらげることもあります。下痢止めは原則使いません。水分がとれない、吐き気が強い、脱水が疑われる場合は点滴による治療を行うこともあります。
再発と感染予防の注意点
症状が治まっても、ウイルスは1週間ほど便から排出され続けることがあります。そのため、症状が回復したあとも手洗いや食品の取り扱いに十分注意することが大切です。特に家庭内や学校、職場で感染が広がらないよう、回復後も2日程度は登園や出勤を控えるのが望ましいとされています。気になる症状があれば、軽い症状であってもお気軽にご相談ください。
胃食道逆流症
 胃食道逆流症は、胃の中の胃酸や食べ物が、食道へ逆流してしまうことで起こる病気です。代表的な症状は、胸やけ(胸が焼けるような感じ)や、酸っぱい液体がこみ上げてくる感じ(呑酸)などです。内視鏡で炎症(びらん)が見つかる人もいれば、検査では異常がないのに症状だけが続く人もいます。命に関わる病気ではありませんが、日常生活の質(QOL)を下げてしまうことが多く、早めの対応が大切です。
胃食道逆流症は、胃の中の胃酸や食べ物が、食道へ逆流してしまうことで起こる病気です。代表的な症状は、胸やけ(胸が焼けるような感じ)や、酸っぱい液体がこみ上げてくる感じ(呑酸)などです。内視鏡で炎症(びらん)が見つかる人もいれば、検査では異常がないのに症状だけが続く人もいます。命に関わる病気ではありませんが、日常生活の質(QOL)を下げてしまうことが多く、早めの対応が大切です。
原因とよくある症状
食道と胃の境目には、胃の内容物が逆流しないようにする筋肉の“ふた”(下部食道括約筋)があります。この働きが弱まったり、一時的にゆるんだりすることで、胃酸などが逆流して症状が出ます。原因には、肥満、加齢、姿勢(前かがみ)、ストレス、食べすぎ、甘いものや脂っこい食事、アルコール、カフェイン、寝る直前の食事などがあります。
よく見られる症状は以下のとおりです。
- 胸やけ(胸が焼けるような感じ)
- 呑酸(酸っぱい液が上がる感じ)
- 喉の違和感、咳、声がれ
- 胃の不快感、お腹の張り
特に食後や夜間、横になったときに悪化しやすいのが特徴です。
治療の基本と生活の工夫
胃食道逆流症は、生活習慣の見直しと薬の治療で、多くの方がコントロール可能です。
生活改善のポイント
- 寝る2〜3時間前の食事は避ける
- 食べすぎ、脂っこいもの、甘いものを控える
- アルコール、カフェインをとりすぎない
- 前かがみやベルトなど、お腹を圧迫する姿勢、服装を避ける
- 枕を少し高くして寝る(上半身を少し起こす)
- 適度な運動やストレス解消も有効です
薬による治療
主に胃酸を抑える薬や、胃の動きを助ける薬を使用します。通常は1〜2週間で症状が改善することが多く、良くなれば薬を減らしていくことも可能です。漢方薬を併用することもあります。
当院での対応と検査の考え方
当院では、問診を丁寧に行い、生活習慣や症状の出方を細かく把握した上で、生活指導と薬の提案を行います。ただし、以下のような場合には胃カメラ(内視鏡)検査が必要になることがあります。
- 初めて強い胸やけが出た高齢の方
- 体重が減ってきた
- 吐血や黒色便がある
- 食べ物の飲み込みにくさがある
内視鏡検査が必要な場合には、連携している専門医療機関へご紹介いたします。胃食道逆流症は一時的によくなっても再発することがあるため、生活改善を続けながら無理のない治療を継続していくことが大切です。
ピロリ菌感染症
 ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の中にすみつく細菌で、胃の粘膜に炎症を起こす原因になります。日本では、中高年層を中心に多くの人が感染していることが知られていますが、自覚症状がないまま長年感染しているケースも少なくありません。ピロリ菌に感染すると、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、胃MALTリンパ腫などのリスクが高まることがわかっています。そのため、感染が確認された場合には内服薬による除菌治療が推奨されています。
ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の中にすみつく細菌で、胃の粘膜に炎症を起こす原因になります。日本では、中高年層を中心に多くの人が感染していることが知られていますが、自覚症状がないまま長年感染しているケースも少なくありません。ピロリ菌に感染すると、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、胃MALTリンパ腫などのリスクが高まることがわかっています。そのため、感染が確認された場合には内服薬による除菌治療が推奨されています。
感染の原因と症状の特徴
ピロリ菌は、主に子どもの頃に家族内の接触(食器の共有など)を通じて口から感染すると考えられています。感染後すぐに症状が出るわけではなく、何年もかけて胃の粘膜に慢性的な炎症が進行していきます。多くの方は無症状ですが、以下のような胃の不快感が続く場合、ピロリ菌感染が関係している可能性があります。
- みぞおちの痛みや重さ
- 胃もたれ、げっぷ
- 食欲低下
- 胸やけ、吐き気
これらの症状がある場合は、ピロリ菌検査を受けることで、治療につながることがあります。
検査と治療の流れ
当院では、便の中に含まれるピロリ菌の抗原を調べる「便中抗原検査」を実施しています。これは内視鏡を使わずにできる、安全で苦痛の少ない検査です。症状や年齢、過去の病歴などをふまえて医師が実施を判断します。感染が確認された場合は、内服薬による「除菌治療」を行います。
治療の基本的な流れ
検査で感染を確認
※1回または2回の治療で、ほとんどの方が除菌に成功します。
除菌後の注意と当院での対応
除菌によって、胃潰瘍の再発や将来の胃がんのリスクを下げることができます。ただし、すでに胃の粘膜が傷んでいる場合は、除菌後も経過観察が必要になることがあります。当院では、内視鏡検査は行っていませんが、必要に応じて連携する専門医療機関へご紹介いたします。「胃の調子が気になる」「過去に胃潰瘍があった」「ピロリ菌が心配」という方は、お気軽にご相談ください。
機能性ディスペプシア
 機能性ディスペプシアは、検査で異常が見つからないのに、胃の不快な症状がくり返し続く病気です。代表的な症状には、食後の胃もたれ、少量で満腹になる感じ、みぞおちの痛みや焼けるような感じなどがあります。これらの症状が6か月以上前から始まり、最近3か月のあいだにくり返し続いている場合に診断されます。命に関わる病気ではありませんが、仕事や生活の質に大きく影響することがあり、適切な対応が重要です。
機能性ディスペプシアは、検査で異常が見つからないのに、胃の不快な症状がくり返し続く病気です。代表的な症状には、食後の胃もたれ、少量で満腹になる感じ、みぞおちの痛みや焼けるような感じなどがあります。これらの症状が6か月以上前から始まり、最近3か月のあいだにくり返し続いている場合に診断されます。命に関わる病気ではありませんが、仕事や生活の質に大きく影響することがあり、適切な対応が重要です。
原因と症状の特徴
原因はひとつではなく、以下のようなさまざまな要因が重なって起こると考えられています。
- 胃の動きの低下(内容物の停滞)
- 胃の過敏性(少しの刺激で不快感を感じやすい)
- ストレスや自律神経の乱れ
- ピロリ菌感染
- 食べすぎ、早食い、脂っこい食事などの生活習慣
症状は日によって変動しやすく、体調や気分、食事内容に左右されやすいのが特徴です。長く続くこともありますが、命にかかわる病気ではありません。
診断と治療の進め方
機能性ディスペプシアは、問診と症状の経過から診断する病気です。当院では、体重減少や出血などの「重大な病気のサイン」がないかを確認し、必要に応じて血液検査やピロリ菌検査(便や尿)を実施します。
※内視鏡検査が必要な場合(高齢者や初発の強い症状など)は、連携する専門医療機関をご紹介いたします。
生活習慣の見直し
- 脂っこいもの、甘いもの、刺激物を控える
- よく噛んで食べる、食事の時間を整える
- 睡眠、運動、ストレス対策も重要です
薬の治療
症状に合わせて、以下のような薬を使うことがあります。
- 胃酸を抑える薬(みぞおちの痛み、胸やけに)
- 胃の動きを助ける薬(胃もたれや張りに)
- 漢方薬(体質や症状に応じて)
必要に応じて、ストレスや自律神経に働きかける薬を使用することもあります
当院での対応と経過の見通し
薬と生活改善の両面からアプローチすることで、多くの方が症状をコントロール可能です。ただし、ストレスや食べすぎ、疲労などで再発することもあるため、焦らず、うまく付き合っていくことが大切です。当院では、患者さん一人ひとりの症状のパターンや生活背景に応じて、無理のない治療と生活のアドバイスをご提案します。「胃の検査では異常がなかったのに、つらい症状が続く」といった場合も、安心してご相談ください。
過敏性腸症候群
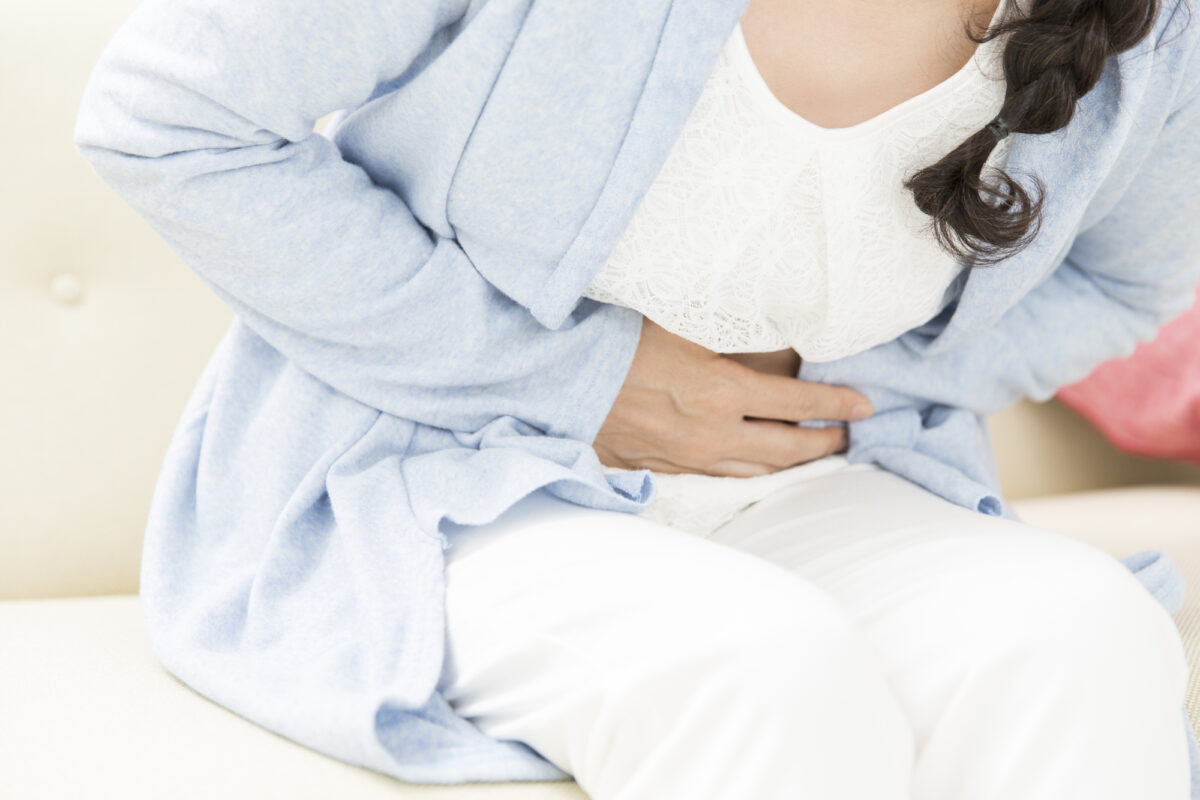 過敏性腸症候群とは、検査では異常が見つからないにもかかわらず、お腹の不調や便通異常がくり返し続く病気です。便秘、下痢、腹痛、お腹の張りなどが慢性的に続き、排便とともに痛みがやわらぐのが特徴です。症状が6か月以上前からあり、直近3か月間に週1回以上お腹の痛みがある場合に診断されます。命に関わる病気ではありませんが、仕事、学校、日常生活に大きな影響を与えることがあるため、適切なケアが大切です。
過敏性腸症候群とは、検査では異常が見つからないにもかかわらず、お腹の不調や便通異常がくり返し続く病気です。便秘、下痢、腹痛、お腹の張りなどが慢性的に続き、排便とともに痛みがやわらぐのが特徴です。症状が6か月以上前からあり、直近3か月間に週1回以上お腹の痛みがある場合に診断されます。命に関わる病気ではありませんが、仕事、学校、日常生活に大きな影響を与えることがあるため、適切なケアが大切です。
原因と症状の特徴
原因はひとつではなく、以下のようなさまざまな要因が重なって起こると考えられています。
- 腸の動きの異常(速すぎる/遅すぎる)
- 腸が敏感になり、ガスや便に反応しやすくなる
- ストレスや自律神経の乱れ
- 腸内細菌バランスの変化
- 腸炎をきっかけに発症
よくある症状
- お腹の痛みや不快感
- 排便後に痛みが和らぐ
- 下痢、便秘、またはその交互
- 便の形が日によって変わる(硬い/ゆるい)
- お腹の張り、ガスがたまりやすい
これらの症状は、ストレス、食事、疲れなどの影響を受けやすく、日によって変動するのが特徴です。
診断と治療の進め方
過敏性腸症候群は、問診を中心に、症状の経過や排便との関係をもとに診断します。当院では、体重減少や血便など重大な病気がないかを確認した上で、必要に応じて血液検査やピロリ菌検査、便検査を行います。
※内視鏡などの詳しい検査が必要な場合には、信頼できる専門医療機関をご紹介します。
治療の基本
- 脂っこいもの、刺激物、甘いものを控える
- 小麦、豆類、玉ねぎなどガスを生じやすい食材を減らす食事法が有効なこともあります
- 睡眠、運動、ストレス対策も大切です
薬による治療
- 腸の動きを整える薬(便秘型、下痢型で使い分け)
- 整腸剤
- 漢方薬(体質に応じて処方)
必要に応じて、気分の落ち込みやストレスに働きかける薬を短期間のみ使用することもあります。
当院での対応と生活のサポート
過敏性腸症候群は慢性化しやすい一方で、命に関わる病気ではありません。当院では、症状の型や生活スタイルに応じた対応を心がけています。「ストレスが原因」と言われて戸惑っている方も少なくありませんが、IBSは気のせいではなく、医学的に認められた病気です。長く続くお腹の不快感にお悩みの方は、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
慢性便秘症
 慢性便秘症とは、3か月以上にわたって便通の異常が続く状態を指します。排便回数が少ない(週3回未満)、便が硬い、強くいきまないと出ない、出てもすっきりしない、といった症状がみられます。原因によって、便秘は次の3つに分類されます。
慢性便秘症とは、3か月以上にわたって便通の異常が続く状態を指します。排便回数が少ない(週3回未満)、便が硬い、強くいきまないと出ない、出てもすっきりしない、といった症状がみられます。原因によって、便秘は次の3つに分類されます。
| 器質性便秘 | 大腸がん、腸の狭窄、癒着など、腸の構造異常が原因 |
|---|---|
| 二次性便秘 | 糖尿病、甲状腺機能低下症、パーキンソン病などの病気や、薬の副作用によるもの |
| 機能性便秘 | 検査で異常が見つからないが、腸の動きや知覚の乱れで起こる便秘(最も多い) |
原因と症状の特徴
慢性便秘症の原因は人によってさまざまですが、以下のような要因が重なっておこることが多いです。
- 食物繊維や水分の不足
- 運動不足や排便習慣の欠如
- 加齢による腸の動きの低下
- ストレスや自律神経の乱れ
- 糖尿病、甲状腺機能低下症、パーキンソン病などの内科疾患
- 鉄剤、抗コリン薬、抗うつ薬、慢性腎臓病で使用される高カリウム血症治療薬などの薬剤
よくみられる症状
- 排便回数が少ない
- 便が硬い、いきんでも出にくい
- 残便感がある(すっきりしない)
- お腹の張り、軽い腹痛や吐き気
便秘が急に始まったり、血便や体重減少を伴う場合は、大腸がんなどの重大な疾患が隠れている可能性もあるため、早めの評価が必要です。
診断と治療の流れ
当院では、まず丁寧な問診と症状の経過を確認し、必要に応じて血液検査、便潜血検査、腹部X線などを行います。体重減少や血便、便秘の急な悪化などがある場合には、専門医療機関へご紹介します。
治療の基本方針
まずは、食事内容や水分摂取、排便習慣、運動などの生活習慣を見直すことが基本となります。それでも十分な改善がみられない場合には、便の性状や排便頻度に応じて、浸透圧性下剤や上皮機能変容薬、腸の動きを整える薬、漢方薬などを使い分けて治療を進めていきます。基本的に大腸を刺激する下剤は常用を避け、必要なときに限定的に使用します。また、腎機能が低下している方では、使用する薬剤を慎重に選択します。
慢性下痢症
 慢性下痢症とは、水のような便や軟便が4週間以上にわたって続く状態を指します。排便回数が1日3回以上になることも多く、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。一時的な下痢とは異なり、背景に体質の問題だけでなく、腸の病気やホルモン異常、薬の影響が関係している場合もあるため、適切な評価が大切です。
慢性下痢症とは、水のような便や軟便が4週間以上にわたって続く状態を指します。排便回数が1日3回以上になることも多く、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。一時的な下痢とは異なり、背景に体質の問題だけでなく、腸の病気やホルモン異常、薬の影響が関係している場合もあるため、適切な評価が大切です。
原因と症状の特徴
慢性下痢症の原因は人によってさまざまですが、以下のような要因が重なっておこることが多いです。
- 乳糖不耐症や人工甘味料などによる浸透圧性の下痢
- 過敏性腸症候群のような腸の過剰な運動
- 糖尿病や甲状腺疾患、薬剤(抗生物質、制酸薬など)による影響
- 潰瘍性大腸炎、クローン病などの腸の炎症
よくみられる症状
- 軟便や水様便が1日3回以上
- 急な便意、我慢できない感覚
- 食後すぐに便意を感じる
- 夜中に下痢で目が覚める
血便、発熱、体重減少がある場合は要注意です。
診断と治療の進め方
当院では、まず症状の経過や便の性状、頻度、全身症状の有無について丁寧にお伺いします。そのうえで、必要に応じて血液検査や便検査を行い、腸の炎症や内科的疾患の可能性を評価します。重い病気が疑われる場合には、大腸内視鏡検査やCTなどを専門医療機関に依頼します。
治療の進め方
原因が明らかであれば、その治療が基本となります。一方、はっきりした異常が見つからない「機能性下痢」の場合は、以下を組み合わせて対応します。
- 食生活の見直し(脂っこいもの、冷たい飲料、刺激物の制限)
- 整腸剤や漢方薬の使用(腸内環境や体質の調整)
- 症状に応じて止瀉薬や過敏性腸症候群の治療薬の使用
脂肪肝
 脂肪肝とは、肝臓に脂肪が過剰にたまっている状態を指します。健康な人でも肝臓には少量の脂肪がありますが、それが増えすぎると肝臓に炎症が起き、進行すると肝硬変や肝がんへとつながるリスクもあります。以前は「NAFLD(非アルコール性脂肪肝疾患)」という名称が使われていましたが、最近では「MASLD(代謝異常関連脂肪性肝疾患)」や「MAFLD(代謝異常関連脂肪肝疾患)」という表現が主流になりつつあります。これは、病気の本質がアルコールではなく代謝の異常にあることをより明確に伝えるためです。
脂肪肝とは、肝臓に脂肪が過剰にたまっている状態を指します。健康な人でも肝臓には少量の脂肪がありますが、それが増えすぎると肝臓に炎症が起き、進行すると肝硬変や肝がんへとつながるリスクもあります。以前は「NAFLD(非アルコール性脂肪肝疾患)」という名称が使われていましたが、最近では「MASLD(代謝異常関連脂肪性肝疾患)」や「MAFLD(代謝異常関連脂肪肝疾患)」という表現が主流になりつつあります。これは、病気の本質がアルコールではなく代謝の異常にあることをより明確に伝えるためです。
原因と症状の特徴
脂肪肝は、主に代謝の乱れや生活習慣の積み重ねによって起こります。
よくある原因
- 内臓脂肪型の肥満(特にお腹まわり)
- 血糖値が高い、糖尿病がある
- 中性脂肪やLDLコレステロールが高い
- 高血圧
- 食べすぎ、飲みすぎ、運動不足、睡眠不足、ストレス
体重が標準の方でも、こうした代謝異常があれば脂肪肝になる可能性があります。多くの場合、脂肪肝には自覚症状がありません。健康診断で肝臓の数値(AST、ALTなど)が高くなって気づくケースが大半です。症状がないからといって安心せず、肝臓からのサインとして早めに対策を始めることが大切です。
診断と治療の方針
脂肪肝の診断には、次のような情報をもとに総合的に判断します。
- 血液検査(肝機能、血糖、脂質、HbA1cなど)
- BMIや血圧などの測定
- 腹部エコー検査
重度の脂肪肝や肝硬変が疑われる場合には、専門医療機関での精査をご案内します。治療の基本は、生活習慣の見直しです。
- 体重が多い場合は、5%の減量で肝臓の脂肪が大きく改善するとされています
- バランスのとれた食事、過食や飲酒の見直し
- 無理のない範囲での運動(速歩きや有酸素運動など)
- 良質な睡眠やストレス管理も大切です
薬による治療は、現時点で脂肪肝そのものを直接改善する薬は限られていますが、糖尿病や脂質異常症の治療をしっかり行うことで、結果的に肝臓の状態が良くなることが多くあります。
当院での対応
脂肪肝は、症状がないうちに見つけて生活を見直すことで、進行を防ぐことができる病気です。脂肪肝の治療の肝は内臓脂肪の減量ですが、そのアプローチは当院の最も得意とするところです。「肝臓の数値が高いと言われた」「脂肪肝と診断されたが放置している」「生活習慣をどう改善してよいか分からない」——そうしたときは、ぜひ一度ご相談ください。