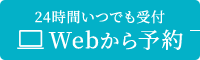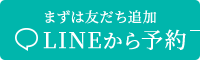気管支喘息(ぜんそく)とは
 気管支喘息は、空気の通り道である「気道」に慢性的な炎症が起こる病気です。その結果、咳やゼーゼーする呼吸音(喘鳴)、といった症状が繰り返し起こります。放置すると症状が重くなり、日常生活に支障をきたすこともあるため、早めの対応が大切です日本では約800万人が喘息を持つとされ、成人の約8%に相当します。子どもに多い病気と思われがちですが、中高年から発症する「成人発症喘息」も多く、誰でもかかり得る病気です。
気管支喘息は、空気の通り道である「気道」に慢性的な炎症が起こる病気です。その結果、咳やゼーゼーする呼吸音(喘鳴)、といった症状が繰り返し起こります。放置すると症状が重くなり、日常生活に支障をきたすこともあるため、早めの対応が大切です日本では約800万人が喘息を持つとされ、成人の約8%に相当します。子どもに多い病気と思われがちですが、中高年から発症する「成人発症喘息」も多く、誰でもかかり得る病気です。
気管支喘息の病態
 気管支喘息では、気道に慢性的な炎症が起こっています。炎症によって気道が狭くなり、発作的な咳や息苦しさが出やすい状態になります。
気管支喘息では、気道に慢性的な炎症が起こっています。炎症によって気道が狭くなり、発作的な咳や息苦しさが出やすい状態になります。
炎症タイプの違い
気管支喘息の炎症には2つのタイプがあります。
好酸球(アレルギー体質に関わる白血球の一種)が関与するタイプ
子どものころからのアレルギー体質に関連して起こることが多く、小児期に発症する喘息でよく見られます。このタイプは炎症に好酸球という細胞が深く関わっており、吸入ステロイド薬が効きやすいのが特徴です。
好中球(感染や炎症の時に働く白血球の一種)が関与するタイプ
大人になってから発症する喘息では、タバコの煙や大気汚染、感染などの環境因子が大きく関与するとされており、好中球という細胞が中心的に関わります。このタイプは薬が効きにくい場合もあるため、治療には工夫が必要となります。
治療方針の違い
炎症タイプによって薬の効きやすさや治療の選び方が異なります。当院では患者さん一人ひとりの病態を見極め、最も適した治療を選択します。
気道リモデリング
炎症を放置すると、気管支の壁が厚く硬くなり、空気の通り道が狭く元に戻りにくくなることがあります。これを「気道リモデリング」と呼びます。このリモデリングが進行すると、喘息の重症度が増していきます。このリモデリングを防ぐためにも、症状が軽いときでも炎症をしっかり抑える治療を続けることが大切です。
気管支喘息の症状
 「良くなったり悪くなったりを繰り返す」のが特徴です。症状がない時期でも気道の炎症は続いており、風邪・花粉・タバコの煙などの刺激をきっかけに再び悪化することがあります。
「良くなったり悪くなったりを繰り返す」のが特徴です。症状がない時期でも気道の炎症は続いており、風邪・花粉・タバコの煙などの刺激をきっかけに再び悪化することがあります。
典型的な症状
気管支喘息では、気道の炎症によって空気の通り道が狭くなるため、次のような症状が繰り返し起こります。夜間〜早朝に悪化しやすいのが特徴です。
- ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音(喘鳴)
- 息苦しさ、呼吸困難感
- 長引く咳
喘息発作の主な誘因
喘息の症状は、日常生活のさまざまなきっかけで悪化することがあります。特に多いのは風邪などの呼吸器感染症です。
呼吸器感染症(感冒)
喘息発作のもっとも大きな原因は風邪などの呼吸器感染症です。発作の多くが感冒をきっかけに起こるとされており、特にライノウイルスやインフルエンザなどの感染が関与します。
アレルギー物質
ダニやハウスダスト、花粉、ペットの毛などアレルギーの原因物質に触れると、発作のきっかけになります。
たばこ・大気汚染
喫煙や受動喫煙、大気汚染(排気ガスやPM2.5など)は気道を刺激し、発作を起こしやすくします。
気象や環境の変化
低気圧や気温差、湿度の変化は気道を刺激して発作の要因となります。台風や季節の変わり目に症状が悪化する患者さんも少なくありません。
運動・ストレス・薬剤など
激しい運動や強い感情の変化、ストレスも誘因になることがあります。また、一部の薬(解熱鎮痛薬やβ遮断薬など)が影響する場合もあります。
気管支喘息の長期管理
 目標は発作や症状を抑え、日常生活を制限なく送れるようにすることです。このことにより、将来的なリモデリングの進行による気管支喘息の悪化を防ぐことにもつながっていきます。
目標は発作や症状を抑え、日常生活を制限なく送れるようにすることです。このことにより、将来的なリモデリングの進行による気管支喘息の悪化を防ぐことにもつながっていきます。
薬物療法
中心となるのは、吸入ステロイド薬(ICS)です。補助的に吸入の気管支拡張薬が使用されます。コントロール不十分/不良の場合には治療の強化を検討します。逆に半年以上にわたりコントロールが安定している場合には、治療を弱めることを検討します。吸入薬を正しく使えているかどうかの確認も重要になります。重症で、当院で管理困難と判断した場合は、専門病院を紹介します。
生活習慣と予防
- 風邪(呼吸器感染症)予防:手洗い・うがいを徹底
- ダニやハウスダスト対策:寝具の清掃、室内換気
- 花粉やペットの毛の回避
- 禁煙、受動喫煙を避ける
発作時の対応
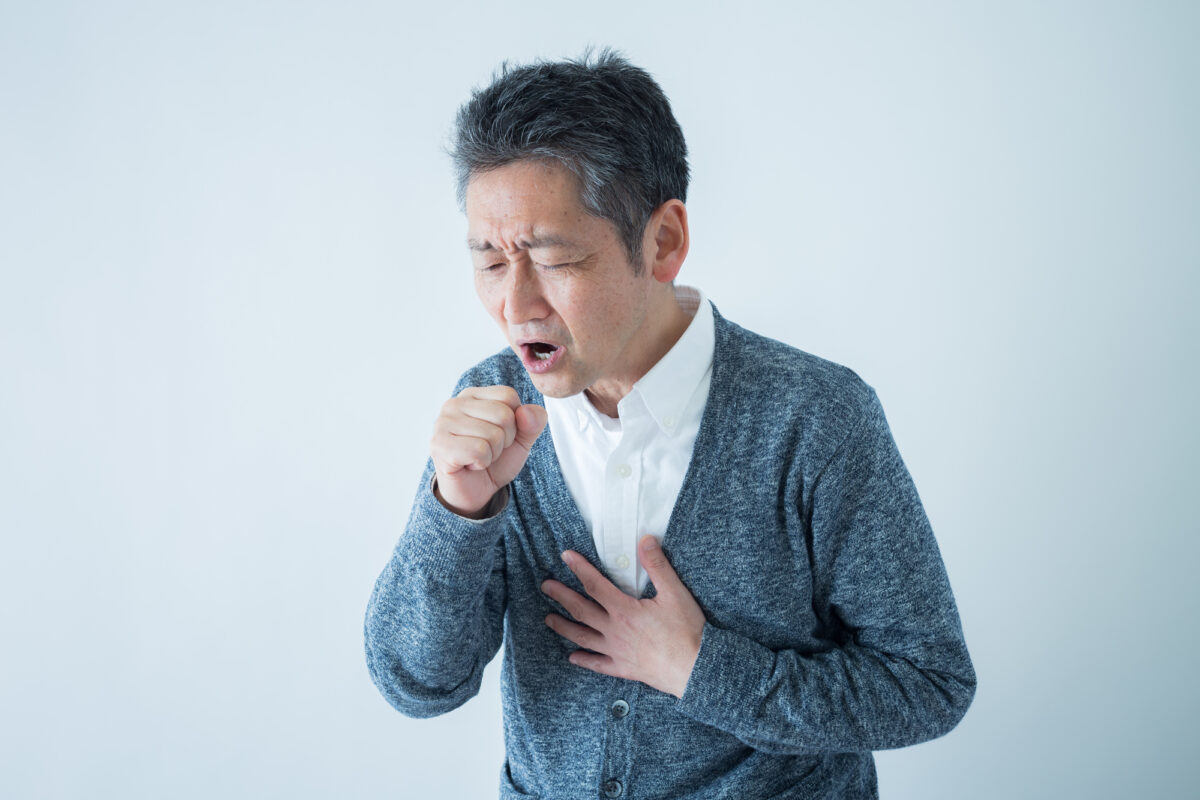 気管支喘息の発作は、その重症度に応じて対応します。軽症の場合には即効性のある気管支拡張薬の吸入で対応します。苦しくて横になれないような中等度以上の発作では、当院では対応困難ですので、専門病院を紹介します。
気管支喘息の発作は、その重症度に応じて対応します。軽症の場合には即効性のある気管支拡張薬の吸入で対応します。苦しくて横になれないような中等度以上の発作では、当院では対応困難ですので、専門病院を紹介します。
よくあるご質問
長引く咳(3週間以上)が続いています。風邪でしょうか?
3週間以上続く長引く咳は、単なる風邪ではなく「咳喘息」「アレルギー」「逆流性食道炎」などが原因の場合があります。特に咳喘息は放置すると本格的な喘息に進展することがあるため、長引く咳は自己判断せず、一度医療機関を受診してください。
夜間や早朝に咳や息苦しさが強くなるのはなぜですか?
気管支喘息では「夜間の咳」や「早朝の呼吸困難」が典型的です。夜間は自律神経の働きや体温の変化により気道が狭くなりやすいため、症状が出やすくなります。夜間の咳が続く場合は喘息の可能性が高いため、診察をおすすめします。
運動するとゼーゼーして苦しくなります。運動は控えるべきですか?
「運動誘発喘息」は、激しい運動をきっかけに咳や息切れが起こるタイプです。必ずしも運動をやめる必要はなく、治療でコントロールできれば多くの方は運動を楽しめます。必要に応じて、運動前に吸入薬を使用して発作を予防する方法もあります。
吸入ステロイド薬は一生続けないといけないのですか?
吸入ステロイド薬(ICS)は「喘息治療の基本薬」です。症状がない時も気道の炎症は続いているため、自己中断は危険です。半年以上にわたり症状が安定していれば、医師の判断で治療を弱めることも可能ですので、必ず医師の指示に従ってください。
吸入薬に副作用はありますか?
吸入ステロイド薬は全身への副作用が少ないのが特徴です。ただし「口腔カンジダ症」などの局所的な副作用は起こり得ます。吸入後にうがいをすることで多くの場合は予防できます。副作用が不安な場合は医師にご相談ください。
気管支喘息は治りますか?
喘息は「完治」というより「長期にわたるコントロール」が重要です。治療を継続することで発作を防ぎ、日常生活を制限なく送ることが可能です。小児喘息では成長とともに症状が軽快することもあります。
喘息と咳喘息はどう違うのですか?
咳喘息は「咳だけが長く続く」タイプの喘息で、ゼーゼーや息苦しさを伴わないのが特徴です。放置すると通常の喘息に移行することがあるため、早めの診断と吸入治療が大切です。
風邪をひくと必ず喘息が悪化しますか?
風邪(呼吸器感染症)は喘息発作の大きな誘因です。必ず悪化するわけではありませんが、多くの方が症状を起こしやすくなります。手洗い・うがい、予防接種(インフルエンザなど)で風邪を防ぐことが重要です。市販の咳止め薬では喘息を根本的に治すことはできませんので、必ず医師の診察を受けてください。
妊娠中や授乳中でも吸入薬を使えますか?
妊娠中や授乳中でも、多くの吸入薬は安全性が確認されています。喘息を放置すると母体や胎児に悪影響を及ぼすため、自己判断で治療を中止するのは危険です。必ず主治医に相談のうえで継続してください。