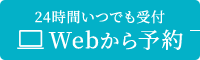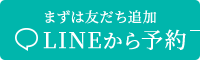南流山で呼吸器内科をお探しの方へ
呼吸器内科は、肺や気管支、気道などの呼吸に関わる臓器の異常を内科的に診断・治療する専門の診療科です。咳、痰、息切れなどの症状は日常生活の中でよく見られますが、放置すると重篤な疾患が隠れていることもあるため、早期の評価と対応が重要です。また、いびきや日中の強い眠気、熟睡感のなさなどから気づかれる閉塞性睡眠時無呼吸症候群も、頻度の高い呼吸器疾患の一つであり、生活習慣病との関連が深いことが知られています。当院ではこのような症状の有無にかかわらず、呼吸に関わる幅広い問題に対応しています。南流山内科トータルクリニックでは、内科全般に対応できる総合内科の視点を活かし、呼吸器疾患にも丁寧に対応しています。特に高血圧、糖尿病、腎臓病などの慢性疾患をお持ちの方は、呼吸器の病気が重症化しやすいため、全身の状態をふまえた総合的な診療を重視しています。診察では、症状の経過を丁寧に確認し、必要に応じて胸部レントゲンや血液検査などを実施し、さらに精密な検査や専門的な治療が必要と判断される場合には、速やかに連携する専門医療機関をご紹介いたします。呼吸や睡眠に関する不安がある方は、お気軽にご相談ください。
呼吸器に関連した症状
呼吸器に関連した症状は、軽い不調に見えて、重大な病気のサインであることも少なくありません。当院では、症状を丁寧に診察し、必要な検査・治療をご提案しています。以下に当院でよくご相談いただく症状をご紹介しますので、気になる症状があればお気軽にご相談ください。
咳が長引く
 3週間以上続く咳は「遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)」と呼ばれ、呼吸器内科を受診される理由の中でも非常に多い症状です。長引く咳にはさまざまな原因があり、症状の現れ方や時間帯、痰の有無、喉の違和感の有無などから、丁寧に原因を見極めていくことが重要です。必要に応じて胸部レントゲンなどの画像検査を行う場合もあります。なかには、肺結核や肺がんといった重大な病気が原因となっていることもあるため、咳が長く続くときは早めの受診をおすすめします。考えられる主な原因は以下のようなものがあります。
3週間以上続く咳は「遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)」と呼ばれ、呼吸器内科を受診される理由の中でも非常に多い症状です。長引く咳にはさまざまな原因があり、症状の現れ方や時間帯、痰の有無、喉の違和感の有無などから、丁寧に原因を見極めていくことが重要です。必要に応じて胸部レントゲンなどの画像検査を行う場合もあります。なかには、肺結核や肺がんといった重大な病気が原因となっていることもあるため、咳が長く続くときは早めの受診をおすすめします。考えられる主な原因は以下のようなものがあります。
- 感染後咳嗽
- 咳喘息
- アトピー咳嗽
- 後鼻漏症候群
- マイコプラズマ肺炎
痰がでる
 痰(たん)は、気道に炎症や感染が起こったときに、体が異物や病原体を排出しようとして出てくる分泌物です。風邪や気管支炎などでも一時的にみられますが、色や量、粘り気に変化がある場合は注意が必要です。とくに黄色や緑色の痰が続くときは、細菌性の気道感染症や肺炎の可能性があり、抗菌薬による治療が必要となる場合があります。また、喫煙歴のある方では、慢性気管支炎やCOPDといった慢性呼吸器疾患の一症状であることもあります。当院では、痰の性状や咳・発熱などの伴う症状を総合的に評価し、必要に応じて胸部レントゲンや血液検査を行ったうえで、適切な治療をご提案いたします。
痰(たん)は、気道に炎症や感染が起こったときに、体が異物や病原体を排出しようとして出てくる分泌物です。風邪や気管支炎などでも一時的にみられますが、色や量、粘り気に変化がある場合は注意が必要です。とくに黄色や緑色の痰が続くときは、細菌性の気道感染症や肺炎の可能性があり、抗菌薬による治療が必要となる場合があります。また、喫煙歴のある方では、慢性気管支炎やCOPDといった慢性呼吸器疾患の一症状であることもあります。当院では、痰の性状や咳・発熱などの伴う症状を総合的に評価し、必要に応じて胸部レントゲンや血液検査を行ったうえで、適切な治療をご提案いたします。
熱がでる
 熱は、体が感染症などの異常に反応して起こる重要なサインです。とくに咳や痰、息苦しさ、胸の痛みなどを伴う発熱は、肺炎や気管支炎などの呼吸器感染症の可能性があります。これらは適切な治療を行わないと重症化することもあり、とくに高齢の方や基礎疾患(糖尿病、腎疾患、心疾患など)をお持ちの方では注意が必要です。また、発熱が長引く場合には、結核や肺がんなどが隠れていることもあります。当院では、症状の経過や全身状態を詳しく確認したうえで、必要に応じて胸部レントゲンや血液検査を行い、診断と治療につなげてまいります。気になる熱が続く場合は、自己判断せず早めにご相談ください。
熱は、体が感染症などの異常に反応して起こる重要なサインです。とくに咳や痰、息苦しさ、胸の痛みなどを伴う発熱は、肺炎や気管支炎などの呼吸器感染症の可能性があります。これらは適切な治療を行わないと重症化することもあり、とくに高齢の方や基礎疾患(糖尿病、腎疾患、心疾患など)をお持ちの方では注意が必要です。また、発熱が長引く場合には、結核や肺がんなどが隠れていることもあります。当院では、症状の経過や全身状態を詳しく確認したうえで、必要に応じて胸部レントゲンや血液検査を行い、診断と治療につなげてまいります。気になる熱が続く場合は、自己判断せず早めにご相談ください。
喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューする)

息を吐くときに「ゼーゼー」「ヒューヒュー」と音がすることがあります。これは“喘鳴(ぜんめい)”と呼ばれる症状で、気道が狭くなり、空気の通り道が細くなることで笛のような音が鳴るのが原因です。主な原因としては、気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などがあり、アレルギーや風邪などの感染症がきっかけで悪化することもあります。夜間や早朝、季節の変わり目に症状が強くなる方は注意が必要です。また、高齢の方では、心不全が原因で喘鳴を起こす「心臓喘息」という状態もあり、鑑別が重要になります。当院では、喘鳴の有無や咳・息苦しさなどを丁寧に評価し、必要に応じて胸部レントゲンや治療薬のご提案を行います。ゼーゼーする息づかいが続く場合は、お早めにご相談ください。
息切れ
 階段の上り下りや少し歩いただけで息が上がる「息切れ」は、呼吸器の病気でよくみられる症状のひとつです。とくに慢性閉塞性肺疾患や気管支喘息、間質性肺炎などでは、空気の通り道や肺の働きに異常があるため、呼吸がうまくできずに息切れが生じます。初期のうちは風邪のあとの体力低下と見過ごされがちですが、進行すると日常の軽い動作でも強く感じるようになり、放置すると重症化することもあります。また、心不全や貧血なども原因となることがありますので、呼吸器疾患との見極めが重要になります。当院では、息切れの出やすい状況や頻度、伴う咳や痰、喘鳴などの呼吸器症状を丁寧に確認し、必要に応じて胸部レントゲンや血液検査を行います。呼吸の不調が続く場合は、早めにご相談ください。
階段の上り下りや少し歩いただけで息が上がる「息切れ」は、呼吸器の病気でよくみられる症状のひとつです。とくに慢性閉塞性肺疾患や気管支喘息、間質性肺炎などでは、空気の通り道や肺の働きに異常があるため、呼吸がうまくできずに息切れが生じます。初期のうちは風邪のあとの体力低下と見過ごされがちですが、進行すると日常の軽い動作でも強く感じるようになり、放置すると重症化することもあります。また、心不全や貧血なども原因となることがありますので、呼吸器疾患との見極めが重要になります。当院では、息切れの出やすい状況や頻度、伴う咳や痰、喘鳴などの呼吸器症状を丁寧に確認し、必要に応じて胸部レントゲンや血液検査を行います。呼吸の不調が続く場合は、早めにご相談ください。
咳や深呼吸で胸が痛む
咳をしたときや深く息を吸ったときに胸が痛む場合、呼吸器に関係する病気が原因となっていることがあります。例えば「胸膜炎」は、肺の外側を覆う膜(胸膜)に炎症が起きる病気で、呼吸のたびに鋭い痛みを感じるのが特徴です。肺炎に伴って発症することもあり、注意が必要です。また、肺に穴があいて空気が漏れる「気胸」でも、同様に胸の痛みが生じます。いずれも、深呼吸や咳で痛みが強くなる点が共通しています。そのほか、肋間神経痛や筋肉痛など、肺以外の原因で同じような痛みが起こることもあります。痛みの場所や性質、咳や熱、呼吸の苦しさなどをもとに、慎重な判断が必要です。
当院では、問診と診察を丁寧に行い、必要に応じて胸部レントゲンなどの検査を実施し、適切な診断と治療につなげてまいります。胸の痛みが続く場合は、早めにご相談ください。
寝ているときにいびきをかき、呼吸がとまることがある
 「いびきがうるさい」「眠っている間に呼吸が止まっているようだ」と家族に指摘されたことはありませんか?このような症状は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。睡眠時無呼吸症候群では、眠っている間に喉の奥の気道が塞がり、呼吸が何度も止まることで、質の高い睡眠がとれず、日中の強い眠気や集中力の低下、高血圧や心疾患のリスクが高まることも知られています。とくに肥満気味の方や首回りが太い方、顎が小さい方などはリスクが高く、気づかずに長年放置されているケースも少なくありません。当院では簡易検査を行い、必要に応じた治療をご案内いたします。睡眠中の呼吸が気になる方や、日中の眠気が強い方は、お早めにご相談ください。
「いびきがうるさい」「眠っている間に呼吸が止まっているようだ」と家族に指摘されたことはありませんか?このような症状は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。睡眠時無呼吸症候群では、眠っている間に喉の奥の気道が塞がり、呼吸が何度も止まることで、質の高い睡眠がとれず、日中の強い眠気や集中力の低下、高血圧や心疾患のリスクが高まることも知られています。とくに肥満気味の方や首回りが太い方、顎が小さい方などはリスクが高く、気づかずに長年放置されているケースも少なくありません。当院では簡易検査を行い、必要に応じた治療をご案内いたします。睡眠中の呼吸が気になる方や、日中の眠気が強い方は、お早めにご相談ください。
急性の呼吸器感染症
喉の痛みや咳、発熱などをきっかけに受診される方の多くは、何らかの呼吸器感染症にかかっている可能性があります。これらはウイルスや細菌が原因で、症状の経過や重症度、治療方針は病原体によって異なります。軽症で自然に治るものから、抗菌薬による治療が必要なもの、さらには周囲への感染力が強く注意が必要なものまでさまざまです。ここでは、当院でよく診療する代表的な急性呼吸器感染症についてご紹介します。気になる症状がある方は、早めの受診をご検討ください。
感冒
 感冒とは、鼻や喉などの上気道に生じる急性の炎症を総称した「かぜ症候群」のことで、日常的に最もよくみられる感染症です。原因のほとんどはウイルス感染で、ライノウイルスやコロナウイルスなど、200種類以上のウイルスが関与します。特異的な検査は存在せず、問診や診察から診断されます。
感冒とは、鼻や喉などの上気道に生じる急性の炎症を総称した「かぜ症候群」のことで、日常的に最もよくみられる感染症です。原因のほとんどはウイルス感染で、ライノウイルスやコロナウイルスなど、200種類以上のウイルスが関与します。特異的な検査は存在せず、問診や診察から診断されます。
症状と経過
症状はゆるやかに始まり、喉の違和感やくしゃみから、鼻汁・鼻づまり、咽頭痛、咳へと進行します。発熱は軽度で、筋肉痛や倦怠感がみられても軽く、インフルエンザのような強い全身症状は通常みられません。症状は数日でピークを迎え、ほとんどは4~7日で自然軽快します。咳や鼻汁がやや長引くこともありますが、通常は2週間以内に消失します。
治療
特効薬はなく、安静、水分摂取を基本として対症療法(症状に応じた薬剤による対応)を行います。鎮咳薬は咳を一時的に抑える効果がありますが、痰の排出を妨げることがあるため、咳が強くない場合には無理に止めない方がよいこともあります。抗菌薬はウイルスには無効であり、細菌性の二次感染が疑われる場合を除いて使用しません。
インフルエンザ
 インフルエンザとは、A型またはB型のインフルエンザウイルスによる急性呼吸器感染症です。突然の高熱、全身倦怠感、筋肉痛や関節痛などの強い全身症状が特徴で、一般的な風邪とは異なります。日本では毎年冬に流行し、特に1〜2月にピークを迎えます。人口の約1割が毎年感染するとされ、高齢者や基礎疾患を有する人、小児では重症化のリスクが高く、毎年のワクチン接種が推奨されます。
インフルエンザとは、A型またはB型のインフルエンザウイルスによる急性呼吸器感染症です。突然の高熱、全身倦怠感、筋肉痛や関節痛などの強い全身症状が特徴で、一般的な風邪とは異なります。日本では毎年冬に流行し、特に1〜2月にピークを迎えます。人口の約1割が毎年感染するとされ、高齢者や基礎疾患を有する人、小児では重症化のリスクが高く、毎年のワクチン接種が推奨されます。
症状と経過
1〜2日の潜伏期の後、突然38℃以上の高熱と全身の倦怠感が出現します。頭痛、筋肉痛、関節痛も強く、咳や喉の痛み、鼻水などの呼吸器症状も伴いますが、全身症状の方が目立つのが特徴です。解熱後に再度発熱・悪化する場合は肺炎の可能性を考慮します。
診断
当院では、鼻咽頭ぬぐい液を用いた抗原検査で診断しています。抗原検査は15分程度で結果が出ますが、正確な判定のためには発症から12~24時間以上経過してからの検査が推奨されます。ウイルス量が少ない場合は陰性となることもあり、症状や流行状況も踏まえて総合的に判断します。
治療
発症後48時間以内であれば、対症療法(症状に応じた薬剤による対応)に加えて抗インフルエンザ薬の使用により症状緩和と合併症予防が期待できます。また、毎年のワクチン接種は発症や重症化を防ぐ上で非常に重要です。
自宅療養期間
厚労省の推奨に基づき、以下のような自宅療養が勧められています。
- 発症日を0日目とし、少なくとも5日間は外出を控えること(特に最初の2〜3日間は感染力が強い)
- 解熱後2日間(小児では3日間)が経過するまでは外出を控えること
- 発症から7日目までは、マスク着用や高齢者、基礎疾患のある方との接触は避けること
外出の再開は、「発症から5日以上経過している」かつ「解熱後2日以上(小児は3日以上)経過している」という両方の条件を満たすことが原則です。職場や学校によっては、独自の基準や提出書類が求められる場合もありますので、必要に応じてご確認ください。
COVID-19
 COVID-19とは、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)によって引き起こされる呼吸器の感染症です。現在の主流株では、発熱や喉の痛み、咳などの「風邪のような症状」が主となっており、以前のような重症肺炎や嗅覚・味覚障害の頻度は減少しています。多くの方は軽症で自然に回復しますが、高齢者や持病のある方などでは注意が必要です。2020年以降、COVID-19は世界的に広がり、日本でも多くの感染者が確認されました。2023年5月からは感染症法上の「5類感染症」となり、通常の医療体制で対応されています。
COVID-19とは、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)によって引き起こされる呼吸器の感染症です。現在の主流株では、発熱や喉の痛み、咳などの「風邪のような症状」が主となっており、以前のような重症肺炎や嗅覚・味覚障害の頻度は減少しています。多くの方は軽症で自然に回復しますが、高齢者や持病のある方などでは注意が必要です。2020年以降、COVID-19は世界的に広がり、日本でも多くの感染者が確認されました。2023年5月からは感染症法上の「5類感染症」となり、通常の医療体制で対応されています。
症状と経過
潜伏期間は通常1〜7日で、発熱・咽頭痛・咳・鼻水などの風邪様症状から始まります。一部の方では、味覚・嗅覚の低下や全身の強い倦怠感が見られることもあります。大半の方は1週間程度で回復しますが、高齢者や基礎疾患のある方、妊娠後期の方では、肺炎や低酸素血症、呼吸不全、血栓症(脳梗塞・心筋梗塞・肺塞栓など)をきたすことがあるため注意が必要です。
診断
当院では、鼻咽頭ぬぐい液を用いた抗原検査で診断しています。抗原検査は15分程度で結果が出ますが、正確な判定のためには発症から24時間以上経過してからの検査が推奨されます。ウイルス量が少ない場合は陰性となることもあり、症状や流行状況も踏まえて総合的に判断します。
治療
ほとんどの方は対症療法(症状に応じた薬剤による対応)で回復します。当院では、解熱鎮痛薬や咳止め、喉の痛みへの処方など、症状に応じた治療を行います。重症化のリスクがある方には、医師の判断により抗ウイルス薬の使用を検討します。しかしながら、抗ウイルス薬は条件を満たした方に限られ、費用面も含めて慎重な判断が必要です。
自宅療養期間
厚労省の推奨に基づき、以下のような自宅療養が勧められています。
- 発症日を0日目とし、少なくとも5日間は外出を控えること(特に最初の3日間にかけては感染力が強い)
- 症状が改善し、解熱および呼吸器症状の改善後24時間以上経過するまでは外出を控えること
- 発症から10日目までは、マスク着用や高齢者、基礎疾患のある方との接触は避けること
後遺症
COVID-19回復後に数週間から数か月以上にわたって体調不良が続くことがあり、「コロナ後遺症」または「Long COVID」と呼ばれています。とくに多く見られるのが慢性的な倦怠感(慢性疲労)で、日常生活や仕事に支障をきたすこともあります。当院では、こうした慢性疲労に対して漢方薬などを用いた体調の調整を行っており、患者さんの症状に応じた対応を心がけています。
マイコプラズマ感染症
 マイコプラズマ感染症とは、マイコプラズマ・ニューモニエという特殊な細菌によって引き起こされる呼吸器感染症です。子どもから若年〜中年層に多く、長引く渇いた咳が特徴です。
マイコプラズマ感染症とは、マイコプラズマ・ニューモニエという特殊な細菌によって引き起こされる呼吸器感染症です。子どもから若年〜中年層に多く、長引く渇いた咳が特徴です。
症状と経過
潜伏期間は1〜3週間とやや長く、初期は発熱・倦怠感・喉の痛みなど、風邪と似た症状から始まります。次第に乾いた咳が目立つようになり、熱が下がった後も2〜3週間以上咳だけが続くことがあり、「歩行性肺炎」とも呼ばれます。
診断
診断は症状の経過や流行状況、聴診所見、胸部レントゲンなどの臨床的評価を中心に行います。胸部レントゲンの陰影が明瞭でも聴診所見に乏しいというギャップが特徴です。必要に応じてマイコプラズマ抗原迅速検査などを組み合わせて診断を補強します。抗原検査の結果は15分ほどで出ますが、少なくとも発症3日以降の検査が望ましく、偽陰性も多いです。
治療
マクロライド系の抗菌薬が第一選択とされますが、近年は耐性菌が増加しています。効果が不十分な場合には、ニューキノロン系への変更を検討することがあります。治療は医師の判断で行いますので、自己判断せず、症状が長引く場合は再受診をご検討ください。
クラミジア肺炎
クラミジア肺炎とは、クラミドフィラ・ニューモニエという特殊な細菌によって引き起こされる呼吸器感染症です。咳が長引く点など、症状の経過はマイコプラズマ感染症と似ていますが、クラミジア肺炎は40~70歳代の中高年に多く、より緩やかに進行する傾向があります。
症状と経過
潜伏期間は3〜4週間と長めで、初めは喉の違和感や声のかすれ(嗄声)など風邪のような症状が出ます。その後、痰の少ない乾いた咳が長引き、肺炎に進行します。発熱は軽度〜中等度(38℃前後)で、重症化することは少ないです。マイコプラズマ感染症と同様に全身状態が良好で咳のみ長引くことが多く、「歩行性肺炎」とも呼ばれます。
診断
クラミジア肺炎は、迅速検査や血液検査では明確に診断することが難しいため、症状や経過、画像所見を総合的に見て判断します。医師はこの病気が疑われる場合には、効果のある抗菌薬を経験的に処方し、症状の改善を確認しながら診断していきます。
治療
マイコプラズマ感染症と同じく第一選択はマクロライド系の抗菌薬です。重症例や他の細菌も一緒に感染していると考えられる場合には、ニューキノロン系抗菌薬が選択されることもあります。
百日咳
 百日咳とは、百日咳菌によって引き起こされる呼吸器感染症です。子どもに多い病気という印象がありますが、ワクチンの効果が薄れてくる成人でも感染が見られます。小児では典型的な激しい咳発作を起こしますが、成人では咳が長引くものの症状が軽いため、百日咳とは気づかれにくいことがあります。とくに乳幼児では重症化することがあり、周囲の大人が感染源になることもあるため、注意が必要です。
百日咳とは、百日咳菌によって引き起こされる呼吸器感染症です。子どもに多い病気という印象がありますが、ワクチンの効果が薄れてくる成人でも感染が見られます。小児では典型的な激しい咳発作を起こしますが、成人では咳が長引くものの症状が軽いため、百日咳とは気づかれにくいことがあります。とくに乳幼児では重症化することがあり、周囲の大人が感染源になることもあるため、注意が必要です。
症状と経過
潜伏期間は7〜10日程度で、初期は鼻水・くしゃみ・軽い咳など、風邪に似た症状から始まります。2週間を経過したくらいから咳が激しくなり、特に夜間に咳き込む、咳で声が枯れる、などの症状が現れます。咳が数週間から長い場合は2〜3か月続くこともあり、「百日咳」という名前の由来にもなっています。発熱は軽度で、咳以外の全身症状は少ないのが特徴です。
診断
検査には抗原検査やPCR検査、抗体検査などがありますが、感度の低下や、結果が出るまでに時間がかかることから、現場ではあまり使いにくいのが実情です。さらに成人では典型的な症状を欠くことが多いため、明確に診断することは難しいです。流行の状況や臨床経過を総合的に判断していきます。
治療
百日咳は、百日咳菌が産生する毒素によって気道に炎症が起こり、強い咳が引き起こされます。治療にはマクロライド系の抗菌薬を使用しますが、抗菌薬には百日咳菌を駆除する効果はあっても毒素を中和する効果はありません。したがって、百日咳の診断がつく痙咳期に入ってから抗菌薬を開始しても咳症状を抑える効果はほとんどないと言われています。それでも抗菌薬を投与するのは、感染者本人から周囲への菌の拡散を防ぎ、これ以上新たな感染者を出さないためです。実際、適切な抗菌薬治療を行えば菌の排出期間は治療開始後5日程度でほぼ終息するとされます。
他人にうつす時期
百日咳菌は非常に感染力が高く、濃厚接触者の80%ほどに感染すると言われています。最も感染させやすい時期は発症後2週間程度の間ですが、この時期に百日咳の診断が困難なため、感染拡大につながりやすいとされています。小児では学校保健安全法により「特有の咳が消失するまで、または適正な抗菌薬治療開始後5日を経過するまで」登校停止と定められています。成人では法律での出勤停止規定はありませんが、感染拡大防止の観点から発症後少なくとも5日間は周囲(特に乳児や高齢者)との接触を控えることが推奨されます。
成人市中肺炎
 市中肺炎とは、普段の生活をしている中でかかる肺の感染症です。風邪とは違い、肺に細菌が入り込んで炎症を起こします。主に「肺炎球菌」などの細菌が原因ですが、「マイコプラズマ」などの特殊な細菌が原因になることもあります。若い人から高齢の方まで誰でもかかりますが、特に高齢の方や持病のある人は重くなりやすいため注意が必要です。
市中肺炎とは、普段の生活をしている中でかかる肺の感染症です。風邪とは違い、肺に細菌が入り込んで炎症を起こします。主に「肺炎球菌」などの細菌が原因ですが、「マイコプラズマ」などの特殊な細菌が原因になることもあります。若い人から高齢の方まで誰でもかかりますが、特に高齢の方や持病のある人は重くなりやすいため注意が必要です。
症状と経過
典型的な症状は、発熱、咳、黄色や緑色の痰、胸の痛み、息切れなどです。若年者では比較的軽く済むこともありますが、高齢者では熱が出ない、意識がぼんやりする、食欲が落ちるなど非典型的な症状で始まることもあり注意が必要です。病原体や体力によっては、数日で改善する軽症例から、入院管理が必要となる中〜重症例まで幅広い経過をとります。
診断
診断は、症状の経過、聴診、胸部レントゲン、血液検査などを組み合わせて行います。胸部レントゲンで肺に炎症性の陰影(浸潤影)が確認されることで、診断が確定することが多く、重症度に応じてCRPや白血球数、酸素飽和度の測定も行います。原因となる菌の特定には、喀痰検査や尿中抗原検査(肺炎球菌・レジオネラ)を追加することもあります。
治療
治療の基本は「飲み薬(抗菌薬)」です。症状や年齢、持病に応じて、原因と思われる菌に効く薬を選びます。また、十分な水分補給・安静・発熱への対応など、対症療法も併せて行います。軽症であれば外来での内服治療が可能ですが、重症例や高齢者、基礎疾患のある方では入院加療が必要になることもあります。
予防
市中肺炎を予防するには、日常生活での体調管理とワクチン接種が重要です。特に高齢者や基礎疾患のある方では、肺炎の発症や重症化を防ぐために、以下のような対策が推奨されています。
- 肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンの定期的な接種
- 体調不良を感じた際は早めの受診を心がける
- 栄養バランスのとれた食事と十分な睡眠、口腔衛生の維持
肺炎は早期に診断・治療を行えば多くの場合は改善可能な病気ですが、放置すると重症化することがあります。とくに高齢の方では発熱が目立たず進行することもあるため、体調の変化に気づいた際はお早めにご相談ください。
慢性呼吸器疾患
咳や痰、息切れといった呼吸器の症状が長く続く場合、それは「慢性呼吸器疾患」が背景にある可能性があります。これらの病気は、気道や肺に慢性的な炎症や障害があることによって生じ、放置すると徐々に悪化していく特徴があります。なかでも代表的なものが、たばこなどが原因で肺の働きが低下していく「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」や、アレルギー体質と関係して発作的な咳や息苦しさを繰り返す「気管支喘息」です。これらは早期に診断し、適切な治療を続けることで進行を抑えることが可能です。ここでは、それぞれの病気の特徴や診療のポイントについてご紹介します。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
 慢性閉塞性肺疾患(COPD:シーオーピーディー)は、主に喫煙によって肺が慢性的に炎症を起こし、息切れや咳、痰などの症状が徐々に進行していく病気です。肺の空気の通り道(気道)が狭くなったり、肺そのものが壊れてしまうことで、呼吸機能が低下していきます。一度壊れた肺は元に戻らないため、早期の発見と進行の抑制がとても大切です。
慢性閉塞性肺疾患(COPD:シーオーピーディー)は、主に喫煙によって肺が慢性的に炎症を起こし、息切れや咳、痰などの症状が徐々に進行していく病気です。肺の空気の通り道(気道)が狭くなったり、肺そのものが壊れてしまうことで、呼吸機能が低下していきます。一度壊れた肺は元に戻らないため、早期の発見と進行の抑制がとても大切です。
疫学
日本では40歳以上の約8.6%がCOPDと推定され、潜在患者は約500万人以上と考えられていますが、実際に診断・治療を受けている人はその一部にとどまっています。高齢化の影響で、今後もしばらくは患者数が高いまま推移すると見られています。2022年の人口動態統計によると、1年間に1万6,676人がCOPDにより亡くなっており、死因の第10位でした。
症状と経過
最も多い原因は喫煙で、喫煙年数と本数が多いほどCOPDのリスクが高まり、非喫煙者でも受動喫煙や大気汚染が要因となる場合があります。発症は特に40歳以上の中高年に多く、初期には動いたときの息切れ、長引く咳や痰が現れます。進行すると、日常生活の動作でも呼吸が苦しくなり、重症になると安静時にも息切れを感じるようになります。
診断
COPDの診断には、肺活量や息を吐く力を調べる「スパイロメトリー検査」が必要です。当院ではこの検査を行っていないため、COPDが疑われる場合には、必要に応じて専門病院をご紹介します。診断には、長期の喫煙歴、症状の経過、レントゲン所見なども参考になります。
治療
治療の基本は禁煙です。禁煙をすることで、それ以降の肺機能の低下を大きく抑えることができます。当院には禁煙に関する専門的知識を有する医師が在籍しており、医学的根拠に沿った禁煙支援にも対応しています。ご自身での禁煙が難しいと感じている方には、状況に応じたアドバイスや今後の対応のご相談も可能です。薬物治療は、吸入薬を使って気道を広げ、症状を和らげます。最初は長時間作用性抗コリン薬(LAMA)を使用し、効果が不十分な場合は、長時間作用性β₂刺激薬(LABA)を追加します。増悪を繰り返す場合や、血液中の好酸球が多い場合、喘息を合併している場合には、吸入ステロイド薬(ICS)を併用することもあります。そのほかにも、呼吸リハビリテーション、栄養指導、インフルエンザや肺炎球菌などのワクチン接種も大切です。病気が進行して呼吸不全をきたした場合には、在宅酸素療法を検討することがあります。ただし、過剰な酸素投与は二酸化炭素の排出障害を招く可能性があるため、医師の管理のもとで行う必要があります。早めの診断と治療により、進行を抑えて生活の質を保つことができます。
気管支喘息
 気管支喘息は、空気の通り道である「気道」に慢性的な炎症が起こり、発作的に咳や喘鳴、息苦しさが現れる病気です。日本では約800万人が喘息を持つとされ、成人の約8%が該当します。子どもに多い病気と思われがちですが、中高年から発症する「成人発症喘息」も多く、誰でもかかり得る病気です。放置すると症状が重くなり、日常生活に支障をきたすこともあるため、早めの対応が大切です。
気管支喘息は、空気の通り道である「気道」に慢性的な炎症が起こり、発作的に咳や喘鳴、息苦しさが現れる病気です。日本では約800万人が喘息を持つとされ、成人の約8%が該当します。子どもに多い病気と思われがちですが、中高年から発症する「成人発症喘息」も多く、誰でもかかり得る病気です。放置すると症状が重くなり、日常生活に支障をきたすこともあるため、早めの対応が大切です。
症状と経過
症状は、ちょっとした刺激(気候の変化、花粉、ハウスダスト、風邪、冷気、運動など)で発作的に現れます。以下のような症状が典型的です。
- 咳が長引く(特に夜間や早朝)
- 喘鳴(息を吐くときにゼーゼー・ヒューヒューと音がする)
- 胸が苦しくなる、呼吸がしにくいと感じる
- 深夜や明け方に息苦しさで目が覚めることがある
診断
診断は、症状の経過や既往歴、聴診所見などをもとに行います。必要に応じて、胸部レントゲンや呼吸機能検査、アレルギー検査などを検討します。喘息の診断が難しい場合や他疾患との鑑別が必要なときには、専門病院へのご紹介も可能です。
治療
治療の中心は吸入ステロイド薬(ICS)と長時間作用型気管支拡張薬(LABA)の配合吸入薬です。症状の強さに応じて薬剤を選びます。発作時には短時間作用型薬(SABA)を頓用しますが、SABA単剤の常用は推奨されなくなってきており、ICSの併用、またはICS/LABAによる頓用治療が注目されています。アレルゲン対策や禁煙も重要な治療の一部です。症状が続く場合や重症が疑われる場合には、専門医と連携し、生物学的製剤などの追加治療を検討します。適切な治療を続けることで、多くの方が発作のない生活を過ごすことが可能です。しかし、高齢者や重症例では注意が必要で、日本では今も年間約1,000人が喘息で亡くなっています。吸入薬の継続、禁煙、合併症の管理が予後を大きく左右します。当院では、日常生活に合った無理のない治療を一緒に考えてまいります。
長引く咳の原因となる疾患
咳が長く続く背景には、風邪以外のさまざまな病気が隠れていることがあります。当院では、問診や検査を通じて原因を見極め、適切な診断と治療を行っています。なお、肺がんや結核といった重篤な疾患については、専門的な検査や治療が必要になるため、当院では診療の対象としていません。これらの可能性が否定できない場合には、連携する専門医療機関をご紹介いたします。ここでは、当院でよくみられる「長引く咳」の原因疾患についてご紹介します。
感染後咳嗽(かんせんごがいそう)
 呼吸器の感染症が治ったあとに、咳だけが長く続くことがあります。このような状態を「感染後咳嗽(かんせんごがいそう)」と呼び、長引く咳の原因として比較的よくみられる病気です。多くは感冒に続いて起こり、咳だけが3〜8週間にわたって持続するのが特徴です。
呼吸器の感染症が治ったあとに、咳だけが長く続くことがあります。このような状態を「感染後咳嗽(かんせんごがいそう)」と呼び、長引く咳の原因として比較的よくみられる病気です。多くは感冒に続いて起こり、咳だけが3〜8週間にわたって持続するのが特徴です。
症状と経過
感染後咳嗽では、発熱や鼻水などの風邪症状はすでに改善している一方で、咳だけが長引くのが特徴です。咳は乾いた咳であることが多く、会話中、冷気を吸ったとき、運動後などの軽い刺激で出やすくなります。咳が続くことで気道がさらに刺激され、悪循環となることもあります。通常は少しずつ軽快していきますが、夜間や明け方に強く出ることもあり、睡眠や日常生活に支障をきたすことがあります。
診断
感染後咳嗽は、以下のような項目を満たす場合に疑われます。必要に応じて血液検査や胸部レントゲン検査を行い、肺炎などの他の咳の原因となる疾患を除外したうえで、総合的に診断します。
- 咳の前に風邪や肺炎などの感染症があった
- 咳が3〜8週間続いており、徐々に軽快傾向にある
- 胸部レントゲンに明らかな異常がない(肺炎、腫瘍、結核などの除外)
- 喘鳴や息苦しさ、胸やけなどの逆流症状、咳を引き起こす薬(ACE阻害薬など)の使用歴がない
治療
感染後咳嗽は、多くの場合、時間の経過とともに自然に軽快する良性の経過をたどります。ただし、咳がつらくて眠れない、日常生活に支障があるといった場合には、咳をやわらげる薬(鎮咳薬)、抗アレルギー薬、気管支拡張薬、漢方薬などを組み合わせて対応します。治療効果は通常2週間程度で現れ、改善が不十分な場合はさらに2週間程度継続します。それでも改善がみられない場合は必要に応じて専門病院へのご紹介を行います。なお、感染後咳嗽では感染症そのものはすでに治っており、他人にうつることはありません。咳だけが残っている状態ですので、ご安心ください。
咳喘息
 咳喘息とは、喘鳴(ぜんめい)や息苦しさを伴わずに、乾いた咳(乾性咳嗽)だけが長く続く病気です。風邪のあとに発症することが多く、はじめは感染後咳嗽と区別がつきにくい場合もありますが、8週間以上咳が続き、吸入ステロイド薬がよく効くのが特徴です。症状は一見軽く見えることもありますが、適切に治療しないと将来的に気管支喘息へ移行する可能性があるため、早めの対応が大切です。
咳喘息とは、喘鳴(ぜんめい)や息苦しさを伴わずに、乾いた咳(乾性咳嗽)だけが長く続く病気です。風邪のあとに発症することが多く、はじめは感染後咳嗽と区別がつきにくい場合もありますが、8週間以上咳が続き、吸入ステロイド薬がよく効くのが特徴です。症状は一見軽く見えることもありますが、適切に治療しないと将来的に気管支喘息へ移行する可能性があるため、早めの対応が大切です。
症状と経過
咳喘息では、咳が8週間以上持続し、乾いた咳が続くことが特徴です。咳は乾いた咳で、会話・運動・冷気などの軽い刺激で誘発されやすく、特に夜間や明け方に強く出る傾向があります。発作的に咳き込んだり、眠れない・胸がムズムズするといった違和感を伴うこともあります。一方で、喘鳴や息苦しさは見られません。咳だけのため「風邪の治りかけ」と思われがちですが、治療が遅れると気管支喘息に進展するリスクがあります。
診断
咳喘息は、以下のような項目を満たす場合に疑われます。必要に応じて血液検査や胸部レントゲン検査を行い、肺炎などの他の咳の原因となる疾患を除外したうえで、総合的に診断します。
- 咳が8週間以上続いている
- 咳は乾いた咳で、喘鳴や息苦しさを伴わない
- 胸部レントゲンに明らかな異常がない(肺炎、腫瘍、結核などの除外)
- 吸入薬や気管支拡張薬で咳が改善する
治療
治療の中心は、吸入ステロイド薬(ICS)による気道の炎症抑制です。咳が改善した後も再発予防のために3か月以上の継続使用が推奨されます。必要に応じて、咳をやわらげる薬(鎮咳薬)、抗アレルギー薬、気管支拡張薬、漢方薬などの薬を組み合わせて対応します。治療効果は2〜4週間程度で現れることが多く、改善があればそのまま継続します。咳が治まっても、自己判断で治療を中断せず、医師の指示のもとで続けることが大切です。改善がみられない場合は必要に応じて専門病院へのご紹介を行います。
アトピー咳嗽
 アトピー咳嗽とは、アレルギー反応によって喉の粘膜が炎症を起こし、乾いた咳(乾性咳嗽)だけが長く続く病気です。花粉やハウスダストなどのアレルゲンに反応して咳が出ることが多く、喉のイガイガ感を伴うのが特徴です。喘鳴や息苦しさはなく、気管支拡張薬が効かないことも特徴の一つです。一般的に気管支喘息へ進行することはほとんどありませんが、慢性的に繰り返すことがあるため、適切な診断と治療が大切です。
アトピー咳嗽とは、アレルギー反応によって喉の粘膜が炎症を起こし、乾いた咳(乾性咳嗽)だけが長く続く病気です。花粉やハウスダストなどのアレルゲンに反応して咳が出ることが多く、喉のイガイガ感を伴うのが特徴です。喘鳴や息苦しさはなく、気管支拡張薬が効かないことも特徴の一つです。一般的に気管支喘息へ進行することはほとんどありませんが、慢性的に繰り返すことがあるため、適切な診断と治療が大切です。
症状と経過
アトピー咳嗽では、乾いた咳が3週間以上持続するのが特徴です。咳は昼間に多く、アレルゲン(花粉、ダニ、カビなど)への曝露により悪化する傾向があります。喉のイガイガ感や違和感を伴うことが多く、冷気や会話などでも咳が誘発されることがあります。夜間は比較的落ち着くことが多く、喘鳴や息苦しさはみられません。
診断
アトピー咳嗽は、以下のような項目を満たす場合に疑われます。必要に応じて血液検査や胸部レントゲン検査を行い、肺炎などの他の咳の原因となる疾患を除外したうえで、総合的に診断します。
- 咳が3週間以上続いている
- 咳は乾いた咳で、喘鳴や息苦しさを伴わない
- 胸部レントゲンに明らかな異常がない(肺炎、腫瘍、結核などの除外)
- 血液検査でアレルギーの指標(IgE高値、好酸球増加など)が認められる
- 気管支拡張薬が無効である
- 抗ヒスタミン薬や吸入ステロイド薬で咳が改善する
治療
治療の基本は、抗ヒスタミン薬(第二世代)によるアレルギーのコントロールです。症状の程度に応じて、吸入ステロイド薬や漢方薬を併用することもあります。とくにアレルギー性鼻炎を伴う場合や、喉の乾燥感が強い場合には、漢方薬が有効なことがあります。治療効果は通常2〜4週間で現れ、改善があればそのまま継続します。症状が改善した後は、医師の指示に従って薬を徐々に減量・中止していきます。アレルゲンにさらされる季節や環境では再発しやすいため、必要に応じて予防的な治療(事前の内服)を行うこともあります。改善がみられない場合には、必要に応じて専門病院へのご紹介を行います。
胃食道逆流症関連咳嗽
 胃食道逆流症関連咳嗽とは、胃の内容物が食道や喉の奥にまで逆流し、それが刺激となって咳が続く病気です。長引く咳の原因のひとつであり、胸やけや呑酸(どんさん:酸っぱい液が上がる感じ)を伴う方に多く見られますが、咳だけが目立つことも少なくありません。胃酸以外の逆流や食道の動きの異常などが関係している場合もあり、診断が難しいこともあります。咳がなかなか改善しないときは、胃食道逆流症関連咳嗽の可能性も考慮することが大切です。
胃食道逆流症関連咳嗽とは、胃の内容物が食道や喉の奥にまで逆流し、それが刺激となって咳が続く病気です。長引く咳の原因のひとつであり、胸やけや呑酸(どんさん:酸っぱい液が上がる感じ)を伴う方に多く見られますが、咳だけが目立つことも少なくありません。胃酸以外の逆流や食道の動きの異常などが関係している場合もあり、診断が難しいこともあります。咳がなかなか改善しないときは、胃食道逆流症関連咳嗽の可能性も考慮することが大切です。
症状と経過
胃食道逆流症関連咳嗽では、乾いた咳が8週間以上続くことが多く、食後、会話中、横になったとき、または日中に咳が悪化しやすいという特徴があります。咳以外に、胸やけ、呑酸、喉の違和感、声のかすれ、咽喉頭部のつかえ感などを伴うこともありますが、これらの症状がまったくない場合もあります。
診断
胃食道逆流症関連咳嗽は、以下のような項目を満たす場合に疑われます。必要に応じて胸部レントゲンや血液検査を行い、肺炎や咳喘息などの他の咳の原因となる疾患を除外したうえで、総合的に診断します。
- 咳が8週間以上続いている
- 食後や横になると咳が悪化する
- 胸やけや呑酸、喉の違和感を伴う、または過去に胃食道逆流症の診断歴がある
- 胸部レントゲンに明らかな異常がない(肺炎、腫瘍、結核などの除外)
- 胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)を一定期間使用すると咳が改善する(治療的診断)
治療
治療の基本は、胃酸の逆流を抑えることと、咳の悪循環を断つことです。まずはPPIによる薬物治療を2〜8週間程度行います。ただし、食道症状よりも咳の改善には時間がかかることが多く、効果が現れるまでに2〜3か月かかる場合もあります。治療効果が不十分な場合には、PPIの増量や1日2回の分割投与を行うこともあります。また、消化管の動きを整える薬(消化管運動機能改善薬)を併用することもあります。さらに、食後すぐに横にならない、就寝時に頭を高くして寝る、脂っこい食事を控える、過食・飲酒・喫煙を避けるなど、生活習慣の見直しも治療において非常に重要です。改善があればそのまま継続し、症状が治まった後は医師の指示のもとで薬の調整を行い、再発予防を図ります。効果が不十分な場合や、消化器症状が強い場合には、専門病院をご紹介することがあります。
薬剤性咳嗽
 薬剤性咳嗽とは、特定の薬を内服したことが原因で咳が続く状態です。風邪やアレルギーなどの明らかな原因がないのに咳が長引く場合、薬の副作用が関与している可能性があります。とくに高血圧の治療薬である「ACE阻害薬(エースそがいやく)」による咳が代表的です。薬が原因と考えられる場合には、原因薬剤を中止・変更することで咳が改善する可能性があります。
薬剤性咳嗽とは、特定の薬を内服したことが原因で咳が続く状態です。風邪やアレルギーなどの明らかな原因がないのに咳が長引く場合、薬の副作用が関与している可能性があります。とくに高血圧の治療薬である「ACE阻害薬(エースそがいやく)」による咳が代表的です。薬が原因と考えられる場合には、原因薬剤を中止・変更することで咳が改善する可能性があります。
症状と経過
薬剤性咳嗽では、乾いた咳が持続するのが特徴です。薬を飲み始めて数日から数か月以内に咳が出現することが多く、夜間や会話中、横になったときなどに悪化することがあります。発熱や痰はほとんどなく、その他の呼吸器症状を伴わないことが一般的です。
診断
薬剤性咳嗽は、以下のような項目を満たす場合に疑われます。必要に応じて胸部レントゲンや血液検査を行い、肺炎や咳喘息などの他の咳の原因となる疾患を除外したうえで、総合的に診断します。ACE阻害薬以外にも、β遮断薬、痛み止め、抗がん薬、一部の抗生物質などで咳が出ることもあり、薬剤歴の詳細な確認が不可欠です。
- 咳が8週間以上続いている
- 咳は乾いた咳で、その他の異常所見が乏しい
- 胸部レントゲンに明らかな異常がない(肺炎、腫瘍、結核などの除外)
- 発症前後で新たに薬剤(特にACE阻害薬など)の使用を開始している
- 考えられる薬剤を中止・変更した後に咳が改善する
治療
治療の基本は、原因と考えられる薬剤の中止または他の薬への変更です。中止後、早ければ数日〜1週間、遅くても4週間程度で咳が自然に改善していくことが多いです。咳が強く生活に支障をきたしている場合には、一時的に咳をやわらげる薬や漢方薬を併用することもあります。咳の改善がみられた後は、もとの薬の再開は避け、代替薬での継続治療を検討します。原因薬剤の見極めが難しい場合や、複数の薬を併用している場合には、必要に応じて専門病院へのご紹介を行います。
後鼻漏症候群
後鼻漏症候群とは、鼻水が鼻の奥から喉のほうに垂れ落ちることによって、喉や気道が刺激されて咳が続く病気です。長引く咳の原因としては咳喘息に次いで多く、全体の2〜3割を占めるとされています。背景にはアレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎があることが多く、鼻づまりや鼻水などの不調を伴うのが特徴です。適切な治療によって咳が改善することが多いため、早めの対応が大切です。
症状と経過
後鼻漏症候群では、湿った咳(湿性咳嗽)が3週間以上続くのが特徴です。夜間から早朝にかけて咳が悪化しやすく、起床時に痰や咳払いが多いことがあります。また、喉の違和感や、鼻水が喉に垂れてくるような感覚(後鼻漏感)を伴うことが多く、鼻づまりやくしゃみ、鼻水などの鼻症状を合併していることもあります。感冒のあとに症状が悪化する場合は、副鼻腔炎が関与していることもあります。
診断
 後鼻漏症候群は、以下のような項目を満たす場合に疑われます。必要に応じて胸部レントゲンや血液検査を行い、肺炎や咳喘息などの他の咳の原因となる疾患を除外したうえで、総合的に診断します。
後鼻漏症候群は、以下のような項目を満たす場合に疑われます。必要に応じて胸部レントゲンや血液検査を行い、肺炎や咳喘息などの他の咳の原因となる疾患を除外したうえで、総合的に診断します。
- 湿った咳が3週間以上続いている
- 夜間〜早朝に咳が悪化し、起床時に咳払い・痰が多い
- 喉の違和感や後鼻漏感がある
- 鼻づまり、鼻水、くしゃみなどの鼻症状を伴う
- 胸部レントゲンに明らかな異常がない(肺炎、腫瘍、結核などの除外)
- 鼻炎、副鼻腔炎への治療により咳が改善する(治療的診断)
治療
治療は、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎など、原因となっている鼻の状態に応じて行います。通常は2週間程度で効果を判定し、改善があればそのまま継続します。副鼻腔炎が関与している場合は、4週間以上の継続治療が基本となります。症状の改善がみられない場合や、手術が必要な慢性副鼻腔炎が疑われる場合には、必要に応じて専門病院へのご紹介を行います。
心因性咳嗽
 心因性咳嗽とは、身体に明らかな異常がないにもかかわらず、心理的なストレスや緊張などを背景に咳が続く病気です。咳は乾いた咳であることが多く、検査や治療に反応しにくい傾向があります。夜間や睡眠中には咳が出ないことが多く、日中にだけ症状が目立つという特徴があります。咳を繰り返すことが癖のようになっているケースもあり、心因性咳嗽は“習慣性咳嗽”とも呼ばれます。
心因性咳嗽とは、身体に明らかな異常がないにもかかわらず、心理的なストレスや緊張などを背景に咳が続く病気です。咳は乾いた咳であることが多く、検査や治療に反応しにくい傾向があります。夜間や睡眠中には咳が出ないことが多く、日中にだけ症状が目立つという特徴があります。咳を繰り返すことが癖のようになっているケースもあり、心因性咳嗽は“習慣性咳嗽”とも呼ばれます。
症状と経過
心因性咳嗽では、乾いた咳が3週間以上持続します。会話中や緊張時に咳が出やすく、日中に目立つ一方で、夜間や睡眠中は咳がほとんど出ないことが多いです。咳以外の症状はなく、発熱や痰、息苦しさ、喘鳴は見られません。学校や職場などの人間関係、家庭内の不安や過度な緊張など、心理的なストレスが引き金となっていることが多く、咳がその緊張を和らげる役割をしていることもあります。
診断
心因性咳嗽は、以下のような項目を満たす場合に疑われます。必要に応じて胸部レントゲンや血液検査を行い、肺炎や咳喘息などの他の咳の原因となる疾患を除外したうえで、総合的に診断します。
- 乾いた咳が3週間以上続いている
- 夜間や睡眠中には咳が出ない
- 胸部レントゲンや診察所見に異常がない
- 喘鳴や息苦しさがない
- 吸入薬、抗アレルギー薬、胃酸抑制薬などが無効である
- 心理的なストレスや生活上の不安を背景に持っている
診断は除外的に行われることが多く、他の病気の可能性がないことを慎重に確認したうえで、心因性の関与を疑います。
治療
治療の基本は、十分な説明と心理的なサポートです。「器質的な異常がないこと」「命に関わるものではないこと」「多くは時間とともに改善すること」を丁寧に説明することで、患者さんの不安を和らげることができます。原因と考えられるストレスへの対応を図りながら、必要に応じて咳をやわらげる薬や不安を抑える薬、漢方薬などを短期間・最小限に使用することがあります。治療を継続しても症状が改善しない場合や、明らかな心理的要因が強く疑われる場合には、心療内科などへのご紹介を検討します。