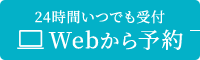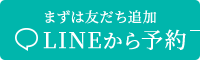生活習慣病
 生活習慣病とは、食事・運動・喫煙・飲酒・睡眠など、日々の生活習慣が発症や進行に深く関わる病気の総称です。代表的なものに、高血圧、脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症があります。これらは自覚症状がほとんどないまま進行し、放置すると血管の壁を傷つけ、動脈硬化が進行します。その結果、心臓・脳・腎臓などの臓器の機能を損ない、動脈硬化性疾患とも呼ばれる様々な合併症につながります。生活習慣が主な原因ですが、実際には遺伝的な要因や加齢、環境要因も関与することもわかっています。このことを踏まえて、近年、感染症以外の慢性的な病気の総称として非感染性疾患(NCDs)と言う呼び方が広まってきています。
生活習慣病とは、食事・運動・喫煙・飲酒・睡眠など、日々の生活習慣が発症や進行に深く関わる病気の総称です。代表的なものに、高血圧、脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症があります。これらは自覚症状がほとんどないまま進行し、放置すると血管の壁を傷つけ、動脈硬化が進行します。その結果、心臓・脳・腎臓などの臓器の機能を損ない、動脈硬化性疾患とも呼ばれる様々な合併症につながります。生活習慣が主な原因ですが、実際には遺伝的な要因や加齢、環境要因も関与することもわかっています。このことを踏まえて、近年、感染症以外の慢性的な病気の総称として非感染性疾患(NCDs)と言う呼び方が広まってきています。
内臓脂肪と生活習慣病
 お腹の奥にたまる内臓脂肪は、体の中で炎症を引き起こし、糖や脂質の処理に影響を与えます。その結果、血糖・血圧・脂質・尿酸などが高くなりやすく、生活習慣病の発症につながります。内臓脂肪の量は腹囲と深く関連しており、この点に注目した概念が「メタボリックシンドローム」です。
お腹の奥にたまる内臓脂肪は、体の中で炎症を引き起こし、糖や脂質の処理に影響を与えます。その結果、血糖・血圧・脂質・尿酸などが高くなりやすく、生活習慣病の発症につながります。内臓脂肪の量は腹囲と深く関連しており、この点に注目した概念が「メタボリックシンドローム」です。
動脈硬化と動脈硬化性疾患
生活習慣病を放置して血管が傷つくと、体は修復しようとして炎症を起こす物質を出します。これが長く続くと、コレステロールとともに傷ついた部分にたまり、自覚症状がないまま進行し、血管を硬く狭くしてしまいます。このことを動脈硬化と呼びます。血管年齢と言った方がわかりやすいかもれません。進行すると、心筋梗塞・脳梗塞・足の血流障害・腎不全など、生活の質や生命に関わる様々な動脈硬化性疾患につながります。複数の生活習慣病が重なると、動脈硬化はさらに加速します。他、喫煙も動脈硬化を強く促す因子として知られており、その観点からも全ての人に禁煙は強く勧められます。
治療の目的
生活習慣病の治療は、単に血圧や血糖、コレステロール、尿酸の数値を下げることが目的ではありません。血管を守り、生活習慣病が進んだ結果として起こる生活の質や生命に関わる動脈硬化性疾患を防ぐことが最大の目的です。実際に、動脈硬化性疾患は日本人の死亡原因の約22%を占めています。当院では、生活習慣の改善と薬物療法を組み合わせ、患者さん一人ひとりのリスクに応じた診療を行っています。
生活習慣病についてよくある質問
生活習慣病とはどんな病気ですか?
食事、運動、喫煙、飲酒、睡眠といった日々の生活習慣が原因となって発症・進行する病気の総称です。高血圧、脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症などが代表例で、いずれも放置すると動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞など重大な病気を引き起こすおそれがあります。
生活習慣病は遺伝とは関係ないのですか?
主な原因は生活習慣ですが、遺伝的な体質や加齢、環境なども関与します。そのため、家族に生活習慣病のある方は、より注意が必要です。
内臓脂肪が多いと、なぜ病気につながるのですか?
内臓脂肪は炎症を起こす物質を分泌し、血糖や脂質の代謝を乱します。その結果、高血圧・糖尿病・脂質異常症などを引き起こしやすくなり、動脈硬化のリスクも高まります。
メタボリックシンドロームと生活習慣病はどう違うのですか?
メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積に加え、高血圧・高血糖・脂質異常のいずれかが複数ある状態を指します。生活習慣病の危険な組み合わせと考えられており、動脈硬化のリスクがより高くなります。
動脈硬化は何がいけないのですか?
動脈硬化は血管が硬く狭くなり、血流が悪くなる状態です。進行すると心筋梗塞、脳梗塞、腎不全などの命に関わる病気につながるため、早期の予防・治療が大切です。
治療はどこまで必要ですか?薬はずっと飲み続けるのですか?
生活習慣病の治療の目的は、血圧や血糖の数字を下げることではなく、将来の重い病気を防ぐことです。必要に応じて、生活習慣の改善とともに薬の継続が勧められますが、状態が安定すれば薬を減らすことも可能です。医師と相談して適切な管理を続けましょう。
たばこを吸っていなくても動脈硬化になりますか?
 はい。喫煙は動脈硬化を強く進めますが、吸っていなくても生活習慣病があると動脈硬化は進行します。逆に、喫煙習慣がある方はさらにリスクが高くなるため、禁煙が強く推奨されます。
はい。喫煙は動脈硬化を強く進めますが、吸っていなくても生活習慣病があると動脈硬化は進行します。逆に、喫煙習慣がある方はさらにリスクが高くなるため、禁煙が強く推奨されます。
生活習慣病は自覚症状がないのですか?
多くの場合、自覚症状がないまま進行します。健康診断で数値の異常を指摘されて初めて気づく方も多く、定期的な検査と早めの対策が重要です。
高血圧症
 高血圧症とは慢性的に高血圧が続く状態です。我が国の高血圧の患者数は4300万人と推定され、そのうち、自らの高血圧を認識していない人は1400万人、認識しているが治療を受けていない人は450万人とされています。
高血圧症とは慢性的に高血圧が続く状態です。我が国の高血圧の患者数は4300万人と推定され、そのうち、自らの高血圧を認識していない人は1400万人、認識しているが治療を受けていない人は450万人とされています。
高血圧症の診断
高血圧とは血圧が正常範囲よりも高い状態です。たまたま図った血圧が高くても高血圧症とは言い切れません。高血圧症とは慢性的に高血圧が続く状態です。
高血圧とは
血圧とは、心臓が血液を全身に送り出すときに、血管の内側にかかる圧力のことです。この血圧が高くなる状態を高血圧と言います。高血圧の基準を以下に示します。血圧を測定する状況に応じて高血圧の基準は変わってきます。
- 診察室血圧:140/90 mmHg以上
- 家庭血圧:135/85 mmHg以上
高血圧症の診断
少なくとも2回以上の異なる機会で高血圧を認める場合に高血圧症と診断されます。診察室血圧と家庭血圧で差がある場合には家庭血圧が優先されます。家庭血圧の方が再現性が高く、高血圧による臓器障害や死亡と深く関係するからです。
高血圧症の治療の目的
高血圧をそのままにしておくと、脳や心臓などの血管に病気が起こりやすくなります。治療の目的は、こうした病気を予防し、再発を防ぎ、命に関わるリスクを減らすことです。また、健康を守り、安心して日常生活を送れるようにすることも大切な目的です。
高血圧症の治療の対象者
血圧120/80 mmHgを超えると、血圧が高くなるほどに脳の血管の病気をはじめとして、様々な病気や死亡のリスクが高まることがわかっています。そのため、この段階から(薬物療法は不要ですが)生活習慣の見直しを始めることが大切です。
治療の血圧目標値
患者さんの年齢や体の状態により血圧の目標値が変わります。
|
|
|
|
日常生活を自立して送れている方 |
130/80 mmHg未満 |
124/75 mmHg未満 |
|
65才以上で身体が弱っている方 |
身体が弱っている方身体の状態に応じてより収縮期血圧 140-160 mmHg未満で管理する |
|
高血圧の治療
高血圧の治療は、人によって少しずつ方針が変わります。基本となるのは、まず生活習慣を整えることです。ただし、血圧がとても高い場合(180/110 mmHg以上)、または糖尿病・たんぱく尿・心房細動がある方、過去に脳卒中(脳出血や脳梗塞)を起こしたことがある方では、すぐに薬を使った治療を始める必要があります。
生活習慣の改善
高血圧の最も関連する生活習慣は塩分の過剰摂取です。そのほか、さまざまな生活習慣が関与することが分かっています。
塩分制限
塩分摂取の血圧上昇および減塩と血圧低下との関連が示されています。塩分は6 g/日未満に制限することが推奨されます。日本人は昔から味噌汁や漬物、醤油など塩分を多く含む食品を日常的に食べてきました。そのため食文化として塩分摂取が習慣化しており、気づかないうちに多く取りやすいのが特徴です。食品を選ぶ際には栄養成分表示を確認することが大事です。
カリウム(K)の摂取
K摂取不足の血圧上昇およびK摂取の血圧低下との関連が示されています。しかしながら、Kをたくさん摂ろうとすると塩分の摂取量が増えてしまうことが多いです。減塩しつつKを摂取するためには、野菜や果物、低脂肪牛乳や乳製品、緑茶、コーヒーなどを組わせて摂取することが大事です。
その他
適正体重の維持、定期的な有酸素運動、飲酒を控えること、禁煙が推奨されます。
薬物療法
生活習慣の改善だけでは血圧が十分に下がらないときには、薬による治療が必要になります。血圧を下げる薬にはいくつか種類があり、体の状態や持っている病気に応じて選ばれます。一方で、治療の一番の目標である脳の血管の病気を防ぐためには、どの薬を使うかよりも「しっかり血圧を下げること」そのものがとても大切です。
高血圧症についてよくある質問
血圧が少し高いだけでも治療が必要ですか?
血圧が120/80 mmHgを超えると、将来の脳や心臓の病気のリスクが徐々に高まることがわかっています。すぐに薬が必要なわけではありませんが、生活習慣の見直しは早めに始めることが大切です。
家庭で測った血圧が高かったのですが、病院で正常なら問題ありませんか?
家庭血圧のほうが再現性が高く、将来の病気のリスクともより関係しているとされています。診察室血圧と異なる場合は、家庭血圧を優先して判断します。
病院で測ると血圧が高いのですが、家で正常なら問題ありませんか?
診察時に緊張して血圧が一時的に上がる「白衣高血圧」は珍しくありません。家庭血圧が安定していれば、すぐに薬を始める必要はないことも多いですが、白衣高血圧の方も将来的に高血圧になるリスクがあるため、定期的な家庭血圧の測定と生活習慣の改善が重要です。
血圧は何回測って高ければ「高血圧症」と診断されますか?
原則として、別々の機会に2回以上、高血圧の基準を超える場合に「高血圧症」と診断されます。一時的な上昇では判断しません。
血圧は何mmHg以上が高血圧になるのですか?
診察室での血圧:140/90 mmHg以上、家庭での血圧:135/85 mmHg以上が高血圧とされる基準です。診察室での血圧と家庭での血圧が異なる場合には、家庭での血圧を優先して判断します。
薬を使うのはどんな場合ですか?
生活習慣の改善だけでは十分に血圧が下がらない場合や、血圧が非常に高い場合(180/110 mmHg以上)、あるいは糖尿病・たんぱく尿・心房細動・脳卒中の既往がある方は、早期に薬を開始する必要があります。
血圧を下げる薬にはどんな種類がありますか?
血圧を下げる薬にはいくつかの種類があり、患者さんの体の状態や合併症に応じて使い分けます。高血圧の治療の主な目的は脳の血管の病気の予防にあります。そのためには、どの薬を使うかよりも、「しっかり血圧を下げること」自体が重要になります。
塩分はどれくらいまで減らす必要がありますか?
1日あたり6g未満が目標です。日本の食文化では塩分が多くなりがちなので、調味料や加工食品の栄養成分表示を確認することが大切です。
野菜や果物を食べると血圧が下がるのですか?
野菜や果物に含まれるカリウムは、塩分による血圧上昇を抑える働きがあります。減塩とあわせて摂取すると、より効果的です。
高血圧の治療を始めると一生薬を飲み続けなければいけませんか?
生活習慣を大きく改善し、血圧が安定すれば薬を減らしたり中止できる場合もあります。ただし、自己判断で薬をやめるのは危険です。必ず医師と相談してください。
65歳以上の場合、目標の血圧は変わりますか?
はい。ご高齢の方では状態に応じて、収縮期血圧140〜160 mmHg未満を目標とすることがあります。逆に血圧を下げすぎるとふらつきや転倒のリスクもあるため、注意が必要です。
スマートフォンで血圧を測っていますが、正確ですか?
最近はスマートフォンと連携した血圧計やアプリが増えており、家庭での記録や管理がしやすくなる点では非常に有用です。グラフ化や過去データの比較ができるのもメリットです。ただし、スマートフォン単体で測定する場合は、医療機器としての信頼性が不十分なことがあります。医療機器認証(管理医療機器)のある血圧計を使い、腕で測定するタイプを選びましょう。スマートフォンは記録と管理に優れたツールであり、正確な血圧計と組み合わせることで治療に役立つものになります。
糖尿病
 糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高い状態が続く病気です。血糖値が高いまま放置すると、神経や目、腎臓などの細かい血管が障害され、様々な合併症を引き起こすことが知られています。また、大きな血管にも影響を与え、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な病気のリスクも高まります。糖尿病の治療の目的は、血糖をただ下げることではなく、こうした合併症を防ぎ、健康寿命を延ばすことにあります。当院では、ガイドラインに準拠した医学的に妥当な治療方針のもと、患者さんの生活背景や価値観を大切にしながら、個別性の高い診療を行っています。
糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高い状態が続く病気です。血糖値が高いまま放置すると、神経や目、腎臓などの細かい血管が障害され、様々な合併症を引き起こすことが知られています。また、大きな血管にも影響を与え、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な病気のリスクも高まります。糖尿病の治療の目的は、血糖をただ下げることではなく、こうした合併症を防ぎ、健康寿命を延ばすことにあります。当院では、ガイドラインに準拠した医学的に妥当な治療方針のもと、患者さんの生活背景や価値観を大切にしながら、個別性の高い診療を行っています。
糖尿病の原因と分類
糖尿病は、その原因や発症のしくみによっていくつかのタイプに分類されます。なかでも代表的なのが「1型糖尿病」と「2型糖尿病」です。
1型糖尿病
自己免疫により膵臓のインスリン分泌細胞が破壊され、インスリンが出なくなる病気です。治療にはインスリン注射が必要になります。
2型糖尿病
遺伝的な体質に生活習慣(過食、運動不足、肥満など)が重なって発症します。糖尿病全体の90%以上を占め、特に中高年に多くみられます。糖尿病は「不摂生の病気」と誤解されがちですが、実際には遺伝的な体質が大きく関与する病気です。
糖尿病の診断と症状
糖尿病は、以下のいずれかで診断されます。
- 空腹時血糖値≧126 mg/dL
- 随時血糖値≧200 mg/dL
- HbA1c≧6.5%(上記いずれかと併せて)
高血糖がある程度進行しないと症状は出にくく、「のどの渇き」「頻尿」「体重減少」「だるさ」などが見られることがあります。ただし、これらの症状は血糖値が概ね250 mg/dLを超えるような高値にならないと目立ってこないとされており、実際には多くの糖尿病患者さんが自覚症状のないまま過ごしています。そのため、糖尿病は「沈黙の病気」とも呼ばれ、気づかないうちに進行し、合併症が出てから初めて診断されるケースも少なくありません。
糖尿病の治療の目標
糖尿病の治療の目的は、血糖値を正常に保つことだけでなく、合併症を防ぎ、健康的な生活を維持することにあります。そのため、患者さん一人ひとりの状態に応じて、血糖値の管理目標を設定することが大切です。糖尿病の治療の目標は合併症を未然に防ぐことですが、そのための血糖値の管理目標はHbA1c 7.0%未満とされています。当院ではこの目標を参考にしながら、患者さんの年齢や生活背景、体調などをふまえて、無理のない範囲で管理方針を決めていきます。血糖値だけにとらわれるのではなく、安心して日常生活を送ることができるよう、継続しやすい治療を心がけています。
糖尿病の治療方針
糖尿病の治療の基本は生活習慣の見直しです。血糖管理に加えて、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病も同時に管理することで、合併症の発症や進行を予防します。
食事療法
食事療法は糖尿病治療の基本であり、血糖値の安定や体重管理、合併症の予防において大きな役割を果たします。まず大切なのは、必要なカロリー量を把握し、それに見合った食事量を守ることです。食事内容としては、糖質・脂質・たんぱく質の三大栄養素を適切な割合でバランスよく摂取することが基本となります。極端な糖質制限や、過剰なたんぱく質の摂取は原則として推奨されません。また、1日3食を均等な配分で摂ることが望ましく、特に夕食に偏った食事は血糖の急上昇を招きやすいため注意が必要です。当院では、患者さんの生活背景や食の嗜好を考慮し、無理なく続けられる食事療法を個別に提案しています。
運動療法
運動療法は、特に2型糖尿病において、食事療法と並ぶ重要な治療手段です。運動には血糖値を下げる効果があるだけでなく、インスリンの効き目を改善したり、体重や内臓脂肪を減らしたりといった効果も期待できます。また、血圧や脂質の改善、ストレスの軽減などにも役立ちます。おすすめの運動は、ウォーキングや水中運動などの有酸素運動で、1回20〜30分、週に3〜5回を目安に継続するのが理想です。加えて、スクワットやかかと上げといった簡単な筋力トレーニングを取り入れると、より高い効果が得られます。通勤や買い物の際に階段を使うなど、日常生活の中で自然に体を動かす「ながら運動」も有効です。
薬物療法
食事療法や運動療法を行っても血糖のコントロールが不十分な場合には、薬物療法を追加します。糖尿病治療薬には、内服薬と注射薬があり、いずれも血糖値を下げる働きがあります。薬剤の種類は多岐にわたり、それぞれ作用の仕方や適した患者像が異なります。当院では、患者さんの血糖値の状態、年齢、腎機能、体重、合併症の有無、生活スタイルなどを総合的に判断し、それぞれの方に適した薬剤を選択しています。必要に応じて複数の薬剤を組み合わせながら、安全性と効果の両立を図り、継続しやすい治療を心がけています。
糖尿病についてよくある質問
糖尿病はどんな症状が出る病気ですか?
初期の糖尿病では症状がほとんどありませんが、血糖値が高くなってくると「のどの渇き」「尿の回数が増える」「体重が減る」「疲れやすい」といった症状が出てくることがあります。ただし、これらはかなり血糖が高くなった場合に見られるため、多くの方は気づかずに過ごしているのが実情です。
健診で「HbA1cが6.5%」と言われました。これは糖尿病ですか?
HbA1cが6.5%以上の場合、糖尿病の可能性があります。ただし、確定診断には血糖値の測定など他の基準と併せて評価する必要があります。当院では再検査を含めて、正確な診断と今後の対応を丁寧にご説明いたします。
糖尿病は遺伝しますか?
特に2型糖尿病は遺伝的な影響を強く受けることが知られており、親兄弟に2人以上糖尿病患者さんがいる場合には発症頻度は5倍に増加するという報告もあります。また、日本人は人種的に糖尿病を発症しやすいこともわかっています。糖尿病は生活習慣病と思われがちですが、そもそもの発症しやすさにかなりの個人差のある病気です。
糖尿病と診断されたら、すぐに薬を飲まないといけませんか?
必ずしもすぐに薬が必要になるわけではありません。多くの場合、まずは食事と運動など生活習慣の見直しから始めます。それでも血糖値が改善しない場合に、体の状態に合わせた薬物療法を検討します。
インスリン注射は2型糖尿病でも必要ですか?
2型糖尿病でも、血糖値が非常に高い場合や膵臓のインスリンをだす能力が落ちている場合には、インスリン注射が必要になることがあります。ただし、すべての方に必要というわけではなく、内服薬で十分コントロールできるケースも多くあります。
糖尿病の食事療法は厳しい制限が必要ですか?
極端な制限ではなく、カロリーや栄養バランスを整えることが大切です。特定の食品を完全に禁止するのではなく、量や食べ方の工夫で血糖を安定させることが可能です。当院では患者さんのライフスタイルに合わせて無理のない提案を行っています。
運動が大事と聞きましたが、どんな運動をすれば良いですか?
ウォーキングなどの軽めの有酸素運動がおすすめです。1回20〜30分、週に3〜5回を目標にすると効果が期待できます。筋力トレーニングや、通勤・買い物時の階段利用なども有効です。体調に合わせて無理のない範囲で続けることが大切です。
HbA1cはどれくらいを目標にすればいいですか?
一般的な目標は HbA1c 7.0%未満ですが、年齢や合併症の有無、日常生活への影響などをふまえて個別に設定することが推奨されています。当院では患者さん一人ひとりの状況に合わせた無理のない目標を一緒に考えます。
糖尿病は治りますか?
1型糖尿病は生涯にわたるインスリン治療が必要になります。2型糖尿病では生活習慣の改善により、薬物療法なしでも血糖値を正常に保つことは可能です。ただし、これは治ったわけではありません。生活習慣が乱れると血糖値は再度、悪化してしまいます。「治す」ことよりも、「良好なコントロールを続ける」ことが目標となります。
糖尿病になると合併症は必ず起こりますか?
適切に治療を続けて血糖を良好に管理すれば、合併症の発症や進行を防ぐことができます。重要なのは「早期発見」と「継続的な治療」です。当院では、合併症を防ぐことを最重要とし、定期的な検査ときめ細かな治療方針を提供しています。
脂質異常症
 血液中の脂(あぶら)のバランスが崩れた状態を「脂質異常症」といいます。「悪玉」コレステロール(LDL-C)が高い、「善玉」コレステロール(HDL-C)が低い、中性脂肪が高い、これらのいずれかを認める場合に診断されます。以前は「高脂血症」と呼ばれていましたが、HDL-Cの低さも問題となるため、2007年に「脂質異常症」という名前に変わりました。
血液中の脂(あぶら)のバランスが崩れた状態を「脂質異常症」といいます。「悪玉」コレステロール(LDL-C)が高い、「善玉」コレステロール(HDL-C)が低い、中性脂肪が高い、これらのいずれかを認める場合に診断されます。以前は「高脂血症」と呼ばれていましたが、HDL-Cの低さも問題となるため、2007年に「脂質異常症」という名前に変わりました。
脂質異常症の診断
以下のいずれかに当てはまる場合、脂質異常症と診断されます。
- 高LDLコレステロール血症:LDL-C 140 mg/dL以上
- 低HDLコレステロール血症:HDL-C 40 mg/dL未満
- 高トリグリセライド血症:
-トリグリセリド(中性脂肪)150 mg/dL以上(空腹時採血※)
-トリグリセリド(中性脂肪)175 mg/dL以上(随時採血※)
※空腹時:10時間以上食事をしていない状態
※随時:空腹時かどうかがはっきりしない状態
脂質異常症の管理目標値
脂質の値をコントロールして、動脈硬化の進行をゆるやかにし、動脈硬化性疾患を予防することが治療の目的です。患者さん一人ひとりの動脈硬化性疾患のリスクに応じて、管理目標が設定されます。過去に狭心症や脳梗塞を経験したことがある方、糖尿病・慢性腎臓病・末梢動脈疾患をお持ちの方は、より厳しい管理目標が設定されることがあります。LDL-C > 中性脂肪 > HDL-C の順に重要とされています。これまでの研究で、LDL-Cが最も動脈硬化との関係が明らかになっているためです。
脂質異常症の治療
治療の基本は生活習慣の改善,つまり食事療法と運動療法です。それでも管理目標値を達成できない場合には、薬による治療を行います。すでに冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞)や脳梗塞を経験された方やLDL-C 180 mg/dL以上ある場合は,生活習慣の改善と並行して、薬物療法を早めに始めることが検討されます。
脂質異常症の食事療法
- 食事量を適正に保つ(食べ過ぎ、飲み過ぎを避ける)
- 主食、主菜、副菜をそろえて、栄養バランスを整える
- 野菜、海藻、きのこ、大豆製品など、食物繊維を多く含む食品をしっかりとる
- 揚げ物や加工食品など、脂質の多い食品は控えめにする
LDLコレステロールを下げるための食事の工夫
- 飽和脂肪酸を減らす(脂身の多い肉、バター、ラード、加工肉などを控える)
- トランス脂肪酸を避ける(マーガリン、ショートニング、揚げ物、加工食品)
- コレステロールを多く含む食品(卵黄、レバー、乳製品など)を摂りすぎない
中性脂肪を下げるための食事の工夫
- 糖分の多い食品(甘い菓子、ジュース、清涼飲料水)を控える
- 精製された炭水化物(白米、パン、麺など)の摂りすぎを避ける
- 魚を積極的にとる(EPA、DHAは中性脂肪低下に有効)
- 果物は摂りすぎない(果糖の過剰摂取を避ける)
HDLコレステロールを上げるための食事の工夫
- 精製された炭水化物(白米、パン、麺など)の摂りすぎを避ける
- トランス脂肪酸を含む食品(マーガリン、ショートニング、揚げ物、加工食品)を減らす
- 魚やナッツ類など、不飽和脂肪酸を多く含む食品を適度にとる
運動療法
 運動療法は、脂質の代謝を改善し、動脈硬化性疾患の予防や治療に効果が期待できます。とくに有酸素運動を中心に、1日合計30分以上、週に3回以上(可能であれば毎日)、または週150分以上行うことが推奨されています。有酸素運動では、体が脂肪を優先的にエネルギーとして使うため、内臓脂肪が減少し、脂質異常の改善につながります。また、無酸素運動(筋トレなど)を取り入れることで筋肉量が増え、基礎代謝が高まり、脂質や体重のコントロールにも役立ちます。有酸素運動と無酸素運動をバランスよく組み合わせることで、より高い運動効果を得ることができます。
運動療法は、脂質の代謝を改善し、動脈硬化性疾患の予防や治療に効果が期待できます。とくに有酸素運動を中心に、1日合計30分以上、週に3回以上(可能であれば毎日)、または週150分以上行うことが推奨されています。有酸素運動では、体が脂肪を優先的にエネルギーとして使うため、内臓脂肪が減少し、脂質異常の改善につながります。また、無酸素運動(筋トレなど)を取り入れることで筋肉量が増え、基礎代謝が高まり、脂質や体重のコントロールにも役立ちます。有酸素運動と無酸素運動をバランスよく組み合わせることで、より高い運動効果を得ることができます。
薬物療法を検討する患者さん
次のような場合には、薬による治療(薬物療法)を検討します。
- 生活習慣を見直しても、脂質の管理目標を達成できない場合
※患者さんによって異なりますが、一般的には約3か月間、食事や運動などの生活習慣の改善で様子を見ることが多いです。 - LDLコレステロール(LDL-C)が180 mg/dL以上ある場合
- 冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞)、または脳梗塞などを過去に起こしたことがある場合
薬物療法について
 脂質異常症の治療では、まずHMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)という体内でのコレステロールの合成を抑える薬が第一選択となります。スタチンで十分な効果が得られない場合や、副作用により使用が難しい場合には、食事からのコレステロールの吸収を抑える「エゼチミブ」が使用されます。さらに、動脈硬化性疾患のリスクが高く、スタチンやエゼチミブでも治療目標に達しない場合には、「PCSK9阻害薬」という注射薬の使用を検討することがあります。基本的には生涯にわたる服用が必要になります。
脂質異常症の治療では、まずHMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)という体内でのコレステロールの合成を抑える薬が第一選択となります。スタチンで十分な効果が得られない場合や、副作用により使用が難しい場合には、食事からのコレステロールの吸収を抑える「エゼチミブ」が使用されます。さらに、動脈硬化性疾患のリスクが高く、スタチンやエゼチミブでも治療目標に達しない場合には、「PCSK9阻害薬」という注射薬の使用を検討することがあります。基本的には生涯にわたる服用が必要になります。
横紋筋融解症
スタチンの使用において、注意が必要な副作用として横紋筋融解症があります。これは筋肉が傷つき、筋肉痛やコーラ色の尿が現れる病気です。スタチン使用中の発症率はおよそ0.001%(10万人に1人)とされており、非常にまれです。この副作用は、症状のほかに血液検査や尿検査でも早期に発見することができます。当院では定期的にこれらの検査を行い、異常がないかをしっかりと確認しています。万が一、横紋筋融解症が疑われる場合には、ただちにスタチンを中止し、適切な対応が可能な専門医療機関へご紹介いたします。
閉経とLDLコレステロール(LDL-C)との関係について
女性ホルモンであるエストロゲンはLDL-Cを分解する働きを持っています。閉経後の女性は、エストロゲンの量が急激に低下するため、高LDL-C血症を発症しやすくなります。生活習慣とは異なる理由による高LDL-C血症であるため、食事療法や運動療法のみで改善することは難しく、薬物療法が必要になる患者さんが多いです。
脂質異常症についてよくある質問
健康診断で脂質が高いと言われましたが、放っておいても大丈夫ですか?
脂質異常症はほとんどの場合自覚症状がありません。しかし放置すると、動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な病気につながる可能性があります。早めに医療機関を受診し、生活習慣の見直しや必要な治療を始めることが大切です。
脂質異常症はどんな人がなりやすいですか?
以下のような生活習慣や体質がある方は脂質異常症になりやすいとされています。
- 食べすぎ、飲みすぎ、運動不足
- 肥満、特に内臓脂肪型肥満
- 喫煙や過度の飲酒
- 糖尿病や高血圧などの生活習慣病
- 家族に脂質異常症や心臓病の人がいる(遺伝的要因)
- 閉経後の女性
脂質異常症は何科を受診すればよいですか?
内科での受診が基本です。とくに生活習慣病の管理を行っている内科クリニックでは、診断から食事・運動指導、薬の調整まで一貫して対応できます。当院でも脂質異常症の診療に力を入れており、必要に応じて専門医療機関と連携して治療を行っています。
脂質異常症はどのように診断されますか?
血液検査によって診断され、以下のいずれかに当てはまると脂質異常症とされます。
- LDL-コレステロール:140 mg/dL以上
- HDL-コレステロール:40 mg/dL未満
- 中性脂肪:150 mg/dL以上(空腹時)または175 mg/dL以上(随時)
脂質異常症になると、どんな病気のリスクが高くなりますか?
脂質異常症を放置すると動脈硬化が進行し、以下のような重大な病気のリスクが高まります。
- 心筋梗塞、狭心症などの心臓病
- 脳梗塞などの脳血管障害
- 腎機能障害や末梢動脈疾患
など
治療の目的は何ですか?
単に数値を下げることではなく、動脈硬化の進行を抑えて命にかかわる病気を予防することが目的です。患者さんのリスクに応じて、LDLコレステロールを最重視しつつ、中性脂肪やHDL-コレステロールの改善も図ります。
どのような食事に気をつければよいですか?
 脂質異常症のタイプによって注意点は異なりますが、基本的なポイントは以下のとおりです。
脂質異常症のタイプによって注意点は異なりますが、基本的なポイントは以下のとおりです。
- 食べすぎ、飲みすぎを避ける
- 野菜、海藻、きのこ、大豆など食物繊維を多く含む食品をとる
- 揚げ物や加工食品など脂質の多い食品を控える
- 魚やナッツなどの良質な脂質を適度にとる
- 甘いお菓子やジュースを控える(中性脂肪の改善)
運動はどのくらいすればいいですか?
基本は有酸素運動を中心に週3回以上、1日30分以上行うことが推奨されます。たとえば、ウォーキング、ジョギング、自転車、水泳などです。可能であれば筋トレなどの無酸素運動も組み合わせるとより効果的です。
治療薬の副作用は心配ありませんか?
LDL-コレステロールを下げる代表的な薬としてスタチンがあります。スタチンの有名な副作用として横紋筋融解症という筋肉の障害です。発症率は非常に低く(10万人に1人程度)ですが、筋肉痛や濃い色の尿が出るなどの症状が現れることがあります。当院では定期的に血液・尿検査を行い、早期発見に努めています。
閉経後にコレステロールが上がるのはなぜですか?
女性ホルモン(エストロゲン)はLDL-Cを分解する働きがありますが、閉経後はこのホルモンが急激に減るため、LDL-Cが上がりやすくなります。そのため、生活習慣を整えても改善しにくく、薬の使用を検討することがよくあります。
高尿酸血症
 尿酸とは、体の代謝によって生じる老廃物の一種です。体の中で尿酸が作られすぎたり、うまく排出されなかったりすると、血液中の尿酸の量が増えてしまいます。血清尿酸値が7.0 mg/dLを超えると「高尿酸血症」と診断されます。この7.0 mg/dLという値は、尿酸が血液中に溶けていられる限界(=溶解度)を示しており、これを超えると尿酸は結晶化して関節や腎臓に沈着する可能性があります。
尿酸とは、体の代謝によって生じる老廃物の一種です。体の中で尿酸が作られすぎたり、うまく排出されなかったりすると、血液中の尿酸の量が増えてしまいます。血清尿酸値が7.0 mg/dLを超えると「高尿酸血症」と診断されます。この7.0 mg/dLという値は、尿酸が血液中に溶けていられる限界(=溶解度)を示しており、これを超えると尿酸は結晶化して関節や腎臓に沈着する可能性があります。
高尿酸血症が引き起こす主なリスク
尿酸が結晶化して関節に沈着して炎症を引き起こし、「痛風」の原因となります。また、結晶化していない尿酸自身も腎臓の組織や血管を傷害して「腎機能障害」や「動脈硬化」の原因になると考えられています。
高尿酸血症のタイプ(病型分類)
高尿酸血症は、尿酸の「排泄の低下」と「産生の増加」によって分類されます。現在、日本人では「尿酸排泄低下型」が約60%と最も多く、混合型が30%、産生過剰型が10%程度です。
原因
遺伝的要因に加えて、生活習慣の影響が重なることで発症します。
遺伝的要因
尿酸をうまく排出できない体質が遺伝することがあり、家族歴も重要な要素です。
生活習慣の影響
- プリン体を多く含む食品(肉類、魚卵、内臓類など)の摂取
- 果糖を多く含む清涼飲料や菓子類の過剰摂取
- アルコール(特にビール)摂取
- 過食や運動不足による肥満
高尿酸血症の管理目標値
血清尿酸値をコントロールして合併症を防ぐことが目的です。血清尿酸値の管理目標値は6.0 mg/dL未満です。この数値は、体内の尿酸結晶を消失させるために必要とされる基準です。
高尿酸血症の治療
治療の基本は生活習慣の改善,つまり食事療法と運動療法です。痛風などの合併症がある場合や尿酸値が高い場合には生活習慣の改善と並行して、薬物療法を早めに始めることが検討されます。
生活習慣の見直し
- 食事療法:適切なカロリー摂取、プリン体・果糖の制限、腎機能に応じた飲酒調整
- 運動療法:有酸素運動を中心に、継続的な活動を推奨
薬物療法の適応
- 痛風発作や痛風結節がある場合
- 高血圧や糖尿病などの動脈硬化性疾患や腎機能障害などの高尿酸血症の合併症があり、血清尿酸値が8.0 mg/dL以上ある場合
- 合併症がないが、血清尿酸値が9.0 mg/dL以上ある場合
薬物療法の実際
従来は高尿酸血症の病型や腎臓の機能の配慮した薬剤の選択が必要でした。近年では、病型や腎機能を気にせずに使用可能なフェブリクやトピロリックなどの薬剤が登場しています。当院ではその様な薬剤を中心に処方しています。
高尿酸血症と腎障害との関係
体内の尿酸の70%は腎臓から排泄されます。したがって、腎臓の機能が低下すると尿酸は排泄されなくなるために、高尿酸血症を発症しやすくなります。一方で高尿酸血症も尿酸自体が直接、腎臓に炎症を引き起こし慢性腎臓病の原因となることがわかっています。この様に高尿酸血症と腎機能障害は相互に関連しあう関係にあることがわかっています。
高尿酸血症についてよくある質問
高尿酸血症が続くとどんな病気になりますか?
代表的なのは「痛風(つうふう)」です。足の指などの関節に尿酸の結晶がたまって炎症を起こし、強い痛みを伴います。また、尿酸そのものが腎臓を傷つけて慢性腎臓病の原因になったり、動脈硬化を進めることもわかっています。
高尿酸血症になる原因は何ですか?
大きく分けて以下の2つの原因があります。
- 体質(遺伝的な要因)
生まれつき尿酸を排泄しにくい体質の方がいます。家族に高尿酸血症や痛風の方がいる場合は注意が必要です。 - 生活習慣の影響
プリン体を多く含む食品(肉類・魚卵・内臓など)や、果糖を多く含む清涼飲料・スイーツの摂りすぎ、アルコール(特に
ビール)の過剰摂取、肥満、運動不足などが尿酸値の上昇につながります。
特に日本人では「尿酸の排泄が悪いタイプ」が多いとされており、体質に加えて生活習慣が重なることで高尿酸血症が発症しやすくなります。
薬を飲まなくてもよい場合はありますか?
はい、あります。合併症がなく、尿酸値が7〜8 mg/dL程度で安定している場合には、薬を使わずに生活習慣の見直しだけで様子をみることがあります。ただし、以下のような場合には薬物治療が推奨されます。
- 痛風発作を起こしたことがある場合
- 尿酸値が9.0 mg/dL以上ある場合
- 高血圧や腎機能の低下など、合併症をともなう場合
治療の必要性は個人の状態によって異なるため、医師とよく相談することが大切です。
治療ではどんな薬が使われますか?
血液中の尿酸値を下げる薬を使用します。以前は、病型(尿酸の作られすぎか、出にくいか)や腎機能に応じて使い分けが必要でしたが、近年はどのタイプにも使いやすい薬(フェブリク、トピロリックなど)が登場しています。当院でもこうした薬剤を中心に処方しています。
食事で気をつけるべきことはありますか?
以下のような食品や飲料は控えめにしましょう
- プリン体が多い食品(レバー、魚卵、内臓など)
- 果糖を多く含む清涼飲料やスイーツ
- アルコール(特にビール)
また、食べすぎ・太りすぎを避け、適度な運動を取り入れることも重要です。
高尿酸血症と腎臓の病気は関係がありますか?
はい、深く関係しています。尿酸は約70%が腎臓から排泄されるため、腎臓が弱ると尿酸がたまりやすくなります。また逆に、尿酸が高いと腎臓にダメージを与え、慢性腎臓病を進行させる原因にもなります。腎機能を守るためにも、尿酸値の管理が大切です。
痛風
 高尿酸血症が長期間続くことで、血液中に溶けきれなくなった尿酸が析出・結晶化し、関節などに沈着して激しい炎症を引き起こす病気です。その影響で、ある日突然、「風が当たるだけでも痛い」と表現されるほどの強い痛みや腫れが現れます。
高尿酸血症が長期間続くことで、血液中に溶けきれなくなった尿酸が析出・結晶化し、関節などに沈着して激しい炎症を引き起こす病気です。その影響で、ある日突然、「風が当たるだけでも痛い」と表現されるほどの強い痛みや腫れが現れます。
症状
高尿酸血症のある方に、ある日突然、関節の激しい痛みや腫れを引き起こすのが「痛風発作」が特徴です。多くの場合、夜間から早朝にかけて発症します。発作は24時間以内にピークに達し、10日ほどで自然に軽快することが多いですが、繰り返す特徴があります。最も多い部位は、足の親指の付け根(第一中足趾関節)ですが、足首・膝・肘・手首・手指に起こることもあります。
初期は1か所の関節だけに起こる単関節炎として始まりますが、治療をせずに放置すると、発作の間隔が短くなり、複数の関節に広がったり、関節の変形を招くこともあります。これまで痛風は中高年の男性に多いとされてきましたが、近年は女性の患者さんも増加傾向にあります。
治療
痛風発作は、強い関節の痛みが10日程度続き、日常生活に支障をきたすことが多いため、原則として薬による治療が必要です。
治療薬はできるだけ早期に開始し、症状が軽快したら中止します。発作時の治療薬には以下のようなものがあります。
- コルヒチン:発作の始まりに内服することで、悪化を防ぎます。
- 鎮痛薬(NSAIDs):炎症や痛みを抑えます。
- ステロイド薬:NSAIDsが使えない場合や効果が不十分な場合に使用されることがあります。
これらの薬は、患者さんの症状や体調に応じて適切に使い分けます。
また、発作が起きていない時期の高尿酸血症の管理も非常に重要です。体内に沈着した尿酸の結晶を徐々に減らしていくために、尿酸値は6.0mg/dL未満を目標とし、関節の変形などの重症例では5.0mg/dL未満での管理が推奨されています。
痛風についてよくある質問
痛風発作はどのような前触れがありますか?
多くの場合、前触れなく突然発症しますが、まれに「違和感」「軽い痛み」などを感じることがあります。飲酒や食べすぎ、脱水などのあとに発作が起こりやすくなるため、これらのタイミングは注意が必要です。
痛風はどの関節に起こりますか?
最も多いのは足の親指の付け根(第一中足趾関節)ですが、足首・膝・肘・手首・指など、他の関節に起こることもあります。初期は1か所の関節に限局することが多いですが、放置すると複数の関節に広がることがあります。
痛風の発作は薬を飲まなくても自然に治りますか?
はい、多くの場合は10日ほどで自然に軽快します。ただし、強い痛みが続くため、日常生活に支障をきたすことが多く、痛みや炎症を和らげるために薬物治療が推奨されます。また、繰り返す可能性が高いため、根本的な管理も重要です。
どのような薬が使われますか?
発作時には、以下のような薬を使用します。
- コルヒチン:発作の始まりに使用し、悪化を防ぐ効果があります
- NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬):炎症と痛みを抑えます
- ステロイド:NSAIDsが使えない場合や効果が不十分な場合に用います
これらの薬は、患者さんの症状や体質に応じて使い分けられます。
発作がない時期も治療が必要ですか?
はい、痛風の根本的な原因である「高尿酸血症」を放置すると、再発を繰り返し、関節の変形や腎障害などにつながるおそれがあります。発作がない時期に尿酸値をしっかり管理することが、将来的な合併症予防につながります。
尿酸値はいくつを目標にすればよいですか?
一般的には6.0mg/dL未満を目標とします。関節の変形があるような重症の方では5.0mg/dL未満が推奨される場合もあります。目標値は個人の状態によって異なるため、医師と相談しながら治療方針を決めましょう。
痛風は男性だけの病気ですか?
かつては中高年男性に多い病気とされてきましたが、最近では生活習慣の変化により、女性の患者さんも増えてきています。特に閉経後の女性では尿酸値が上昇しやすくなるため、注意が必要です。
再発を防ぐために、日常生活で気をつけることはありますか?
はい、以下のような生活習慣の見直しが重要です
- 水分をしっかりとる(尿酸の排泄を促進)
- アルコール(特にビールや日本酒)の制限
- プリン体の多い食品(レバー・魚卵など)の摂取を控える
- 肥満の改善、適度な運動
医師と相談のうえ、無理のない範囲で生活改善を進めましょう。
脂肪肝
 脂肪肝とは、肝臓に脂肪が過剰にたまる状態です。症状はほとんどありませんが、放置すると進行して、治療困難な状態に陥り、肝硬変・肝がんに至ることがあります。このことから、早期診断と早期介入が重要と考えられています。
脂肪肝とは、肝臓に脂肪が過剰にたまる状態です。症状はほとんどありませんが、放置すると進行して、治療困難な状態に陥り、肝硬変・肝がんに至ることがあります。このことから、早期診断と早期介入が重要と考えられています。
脂肪肝の原因
 かつては「お酒の飲みすぎ」で起こる病気と考えられていましたが、実際にはお酒をほとんど飲まない人にも起こる脂肪肝(非アルコール性脂肪肝:NAFLD)が圧倒的に多いです。肥満人口の増加を背景に徐々にその割合は増加し、日本では健康診断を受ける人の約3人に1人が脂肪肝を指摘されています。
かつては「お酒の飲みすぎ」で起こる病気と考えられていましたが、実際にはお酒をほとんど飲まない人にも起こる脂肪肝(非アルコール性脂肪肝:NAFLD)が圧倒的に多いです。肥満人口の増加を背景に徐々にその割合は増加し、日本では健康診断を受ける人の約3人に1人が脂肪肝を指摘されています。
アルコール性脂肪肝
アルコール摂取による肝臓の脂肪の分解が抑制され、脂肪が蓄積します。初期段階であれば禁酒により劇的に改善しますが、飲酒を続けると炎症や線維化が進み、肝硬変へ進行することがあります。
非アルコール性脂肪肝(NAFLD)
飲酒歴がほとんどないにもかかわらず、肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積されてしまう脂肪肝のことです。原因としては肥満、内臓脂肪型肥満、糖尿病などの生活習慣病が大きく関わっていることがわかっています。
症状
末期になるまでは、ほとんど自覚症状がありません。健康診断で肝機能異常を指摘されて明らかになることが多いです。そのため、脂肪肝は「沈黙の肝臓病」とも呼ばれています。
診断
脂肪肝は、血液検査・超音波検査などで診断します。血液検査での肝臓の値が正常でも脂肪肝がある場合があります。超音波検査では肝臓が白く映る(高エコー)ことで脂肪の沈着が確認できます。血液検査の結果から算出する「FIB-4 index(フィブフォーインデックス)」という指標で、肝臓の線維化の進み具合を推測することもあります。
治療
 アルコール性脂肪肝の治療は禁酒しかありません。非アルコール性脂肪肝の治療の基本は生活習慣の改善です。並行して併発している生活習慣病を適切に管理することが重要です。体重をわずか5〜10%減らすだけでも、肝臓の脂肪が大きく減少するとされています。
アルコール性脂肪肝の治療は禁酒しかありません。非アルコール性脂肪肝の治療の基本は生活習慣の改善です。並行して併発している生活習慣病を適切に管理することが重要です。体重をわずか5〜10%減らすだけでも、肝臓の脂肪が大きく減少するとされています。
食事療法
極端な糖質制限などではなく、バランスのよい食事(野菜・魚・大豆製品中心)を心がけ、糖質入りの飲料や間食を控えることが効果的です。
運動療法
有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、自転車など)を1回30分・週3回以上実施するとと効果的です。
薬物療法
SGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬などの糖尿病治療薬が脂肪肝に有効であることが報告されています。しかしながら、現在ではまだ、脂肪肝の治療薬として保険で使用することは認められていません。
新しい概念
 脂肪肝をアルコール摂取の有無で分類する概念はやや古いものになりつつあります。ここで、脂肪肝の新しい概念を紹介します。
脂肪肝をアルコール摂取の有無で分類する概念はやや古いものになりつつあります。ここで、脂肪肝の新しい概念を紹介します。
代謝異常関連脂肪肝(MAFLD)
NAFLDの中には、予後の悪い群があり、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)と呼ばれていました。しかしながら、その診断には肝生検という入院が必要な検査が求められます。患者数が非常に多い脂肪肝の患者さんすべてに肝生検を実施するのは現実的ではありません。そこで、2020年に肥満症や高血圧症などの生活習慣病を併発している脂肪肝は予後が悪いことに注目し、MAFLDの概念が提唱されました。
代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)
非アルコール性脂肪肝は英語で「non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)」と書きます。非アルコール性という言葉はアルコール依存症の患者を否定し、さらにfatty(太っている)の言葉が差別を助長するとの批判がありました。以上のような背景があり、2023年にNAFLDは代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)への名称変更が推奨されました。「差別的表現を排除する」というポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)の潮流が医学界にも及び、病名の見直しが進められています。こうした社会的動向には賛否がありますが、医学用語にも時代の価値観が反映されている一例といえるでしょう。
脂肪肝についてよくあるご質問
脂肪肝はどんな人に多い病気ですか?
脂肪肝は大きく、アルコールの飲みすぎによる「アルコール性脂肪肝」と、飲酒が少ない方にみられる「非アルコール性脂肪肝(NAFLD)」に分けられます。アルコール性脂肪肝は多量飲酒を続ける人に多く、禁酒で改善が期待できます。一方、非アルコール性脂肪肝は肥満や糖尿病、高血圧、脂質異常症など生活習慣病を持つ方に多くみられます。
お酒を飲まないのに脂肪肝になるのはなぜですか?
過食や運動不足、肥満、糖尿病などが主な原因です。エネルギーとして使われなかった糖や脂肪が肝臓にたまり、炎症や線維化につながることがあります。
脂肪肝になるとどんな症状が出ますか?
初期は自覚症状がほとんどありません。進行して肝硬変や肝がんに至るまで気づかないこともあります。健診で肝機能異常を指摘された場合は放置せず、早めの対応が大切です。
脂肪肝は放置するとどうなりますか?
脂肪肝の一部は「脂肪肝炎(NASH)」へ進行し、さらに肝硬変や肝がんを発症することがあります。糖尿病や心血管疾患の発症リスクも上がることが知られています。
脂肪肝は治りますか?
多くの場合、生活習慣の改善で十分に改善が期待できます。体重を5〜10%減らすことで肝臓の脂肪が減り、血液検査の値も改善します。
脂肪肝の人が気をつける食事はありますか?
バランスのよい食事を心がけ、糖質入りの飲料や間食を控えることが大切です。野菜・魚・大豆製品を中心に、揚げ物や加工肉などの脂質を減らすことも有効です。
どんな運動が効果的ですか?
有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、自転車など)を1回30分、週3回以上続けると効果的です。無理のない範囲で継続することが大切です。
MASLD(マスルド)とは何ですか?
MASLDとは「代謝機能障害関連脂肪性肝疾患」の略で、2023年に提唱された新しい病名です。以前の「非アルコール性脂肪肝(NAFLD)」から、より中立的な表現に改められました。ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)の流れが医学界にも影響を与えた例といえます。