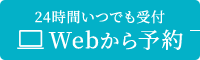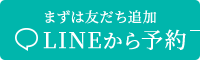南流山で糖尿病の診療なら当院へ
糖尿病と腎臓病は密接に関係しており、糖尿病はわが国の透析導入原因の第1位でもあります。両疾患を専門的に診療できる医療機関は限られていますが、南流山内科トータルクリニックでは、糖尿病と腎臓病の両方の専門資格を持つ医師が、総合的かつ継続的な診療を行っています。
治療方針はガイドラインに準拠しつつも、画一的な対応ではなく、患者さん一人ひとりの生活背景や価値観に配慮した、柔軟な医療提供を心がけています。
「健診で血糖値が高かった」など、症状が軽い段階でもお気軽にご相談ください。
専門的な評価と丁寧な説明を通じて、納得と安心につながる診療を提供いたします。
糖尿病とは
 糖尿病とは、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が慢性的に高くなる病気です。血糖値が高い状態が続くと、血管に負担がかかり、神経障害、網膜症(目の障害)、腎臓病などの合併症を引き起こします。これらの合併症は一度進行すると元に戻すことが難しいため、糖尿病治療の大きな目的は、血糖値を適切にコントロールして合併症を防ぐことにあります。
糖尿病とは、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が慢性的に高くなる病気です。血糖値が高い状態が続くと、血管に負担がかかり、神経障害、網膜症(目の障害)、腎臓病などの合併症を引き起こします。これらの合併症は一度進行すると元に戻すことが難しいため、糖尿病治療の大きな目的は、血糖値を適切にコントロールして合併症を防ぐことにあります。
血糖値が上がってしまう理由
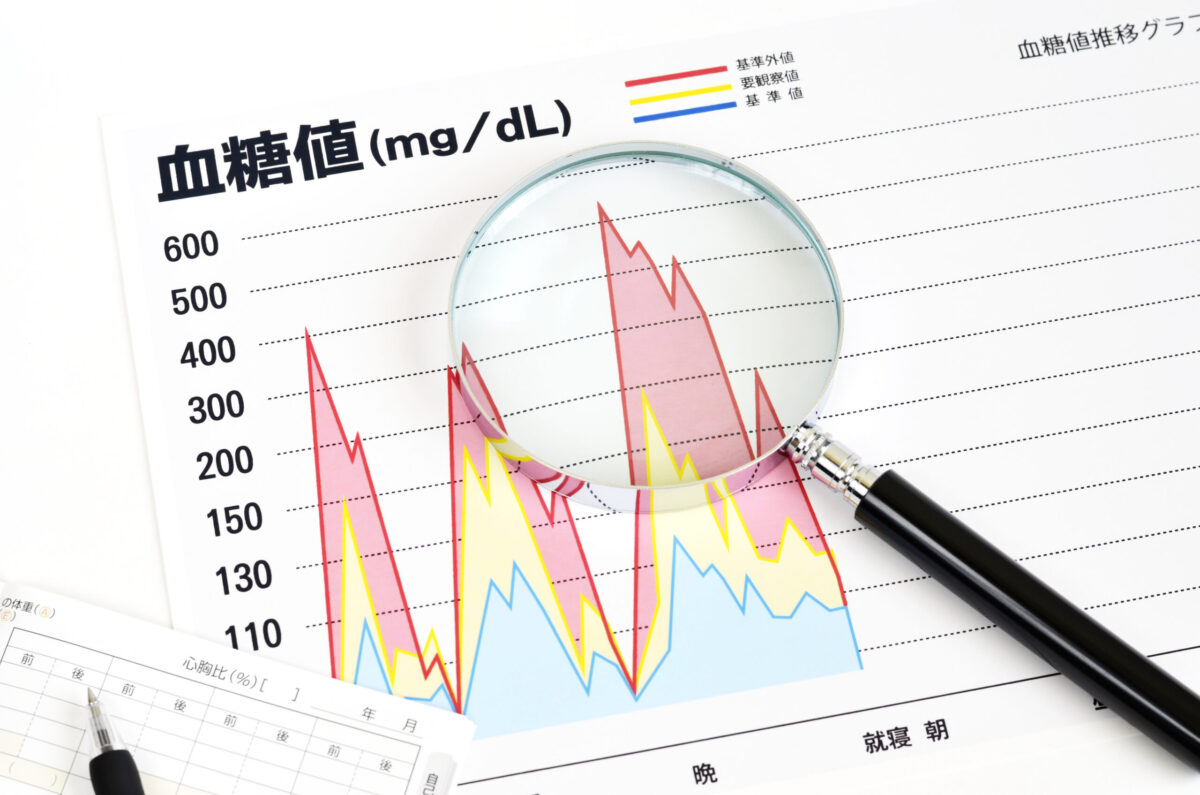 血糖値を下げる唯一のホルモン「インスリン」は、膵臓から分泌されます。
血糖値を下げる唯一のホルモン「インスリン」は、膵臓から分泌されます。
このインスリンの量が不足したり、インスリンがうまく働かない「インスリン抵抗性」が生じたりして、血糖値が高くなります。
インスリン抵抗性とは、インスリンが分泌されていても、その作用が十分に発揮されない状態を指します。特に肥満や内臓脂肪の蓄積があると、この抵抗性が強くなることが知られています。
糖尿病の分類
糖尿病は、その原因や発症のしくみによっていくつかのタイプに分類されます。なかでも代表的なのが「1型糖尿病」と「2型糖尿病」です。1型糖尿病は、主に免疫の異常によって膵臓がインスリンを作れなくなる病気です。2型糖尿病は、遺伝的な体質に加えて、生活習慣(食事や運動不足など)の影響が重なって発症します。糖尿病全体の90%以上は2型糖尿病が占めるため,世間一般に「糖尿病」といえば2型を指すことが多いです。
1型糖尿病
 1型糖尿病は、自己免疫の働きに異常が起こり、自分の膵臓のインスリンを作る細胞(β細胞)が破壊されることで発症する病気です。その結果、血糖を下げるために必要な「インスリン」が作れなくなり、血糖値が急激に上昇します。診断時には90%前後で自己抗体が陽性となることが多く、病型の鑑別に役立ちます。1型糖尿病は病気の進行スピードに応じて、以下のように分類されます。
1型糖尿病は、自己免疫の働きに異常が起こり、自分の膵臓のインスリンを作る細胞(β細胞)が破壊されることで発症する病気です。その結果、血糖を下げるために必要な「インスリン」が作れなくなり、血糖値が急激に上昇します。診断時には90%前後で自己抗体が陽性となることが多く、病型の鑑別に役立ちます。1型糖尿病は病気の進行スピードに応じて、以下のように分類されます。
- 劇症1型糖尿病:1週間前後で急速にインスリン分泌が枯渇します。
- 急性発症1型糖尿病:おおむね3か月以内にインスリン分泌が失われていきます。
- 緩徐進行1型糖尿病:ゆっくりと進行し、3か月〜数年かけてインスリン分泌が低下していきます。
いずれのタイプも、最終的には膵臓でインスリンを作る力がほとんど失われるため、内服薬だけでの治療は困難です。治療には必ずインスリン注射が必要となります。
2型糖尿病
 2型糖尿病は、もともとの体質(遺伝的な要素)に、生活習慣の影響(過食・運動不足・肥満など)が加わって発症する病気です。「不摂生が原因」と思われがちですが、実は持って生まれた体質が発症しやすいさに大きく影響することがわかっています。2型糖尿病の治療は、食事療法と運動療法が基本です。それでも血糖コントロールが不十分な場合は、内服薬や注射製剤などの薬物療法を組み合わせて行います。薬の選択は、血糖値の状態だけでなく、年齢・腎機能・体重・持病・仕事・ライフスタイルなどを考慮して決めていきます。
2型糖尿病は、もともとの体質(遺伝的な要素)に、生活習慣の影響(過食・運動不足・肥満など)が加わって発症する病気です。「不摂生が原因」と思われがちですが、実は持って生まれた体質が発症しやすいさに大きく影響することがわかっています。2型糖尿病の治療は、食事療法と運動療法が基本です。それでも血糖コントロールが不十分な場合は、内服薬や注射製剤などの薬物療法を組み合わせて行います。薬の選択は、血糖値の状態だけでなく、年齢・腎機能・体重・持病・仕事・ライフスタイルなどを考慮して決めていきます。
糖尿病の症状
 糖尿病の症状は、血糖値が非常に高くなったときに現れることが多く、以下のようなものが知られています。
糖尿病の症状は、血糖値が非常に高くなったときに現れることが多く、以下のようなものが知られています。
- 急な体重減少
- 尿の回数が増える
- のどの渇きが強くなる
- 疲れやすさ、だるさ
ただし、これらの症状は血糖値が概ね250 mg/dLを超えるような高値にならないと目立ってこないとされており、実際には多くの糖尿病患者さんが自覚症状のないまま過ごしています。そのため、糖尿病は「沈黙の病気」とも呼ばれ、気づかないうちに進行し、合併症が出てから初めて診断されるケースも少なくありません。症状に乏しいため、糖尿病と診断されても病院を受診しないケースの多いことも知られています。
糖尿病患者さんの病院受診率
令和5年「国民健康・栄養調査」によると、糖尿病と診断された方のうち、実際に治療を受けている割合は男性で81.1%、女性で77.1%、全体では79.5%と報告されています。この割合は年々少しずつ改善していますが、裏を返せば、糖尿病と診断されていながら、約5人に1人は治療を受けていない状況にあります。このような未治療の方に早期に医療介入することが、国全体の健康課題となっており、国レベルでも受診を促す取り組みが進められています。
糖尿病の治療が必要である理由
「症状がないなら治療しなくてもよいのでは?」と感じる方もいらっしゃいますが、糖尿病の本当の怖さは、気づかないうちに進行する「合併症」にあります。糖尿病の合併症は時間がたつほどに治療が難しくなってきます。できるだけ早く糖尿病の治療を開始し、継続することが非常に重要です。つまり、症状がない今こそが治療のチャンスであり、将来の健康を守る第一歩になります。
糖尿病の合併症
糖尿病は、高血糖が長期間続くことで血管に負担をかける病気です。そのため、合併症の多くは血管に関連しており、大きく「細小血管症」と「大血管症」に分けられます。また、これらの血管障害以外にも、免疫力の低下や骨、認知機能、がんとの関係も報告されており、糖尿病は全身に影響を与える病気といえます。
糖尿病の細小血管症
細小血管症とは、目・腎臓・神経などに張り巡らされた細い血管が障害されることで生じる合併症です。糖尿病性神経障害、網膜症、腎症の3つがあり、「三大合併症」とも呼ばれます。この3つは、糖尿病がなければ基本的に起こらない「糖尿病に特異的な合併症」です。また、発症にはある程度の年月がかかり、通常は糖尿病発症後5~10年で症状が現れてきます。発症の順番は、一般的に「神経障害(し)→網膜症(め)→腎症(じ)」が多く、頭文字をとって『し・め・じ』と覚えると分かりやすいでしょう。
糖尿病性神経障害
 糖尿病性神経障害は、高血糖が続くことで神経にダメージが蓄積して起こる合併症です。感覚神経・運動神経・自律神経が障害され、症状は多岐にわたります。もっとも多いのが「感覚・運動神経障害」で、足の指先から左右対称にしびれや痛みが生じます。
糖尿病性神経障害は、高血糖が続くことで神経にダメージが蓄積して起こる合併症です。感覚神経・運動神経・自律神経が障害され、症状は多岐にわたります。もっとも多いのが「感覚・運動神経障害」で、足の指先から左右対称にしびれや痛みが生じます。
「グローブ&ストッキング型」とも呼ばれ、手袋や靴下を履いたような感覚異常が特徴です。自律神経障害では、立ちくらみ、発汗異常、胃のもたれ、排尿障害などがみられます。特に心臓の神経が障害されると、無症候性の狭心症や突然死のリスクがあるため注意が必要です。
糖尿病性網膜症
糖尿病性網膜症は、目の奥にある「網膜」の細い血管が高血糖により障害されることで起こります。
進行段階は以下の4つに分類されます。
- 正常
- 単純網膜症
- 増殖前網膜症
- 増殖網膜症(最重症)
初期段階では自覚症状がほとんどありませんが、進行すると視野の欠け、ゆがみ、飛蚊症(黒いものが飛んで見える)、急激な視力低下などが生じます。最悪の場合には失明することもあり、実際に糖尿病性網膜症は日本の中途失明原因の3位に位置しています。症状がなくても、糖尿病と診断された方は必ず定期的に眼科受診を行い、早期発見・早期治療を心がけましょう。
糖尿病性腎症
糖尿病性腎症は、腎臓の糸球体と呼ばれる微細な血管が障害され、腎機能が徐々に低下していく合併症です。日本では透析導入の原因疾患の第1位となっており、予防と早期介入が非常に重要です。初期には「尿中にアルブミンというたんぱく質が漏れ出る」という変化がみられ、これは血液検査ではわからないため、尿検査によるスクリーニングが欠かせません。かつては進行を抑える方法が限られていましたが、現在ではSGLT2阻害薬など、腎保護効果をもつ薬剤の登場により、治療の選択肢が大きく広がっています。
糖尿病の大血管症
大血管症とは、動脈硬化により太い血管が狭くなったり詰まったりして、血流が悪くなり、臓器に障害が起きる合併症です。代表的なものに「閉塞性動脈硬化症」、「脳梗塞」、「心筋梗塞」があります。これらは高血糖だけでなく、高血圧・脂質異常症・喫煙・加齢などもリスク因子であり、糖尿病がなくても発症する可能性がありますが、糖尿病があると発症リスクが大幅に上昇します。
当院では、上腕と足首の血管の硬さやつまり具合を測定する「baPWV(脈波伝播速度)」や「ABI(足関節上腕血圧比)」を実施しており、大血管症の評価に活用しています。
閉塞性動脈硬化症
足の血管が動脈硬化により細くなり、血液が十分に流れなくなることで起こる疾患です。初期には足の冷感やしびれ程度の症状ですが、進行すると「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」と呼ばれる、歩くとふくらはぎが痛くなり、休むと改善する症状がみられます。さらに悪化すると、安静時の痛みや潰瘍、壊疽(えそ)を起こすこともあります。ABIが0.9未満の場合は閉塞性動脈硬化症の可能性が高く、専門病院への紹介が必要です。
脳梗塞
 脳梗塞は、脳の血管が詰まり、その先の脳細胞が壊死してしまう病気です。突然の手足の麻痺、ろれつが回らない、ふらつき、片側のしびれや脱力などの症状が出現します。発症から治療開始までの時間が予後を大きく左右するため、少しでも疑わしい場合はすぐに救急対応が必要です。糖尿病があると脳梗塞のリスクが約2〜4倍になるとされており、合併症として特に注意すべき疾患です。
脳梗塞は、脳の血管が詰まり、その先の脳細胞が壊死してしまう病気です。突然の手足の麻痺、ろれつが回らない、ふらつき、片側のしびれや脱力などの症状が出現します。発症から治療開始までの時間が予後を大きく左右するため、少しでも疑わしい場合はすぐに救急対応が必要です。糖尿病があると脳梗塞のリスクが約2〜4倍になるとされており、合併症として特に注意すべき疾患です。
心筋梗塞
 心筋梗塞は、心臓に酸素と栄養を送る「冠動脈」が詰まり、心筋が壊死してしまう病気です。典型的には、胸を締めつけられるような強い痛みや圧迫感、呼吸困難が突然出現します。糖尿病の方は神経障害の影響で痛みに気づきにくく、「無痛性心筋梗塞」として発見が遅れることもあります。年間およそ3万人がこの病気で亡くなっており、発症時の迅速な対応が命を守るカギとなります。
心筋梗塞は、心臓に酸素と栄養を送る「冠動脈」が詰まり、心筋が壊死してしまう病気です。典型的には、胸を締めつけられるような強い痛みや圧迫感、呼吸困難が突然出現します。糖尿病の方は神経障害の影響で痛みに気づきにくく、「無痛性心筋梗塞」として発見が遅れることもあります。年間およそ3万人がこの病気で亡くなっており、発症時の迅速な対応が命を守るカギとなります。
その他の合併症
糖尿病は血管障害だけでなく、全身のさまざまな臓器や機能に影響を与える慢性疾患です。近年では、免疫機能の低下、骨折リスクの上昇、認知症の発症リスク増加、さらに一部のがんの発症との関連も明らかになってきています。
免疫力の低下
糖尿病があると、免疫をつかさどる白血球の働きが弱まり、感染症にかかりやすくなることが知られています。血糖値が高い状態では、白血球が細菌やウイルスを取り込んだり排除したりする力が低下し、感染が重症化しやすくなったり、治りにくくなったりします。実際、新型コロナウイルス感染症においても、糖尿病がある方は重症化のリスクが高いという結果が報告されています。また、免疫力の低下は外科手術後の創部感染リスクにもつながるため、糖尿病のある方では術前の血糖管理が非常に重要です。
骨粗鬆症
糖尿病のある方は、骨折のリスクが高いことがわかっています。1型糖尿病では骨折のリスクが3〜7倍、2型糖尿病でも1.3〜2.8倍に増加すると報告されています。骨の強さは「骨密度(70%)」と「骨質(30%)」で構成されますが、2型糖尿病の方では骨密度が比較的保たれていても、骨の質が低下することで骨折しやすくなる傾向があります。現在、広く使われている骨密度検査(DEXA法)では骨質の評価が困難なため、糖尿病患者さんでは検査結果が正常でも骨折リスクが過小評価される可能性があります。日常生活での転倒防止や筋力維持、必要に応じた骨折予防薬の活用が重要です。
認知症
 糖尿病と認知症の関連性も近年注目されています。認知症の主なタイプであるアルツハイマー型認知症や血管性認知症の発症リスクが、糖尿病によって高まることが分かっています。
糖尿病と認知症の関連性も近年注目されています。認知症の主なタイプであるアルツハイマー型認知症や血管性認知症の発症リスクが、糖尿病によって高まることが分かっています。
- アルツハイマー型認知症:1.5〜2.0倍に増加
- 血管性認知症:2〜3.5倍に増加
特に高齢の糖尿病患者さんでは、日々の生活管理能力や服薬管理にも注意が必要です。
がん
糖尿病は一部のがんのリスクを高めることが知られています。日本人を対象とした大規模研究では、糖尿病患者において以下のがんの発症率が高くなることが報告されています。
- 肝臓がん:約1.97倍
- 膵臓がん:約1.85倍
- 大腸がん:約1.4倍
そのほか、子宮内膜がんや膀胱がんのリスクも上昇する可能性があります。一方で、以前は糖尿病が前立腺がんの発症率を下げるとされていた報告もありましたが、最新の研究(2023年)では明確な関連は認められていません。糖尿病をきっかけに、がんを含む全身のリスク評価や健診の受診率を高めることも重要です。
糖尿病に関連する検査項目
糖尿病は「早期発見」と「継続的な評価」が治療の基本となる病気です。当院では、診断から治療方針の決定、合併症の早期発見に至るまで、糖尿病管理に必要な各種検査を行っています。ここでは代表的な検査項目をご紹介します。
空腹時血糖値
 空腹時血糖値とは、10時間以上食事を摂らずに測定した血糖値です。もっとも標準的な評価法であり、糖尿病のスクリーニングや経過観察に広く用いられます。「糖尿病型」は糖尿病の可能性が高い状態です。
空腹時血糖値とは、10時間以上食事を摂らずに測定した血糖値です。もっとも標準的な評価法であり、糖尿病のスクリーニングや経過観察に広く用いられます。「糖尿病型」は糖尿病の可能性が高い状態です。
- 正常値:100 mg/dL未満
- 正常高値:100〜109 mg/dL
- 境界型(予備群):110〜125 mg/dL
- 糖尿病型:126 mg/dL以上
空腹時血糖が正常でも、他の検査で異常が出ることもあるため、総合的な評価が重要です。
随時血糖値
随時血糖値は、食事時間に関係なく、日中の任意のタイミングで測定された血糖値です。健診や外来受診時によく使われる実用的な検査であり、症状や他の検査と組み合わせて評価します。糖尿病型は200mg/dL以上とされ、糖尿病の可能性が高い状態です。ただし、食後の影響を受けやすいため、1回の結果で判断せず、必要に応じて空腹時血糖やHbA1cと併用して診断します。
HbA1c(ヘモグロビンA1c)
HbA1cは、過去1~2か月の平均血糖値を反映する検査で、糖尿病の診断や治療評価の指標として欠かせません。健康な方のHbA1cはだいたい5.5%前後で6.5%以上は「糖尿病型」とされ、糖尿病と診断される目安になります。一時的な血糖変動に左右されにくく、継続的な血糖コントロールの指標としても有用です。
尿中アルブミン(ACR)
糖尿病の合併症である「糖尿病性腎症」では、血清クレアチニンなどの一般的な腎機能検査が正常である初期の段階でも尿中のアルブミンの値が上昇してくることが知られています。腎症ではより初期の段階からの治療介入が必要とされているため、尿中アルブミンによる腎症の早期診断は極めて重要です。尿中アルブミンの排出が多いほど、腎症だけでなく心血管病のリスクも高くなることが分かっています。
空腹時血清C-ペプチド(CPR)
C-ペプチドは、体内でインスリンがどれくらい分泌されているかを反映する指標であり、主に膵臓のインスリン分泌能を評価する目的で用います。特に1型糖尿病との鑑別や、インスリン注射の必要性を判断する際に有用です。値が著しく低い場合、内服薬のみでは血糖コントロールが困難であり、インスリン治療が適応となることがあります。
糖尿病の診断
複数の検査結果や症状を組み合わせて総合的に判断します。以下のいずれかに該当する場合、糖尿病と診断されます。
- 空腹時血糖値≧126 mg/dL又は随時血糖値≧200 mg/dL又はHbA1c≧6.5%を2回確認(1回は必ず血糖値で確認)
- 空腹時血糖値≧126 mg/dL又は随時血糖値≧200 mg/dL+「慢性的な高血糖症状」の確認
- 過去に糖尿病と診断された証拠がある
なお、「慢性的な高血糖症状」とは口渇、多飲、多尿、体重減少などの糖尿病の典型的な症状を認める場合もしくは糖尿病の網膜症を認める場合が該当します。
血糖値の管理目標
 血糖値のコントロール目標は、患者さんの状態に応じて以下のように段階的に設定されます。糖尿病治療の目的は、合併症を予防し、健康的な生活を維持することにありますので。そのため、まずはHbA1cを7%未満を目指すことが基本的な管理目標となります。
血糖値のコントロール目標は、患者さんの状態に応じて以下のように段階的に設定されます。糖尿病治療の目的は、合併症を予防し、健康的な生活を維持することにありますので。そのため、まずはHbA1cを7%未満を目指すことが基本的な管理目標となります。
| HbA1cの数値 | |
|---|---|
| 血糖正常化を目指す際の目標 | 6.0%未満 |
| 合併症予防のための目標 | 7.0%未満 |
| 治療強化が困難な際の目標 | 8.0%未満 |
特に65歳以上の方では、加齢に伴う低血糖リスクや自己管理能力の変化を考慮し、より緩やかな目標設定が必要となります。患者さんの状態や年齢、あるいは低血糖の起こしやすい薬剤の使用状況に応じて、管理目標が決められています。
しかしながら、数値目標はあくまでも目安にすぎません。患者さんの病態や社会的状況や価値観を尊重しながら、管理目標を相談のうえで個別に管理目標を設定します。当院では、ガイドラインに準じた適切な目標値を提示しながら、患者さん一人ひとりのライフスタイルに合った治療方針を大切にしています。
糖尿病の治療
糖尿病治療の基本は、「生活習慣の見直し」です。具体的には、食事療法と運動療法を中心に行い、必要に応じて薬物療法を追加していきます。薬物療法の効果を十分に引き出すためにも、食事療法と運動療法の継続が重要です。また、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病も糖尿病の合併症リスクを高めるため、包括的な管理が求められます。ガイドラインでも、糖尿病患者さんでは、通常よりも厳格な生活習慣病の管理目標が設定されています。
食事療法
食事療法は、糖尿病治療の基本中の基本です。血糖値の安定化や体重管理、合併症の予防において重要な要素と報告されています。1日に必要なカロリー量は、体格(BMI)と身体活動量をもとに算出されます。一般的には、標準体重(身長m×身長m×22)に活動量(25〜35
kcal/kg)を掛けた値が目安となります。計算が難しい場合は、診察時に一緒に確認しますのでご安心ください。食事療法のポイントは「2つのバランス」です。
栄養バランス
 糖質・脂質・たんぱく質の三大栄養素を適切な割合でバランスよく摂取することが基本です。
糖質・脂質・たんぱく質の三大栄養素を適切な割合でバランスよく摂取することが基本です。
極端な糖質制限や過剰なたんぱく質摂取は、原則として推奨されていません。
1日3食の配分バランス
 朝・昼・夕の3食を均等なカロリーで分けることが望ましく、特に夕食に偏った摂取は血糖の急上昇を招く原因となります。実際の献立では「主食(ご飯・パン)」「主菜(肉・魚・大豆製品)」「副菜(野菜・海藻)」を意識した構成が理想です。
朝・昼・夕の3食を均等なカロリーで分けることが望ましく、特に夕食に偏った摂取は血糖の急上昇を招く原因となります。実際の献立では「主食(ご飯・パン)」「主菜(肉・魚・大豆製品)」「副菜(野菜・海藻)」を意識した構成が理想です。
ちょっとした工夫(野菜を先に食べる・甘い飲料を控える・間食を見直す)でも、血糖値の安定に大きな効果があります。
外食やコンビニ食でも、「定食スタイルを選ぶ」「サラダを先にとる」「汁物は控えめにする」など、無理のない調整が可能です。
当院では、患者さんの生活背景や嗜好に合わせた、実行可能で続けやすい食事療法をご提案しています。
運動療法
運動療法は、特に2型糖尿病において食事療法と並ぶ基本的な治療です。運動療法によって得られる主な効果には、以下のようなものがあります。
- 血糖値の低下
- インスリン抵抗性の改善
- 体重、内臓脂肪の減少
- 血圧、脂質の改善
- 気分の安定、ストレス軽減
 おすすめはウォーキングや水中運動などの有酸素運動で、1日20~30分を週3~5回行うのが理想です。ただし、最初は1日10分の軽い運動からでも構いません。さらに、筋トレ(スクワット・かかと上げなど)を組み合わせることで、運動効果がより高まります。通勤や買い物時に階段を使うなどの“ながら運動”も、日常生活に自然に取り入れられる方法のひとつです。
おすすめはウォーキングや水中運動などの有酸素運動で、1日20~30分を週3~5回行うのが理想です。ただし、最初は1日10分の軽い運動からでも構いません。さらに、筋トレ(スクワット・かかと上げなど)を組み合わせることで、運動効果がより高まります。通勤や買い物時に階段を使うなどの“ながら運動”も、日常生活に自然に取り入れられる方法のひとつです。
運動の種類や頻度は、年齢・体力・持病の有無に応じて柔軟に調整しましょう。特に心臓や関節に不安のある方は、安全に取り組める範囲から始めることが大切です。
薬物療法
 食事療法や運動療法を行っても血糖コントロールが不十分な場合は、薬物療法を追加します。糖尿病治療薬には、「経口薬」と「注射薬」があり、患者さんの病態や生活状況に応じて選択します。
食事療法や運動療法を行っても血糖コントロールが不十分な場合は、薬物療法を追加します。糖尿病治療薬には、「経口薬」と「注射薬」があり、患者さんの病態や生活状況に応じて選択します。
経口糖尿病薬
経口薬は8つの種類に分類されますが、主に以下の3系統がよく使われます。
ビグアナイド薬(例:メトホルミン)
古くから使用されており、安価かつ有効性が高い薬です。腎機能障害がある場合は用量調整や休薬が必要で、造影検査や手術前にも休薬することがあります。初期に下痢などの胃腸症状が出ることがありますが、通常は次第に軽快します。
DPP-4阻害薬
血糖値に応じてインスリンの分泌を促す薬で、低血糖を起こしにくく高齢者にも使いやすいのが特徴です。まれに「水疱性類天疱瘡」などの皮膚症状が副作用として報告されています。
SGLT2阻害薬
尿とともに余分な糖を排出する薬で、心臓・腎臓保護作用や体重減少効果も期待できます。最大の特徴は心臓・腎臓保護作用を有している点で、心臓や腎臓の障害を抱えている患者さんに優先して使用されます。一方で、脱水・尿路感染症・筋力低下などに注意が必要です。
GLP-1受容体作動薬(注射)
GLP-1受容体作動薬は、以下の2つの特徴を持つ薬です。
- 血糖値が高いときにだけ作用するため、低血糖を起こしにくい
- 食欲を抑える効果があり、体重減少が期待できる
従来の糖尿病薬は体重が増えやすい傾向がありましたが、GLP-1作動薬は体重を減らせることが大きな特徴です。現在では、抗肥満薬としても使用される様になり注目されています。種類によって効果や頻度が異なるため、患者さんの体調や目標に応じて使い分けます。
GIP/GLP-1共受容体作動薬(マンジャロ)
マンジャロは、GLP-1に加えGIPというホルモンの受容体にも作用する新しい注射薬です。従来のGLP-1受容体作動薬よりも強力な血糖降下作用と体重減少効果があり、非常に注目されています。初期には吐き気などの副作用が出やすいため、少量から開始し、体調を見ながら慎重に増量していきます。急激な体重減少による筋力低下を防ぐため、運動療法を併用することが大切です。
インスリン製剤
 1型糖尿病や進行した2型糖尿病など、自分の膵臓でインスリンをつくることのできなくなった患者さんや特に初診時などで血糖値が非常に高い場合に使用を検討します。
1型糖尿病や進行した2型糖尿病など、自分の膵臓でインスリンをつくることのできなくなった患者さんや特に初診時などで血糖値が非常に高い場合に使用を検討します。
インスリンには2つの役割分担があります。
- 基礎インスリン(空腹時の血糖を維持)
- 追加インスリン(食後の血糖上昇を抑制)
通常は、持効型(基礎)と超速効型(追加)を単独または併用して使用します。患者さんの血糖パターンや生活スタイルに応じて調整を行い、適切な血糖管理を目指します。
糖尿病患者さんにおける生活習慣病の管理
糖尿病そのものの血糖管理に加えて、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病を総合的に管理することが、合併症の予防につながります。これらの疾患は互いに影響し合い、合併症の進行を加速させる「サイレントキラー」として知られています。そのため、糖尿病患者さんでは、通常よりも厳格な管理目標がガイドライン上で推奨されています。
血圧の管理について
糖尿病患者さんの血圧の管理目標は診察室血圧130/80 mmHg未満(家庭血圧 125/75mmHg未満)と報告されています。当院では状態をより正確にあらわす家庭血圧を重視しています。冠動脈疾患や閉塞性動脈硬化症がある場合には病状を悪化させる可能性があるために注意深く、血圧を管理することが推奨されています。
糖尿病患者さんの脂質管理について
管理の中心となるのはLDLコレステロール(悪玉コレステロール)で、患者さんの背景によって目標値が異なります。
- 合併症や既往のない場合:LDL-C<120 mg/dL
- 細小血管症や閉塞性動脈硬化症の合併症がある場合:LDL-C<100 mg/dL
- 冠動脈疾患や脳梗塞の既往がある場合:LDL-C<70 mg/dL
また、以下の値も併せて管理します。
- 中性脂肪(TG):空腹時150 mg/dL未満/随時175 mg/dL未満
- HDLコレステロール(善玉):40 mg/dL以上
当院では、必要に応じて食事・運動の見直しに加え、スタチンやエゼチミブ、フィブラート系薬などの脂質低下薬も使用し、合併症予防を図っています。