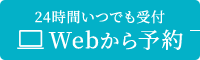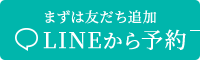南流山で循環器内科をお探しの方へ
循環器内科は、心臓や血管を内科的に診断・治療する専門の診療科です。これらの疾患は進行してからでは治療が難しくなることも多く、早期の発見と管理がとても重要です。とくに高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は心臓病のリスクを高めるため、日頃からの丁寧なフォローが求められます。南流山内科トータルクリニックでは、糖尿病・腎臓病・総合内科の専門医としての知識と経験を活かし、心臓や血管に関わる疾患を総合的に診療しています。生活習慣病に精通しているからこそ、動脈硬化や心不全の予防に向けた継続的な管理が可能です。必要に応じて心電図、血液検査、レントゲンなどの基本的な検査を行い、重大な心疾患が疑われる場合は速やかに専門病院をご紹介いたします。地域のかかりつけ医として、安心してご相談いただける体制を整えていますので、気になる症状がある方はお気軽にご来院ください。
心臓や血管に関連した症状
心臓や血管の病気は、体のさまざまな場所に症状を引き起こします。はじめは軽い違和感でも、放っておくと命に関わる病気が隠れていることもあります。当院では、これらの症状に対して必要な初期評価を行い、対応可能なものは院内で治療し、さらに詳しい検査や専門的な治療が必要と判断される場合には、症状の緊急度に応じて専門病院をご紹介いたします。気になる症状がある方は、お早めにご相談ください。
胸が痛い、胸がしめ付けられる
 体を動かした際に生じる、胸の痛みや圧迫感は、狭心症や心筋梗塞などの命に関わる心臓の血管の病気が原因のことがあります。「胸がギューッと締めつけられるような感じ」が数分続いたり、頻度が増える場合は要注意です。当院では心電図で緊急性を確認し、重篤な心疾患が疑われる場合には速やかに専門病院をご紹介いたします。早期の受診が命を守る鍵になります。
体を動かした際に生じる、胸の痛みや圧迫感は、狭心症や心筋梗塞などの命に関わる心臓の血管の病気が原因のことがあります。「胸がギューッと締めつけられるような感じ」が数分続いたり、頻度が増える場合は要注意です。当院では心電図で緊急性を確認し、重篤な心疾患が疑われる場合には速やかに専門病院をご紹介いたします。早期の受診が命を守る鍵になります。
動悸がする、血圧計で不整と表示された
「心臓がバクバクする」「ドクドクと不規則に感じる」などの動悸は、不整脈が原因のことがあります。家庭の血圧計で「不整脈あり」と表示された場合も、見逃さずに評価が必要です。当院では心電図などで基本的な評価を行いますが、症状が一時的で心電図に現れない場合は、ホルター心電図(24時間心電図)などの追加検査が必要となるため、症状の経過や初期評価に応じて専門病院をご紹介いたします。
息切れ
 少し動いただけで息が上がる、横になると息苦しくなるといった症状は、心不全の初期サインかもしれません。また、肺疾患や貧血、甲状腺異常なども関係する場合があります。当院では、心不全を含めた内科的な疾患に幅広く対応していますが、より詳しい評価や入院加療が必要と判断された場合には専門病院をご紹介いたします。
少し動いただけで息が上がる、横になると息苦しくなるといった症状は、心不全の初期サインかもしれません。また、肺疾患や貧血、甲状腺異常なども関係する場合があります。当院では、心不全を含めた内科的な疾患に幅広く対応していますが、より詳しい評価や入院加療が必要と判断された場合には専門病院をご紹介いたします。
足のむくみ
夕方になると足が腫れる、靴下の跡がなかなか消えない、というむくみは、心不全、腎機能低下、静脈うっ滞、薬剤性などさまざまな原因があります。片足のみのむくみは血栓症のこともあり注意が必要です。当院では、心不全や腎疾患などに対応可能な検査・治療を行っており、必要に応じて専門病院をご紹介いたします。
ふらつく、意識が飛んだ
 突然のふらつきや一瞬意識を失うような感覚は、血圧の急激な変動や不整脈が原因のことがあります。とくに失神を伴う場合は重大な病気が隠れていることがあるため、早めの受診が重要です。当院では心電図や血圧の変動を確認し、一時的な評価で診断がつかない場合には、追加検査が可能な専門病院をご紹介いたします。
突然のふらつきや一瞬意識を失うような感覚は、血圧の急激な変動や不整脈が原因のことがあります。とくに失神を伴う場合は重大な病気が隠れていることがあるため、早めの受診が重要です。当院では心電図や血圧の変動を確認し、一時的な評価で診断がつかない場合には、追加検査が可能な専門病院をご紹介いたします。
歩いていると足が痛くなり、休むとおさまる
歩行中に足が痛み、しばらく休むと楽になる――このような症状は「閉塞性動脈硬化症(ASO)」の典型例です。血管が狭くなり、筋肉に十分な血流が届かなくなることが原因です。当院では、足の血流を調べるABI(足関節上腕血圧比)検査を行っており、血流低下が確認された場合には段階的に専門病院をご紹介いたします。
慢性心不全
慢性心不全とは、心臓のポンプ機能が長い時間をかけて徐々に弱くなり、全身に必要な血液を送り出せなくなる状態です。この状態が長く続いたり、何度も悪化と回復をくり返すことが特徴で、一度発症すると完治することは難しく、生涯にわたって治療と管理が必要な病気です。日本では高齢化の影響もあり、心不全の患者数は2030年には130万人以上に増加すると推定されています。
慢性心不全の原因疾患
原因疾患は多岐わたり、心疾患の原因としては心筋梗塞や弁膜症などがあります。近年は、心疾患でない慢性心不全のリスク因子である高血圧や糖尿病、慢性腎臓病なども原因として重要視されています。近年の診療ガイドラインでは心臓に異常がなくても、これらのリスク因子が存在するだけで“心不全のステージA”と定義され、心不全の初期段階とみなされるようになりました。
| ステージA | 心不全のリスク因子はあるが、心臓の構造の異常がおこっておらず、症状もない状態 |
|---|---|
| ステージB | 心臓の構造の異常はおこっているが、症状がない状態 |
| ステージC | 心臓の構造の異常があり、かつ症状が出現している状態 |
| ステージD | 心臓の構造の異常があり、治療しても症状を抑えられない状態 |
慢性心不全の進展の予防~早期治療の重要性~
いったん障害を受けてしまった心臓は元に戻すことはできません。したがって、まだ心臓の構造に異常が起こっていない早期からの心不全のリスク因子の包括的な管理が必要になります。これは南流山内科トータルクリニックが最も得意とするところです。心不全は、「症状が出てから対応する」よりも、「症状が出る前に止める」ことが何よりも重要です。心不全の進展の予防の第一歩として、ぜひ早めの受診をご検討ください。
慢性心不全の症状
 進行するにつれて、以下のような症状があらわれていきます。
進行するにつれて、以下のような症状があらわれていきます。
- 階段や坂道を登った時に息が切れる
- むくみが夕方になると足首やすねにあらわれ、朝起きたときには消えている
- 横になると息切れが悪化する
- 食事の量は変わっていないのに短期間で体重が急に増える
- 倦怠感があり、疲れやすい
慢性心不全の治療
慢性心不全のステージが進行し、心臓の構造の変化が起こり、症状が現れた場合には、診療の方針は予防から治療にシフトしていきます。慢性心不全の治療は左室駆出率により異なります。
心不全の分類
心臓が1回の拍動で抱え込んだ血液のうち、どれだけを血管に送り出せるかを表す割合を左室駆出率と言います。心不全は左室駆出率の大きさに応じて以下のように分類されます。この分類により病態や有効な薬が異なってくるので、非常に重要です。左室駆出率は心エコー検査で評価することができます。
| 左室駆出率の低下した心不全(HFrEF) | 左室駆出率 ≦ 40% |
|---|---|
| 左室駆出率の軽度低下した心不全(HFmrEF) | 左室駆出率 41-49% |
| 左室駆出率の保たれた心不全(HFpEF) | 左室駆出率 ≧ 50% |
HFrEFの治療
近年、新規の心不全の治療薬が発売され、HFrEFの治療の幅は大きく広がりました。作用機序が異なり、かつ有効性が証明されている4種類の薬剤はアメリカのスーパーヒーロー映画になぞられて「ファンタスティック・フォー」とも呼ばれ、現在ではHFrEF治療の基本となっています。

HFpEFの治療
長らくHFpEFに対する有効な治療薬はなく、心不全が進展して体液が貯留してしまった場合に利尿剤を使用する程度でした。しかし近年、SGLT2阻害薬がHFpEF患者の予後を改善しうる薬剤として報告され、治療の基本として位置付けられています。
代表的な循環器疾患
心臓や血管に関係する病気は多岐にわたりますが、その多くは動脈硬化や高血圧症・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病が背景にあります。進行すると命に関わることもあるため、早期の診断と、継続的な管理・予防がとても大切です。ここでは、当院でよくご相談いただく代表的な循環器疾患についてご紹介します。
虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)
虚血性心疾患は、心臓に酸素を送る血管(冠動脈)が動脈硬化などで狭くなり、酸素が届きにくくなる病気です。「狭心症」は一時的な血流不足、「心筋梗塞」は血流が完全に止まることで起こり、命に関わる重大な病気です。胸の痛み・締め付けられる感じ・圧迫感が主な症状で、階段や坂道で悪化する場合は要注意です。当院では、心電図や血液検査などで緊急性を評価し、虚血性心疾患が疑われる場合には速やかに循環器専門病院にご紹介いたします。急性期治療が終了した後は、抗血小板薬の継続や生活習慣病の管理、生活指導を通じて、再発予防や慢性期のフォローアップを当院で行っています。
心房細動
 心房細動は、心臓の上部(心房)が不規則に震えるように動く不整脈で、動悸や息切れの原因となることがあります。特に高齢者や高血圧・心臓病をお持ちの方に多く、脳梗塞のリスクが高まるため注意が必要です。症状が出ない「隠れ心房細動」もあり、家庭の血圧計で「不整脈あり」と表示された場合も注意が必要です。当院では、心電図を用いた診断を行い、必要に応じて脳梗塞予防のための抗凝固薬の内服や、心拍数を適切に保つレートコントロールを行います。リズムコントロール(正常な脈に戻す治療)やカテーテルアブレーションが必要と判断される場合は、循環器専門医と連携して対応いたします。
心房細動は、心臓の上部(心房)が不規則に震えるように動く不整脈で、動悸や息切れの原因となることがあります。特に高齢者や高血圧・心臓病をお持ちの方に多く、脳梗塞のリスクが高まるため注意が必要です。症状が出ない「隠れ心房細動」もあり、家庭の血圧計で「不整脈あり」と表示された場合も注意が必要です。当院では、心電図を用いた診断を行い、必要に応じて脳梗塞予防のための抗凝固薬の内服や、心拍数を適切に保つレートコントロールを行います。リズムコントロール(正常な脈に戻す治療)やカテーテルアブレーションが必要と判断される場合は、循環器専門医と連携して対応いたします。
閉塞性動脈硬化症(ASO)
閉塞性動脈硬化症は、足の血管が動脈硬化で狭くなり、歩いていると足が痛くなり、休むと楽になる(間欠性跛行)という症状が特徴的な病気です。重症になると、足の冷感や皮膚の色調異常、潰瘍などが見られることもあります。当院では、ABI(足関節上腕血圧比)による血流評価を行い、異常が認められた場合には、MRAなどによる画像検査や血行再建(カテーテル治療やバイパス手術)を目的に、専門病院へご紹介いたします。急性期治療が終了した後は、抗血小板薬の継続や生活習慣病の管理、運動療法などを通じて、再発予防や慢性期のフォローアップを当院で行っています。